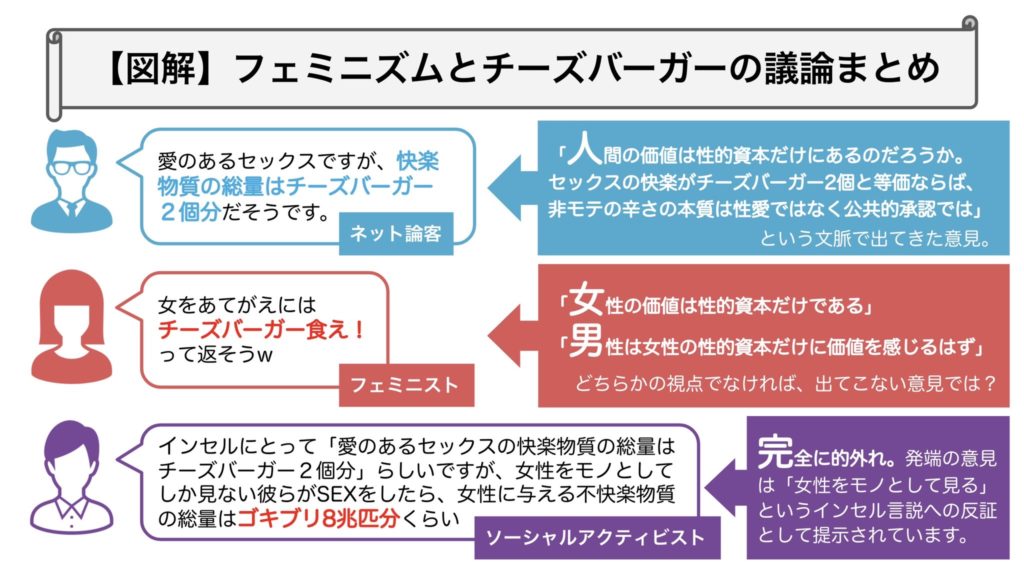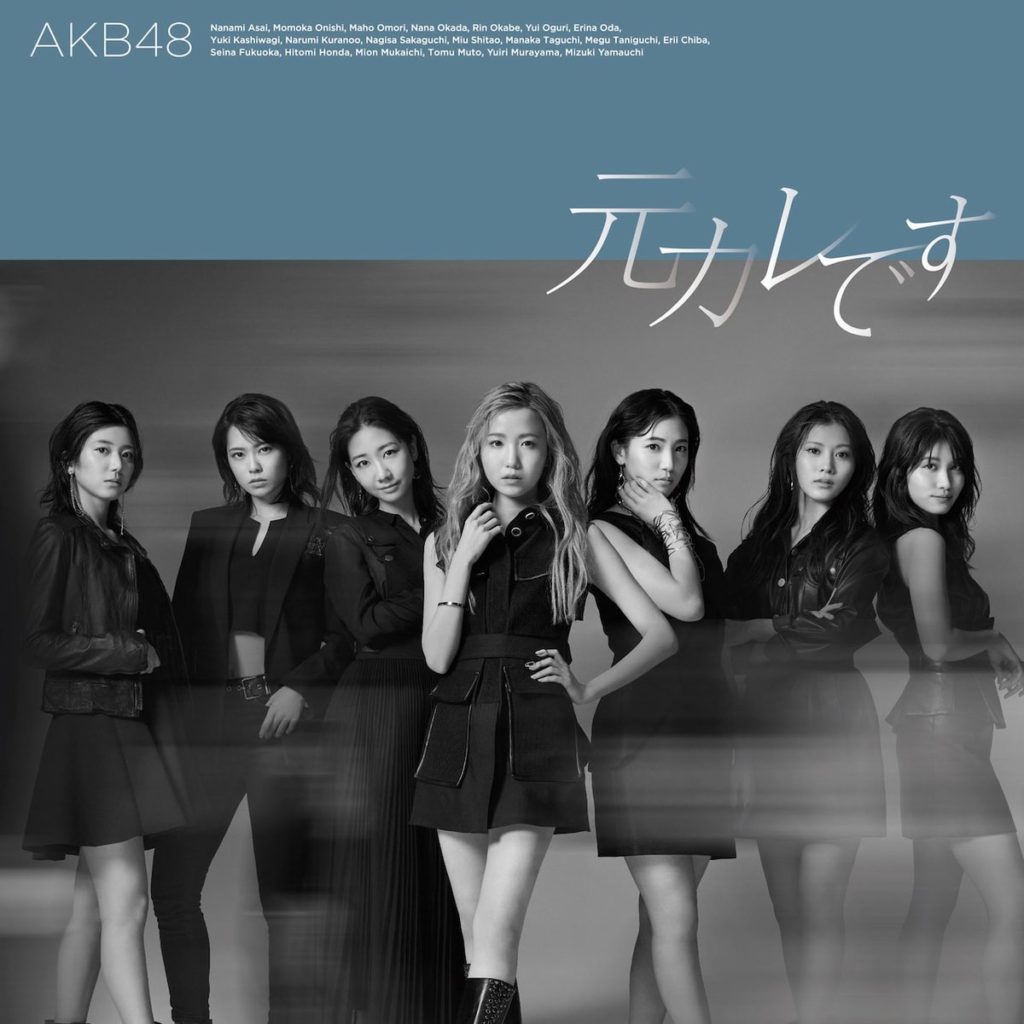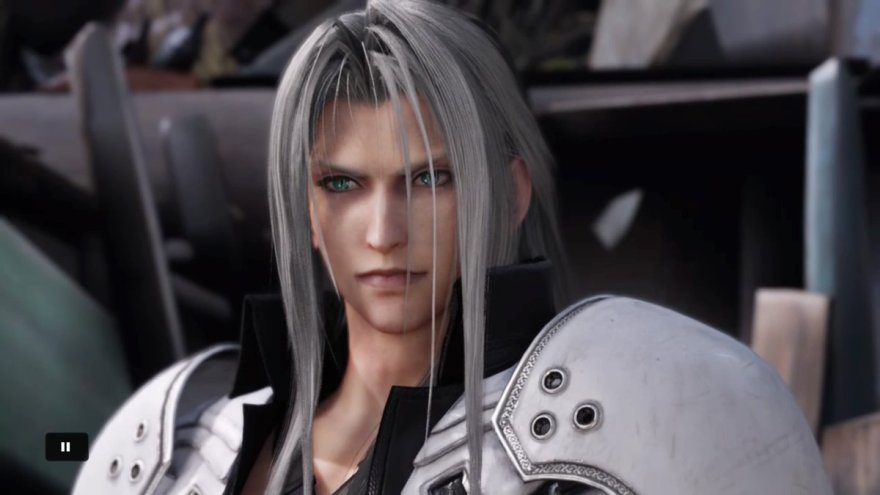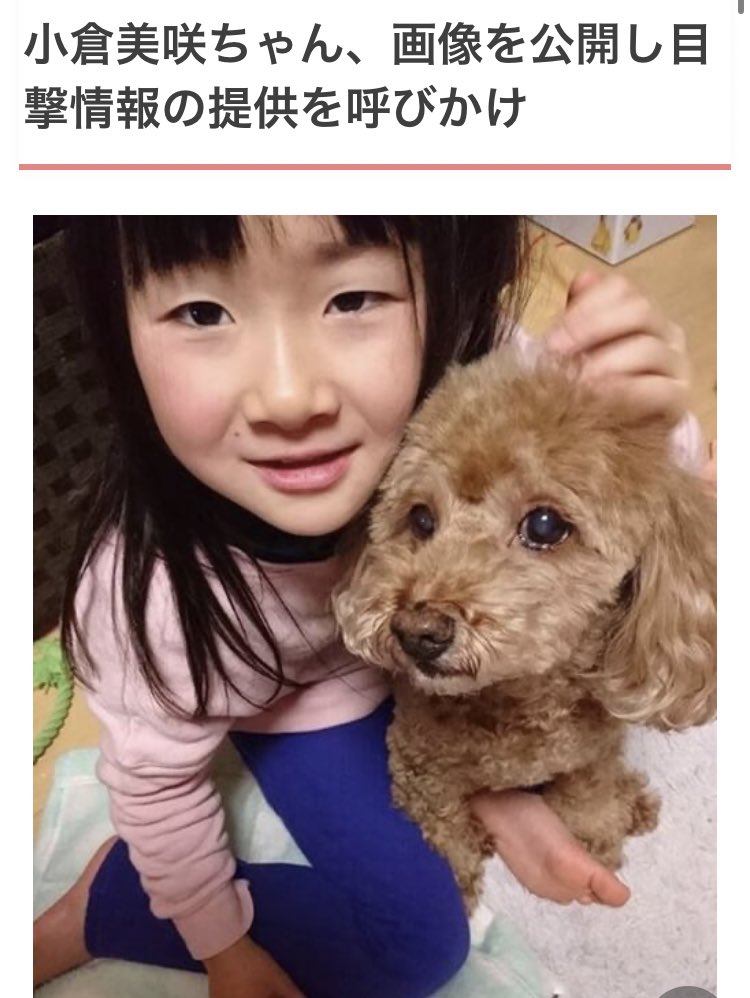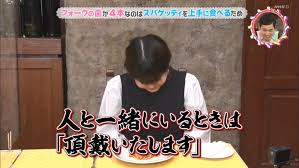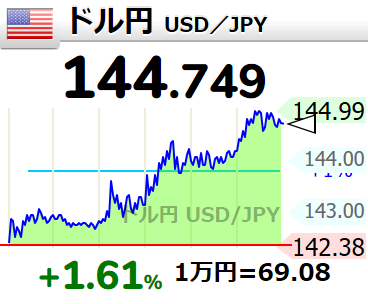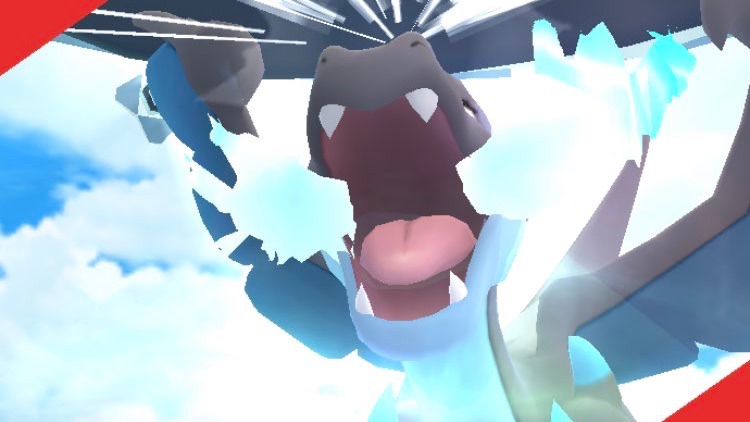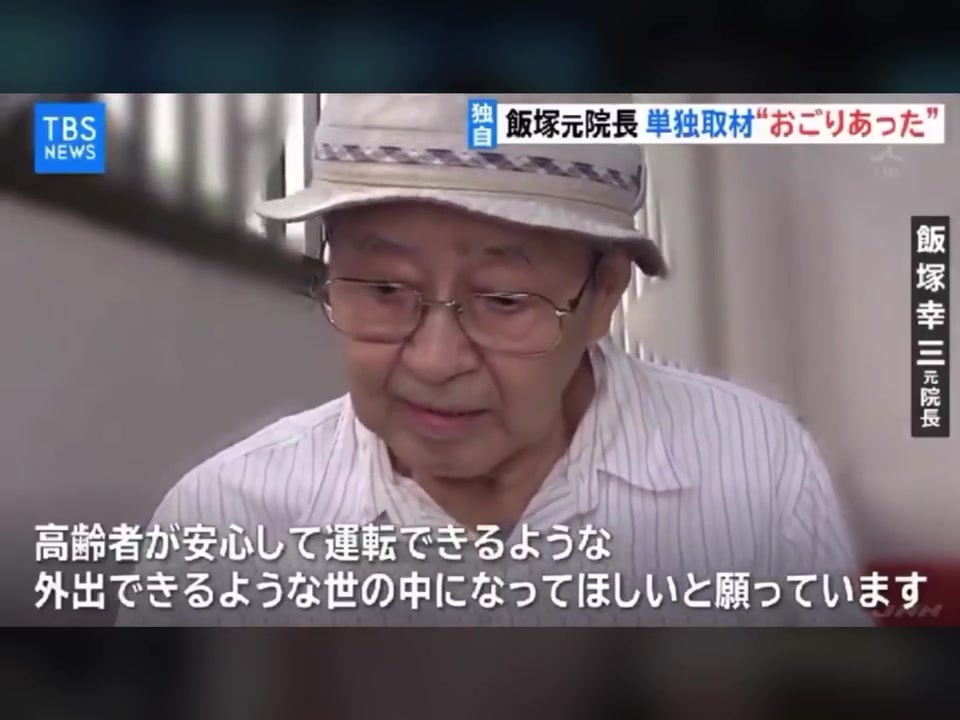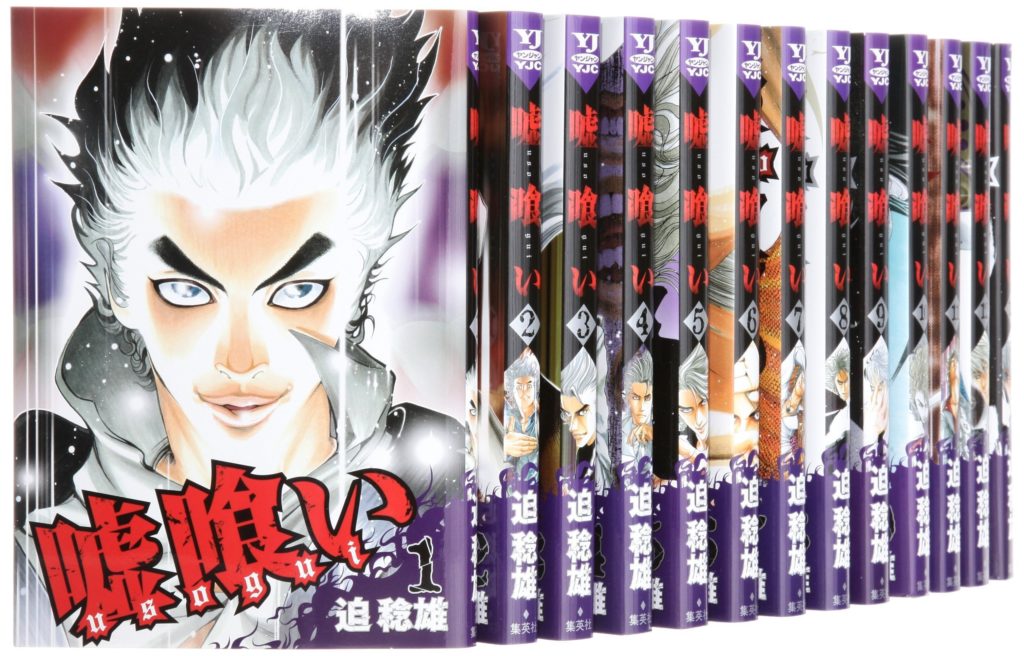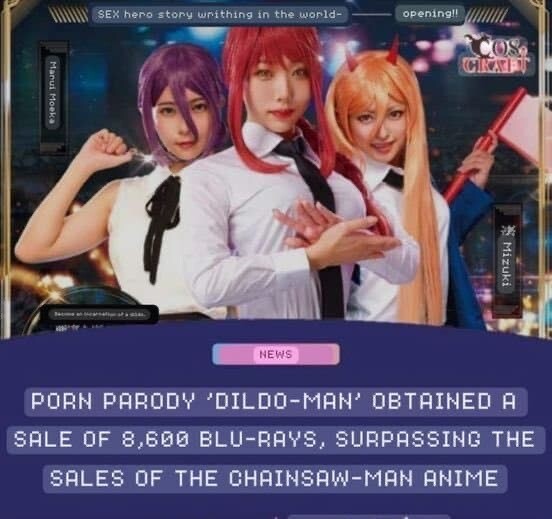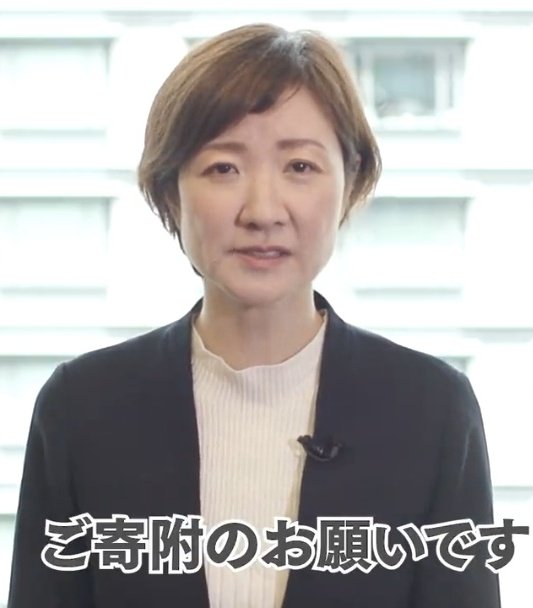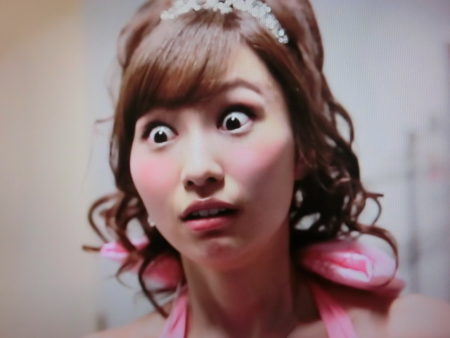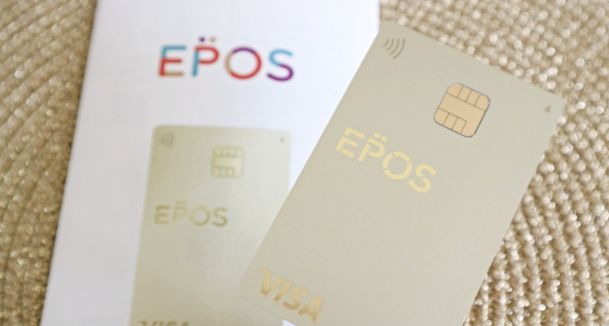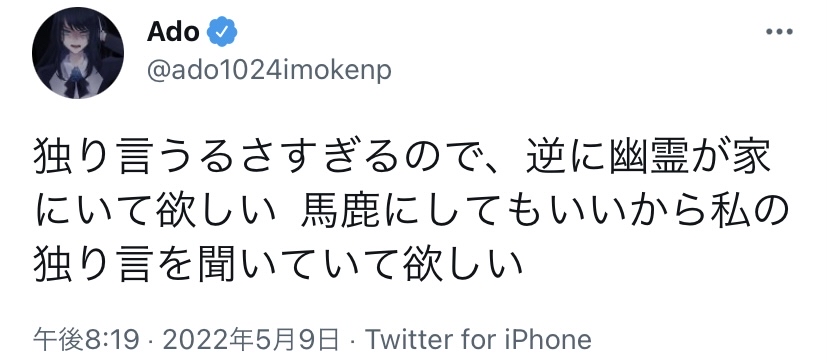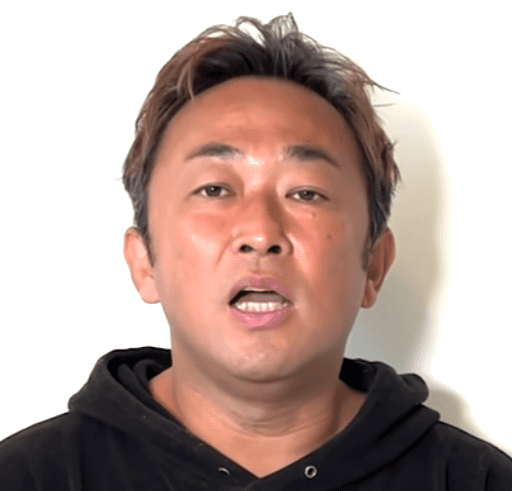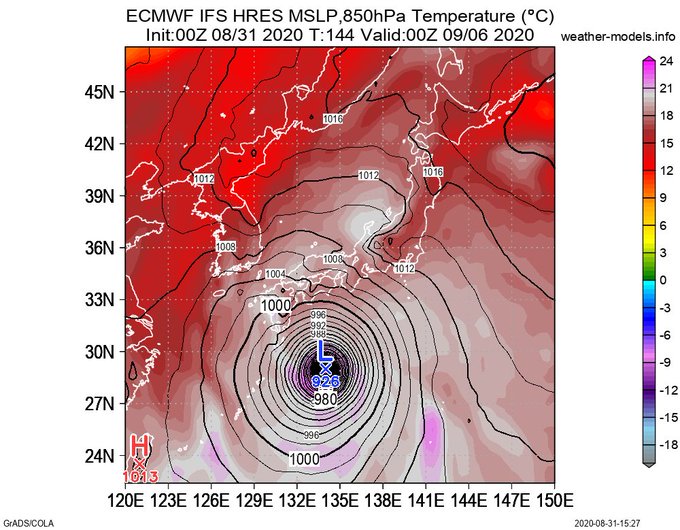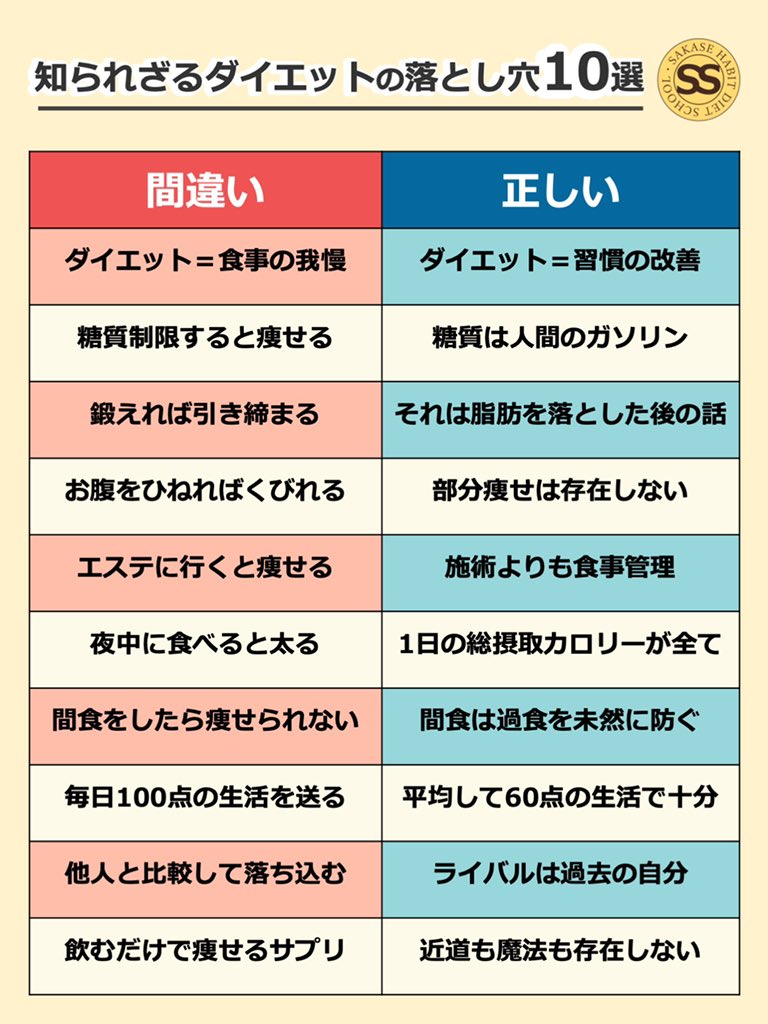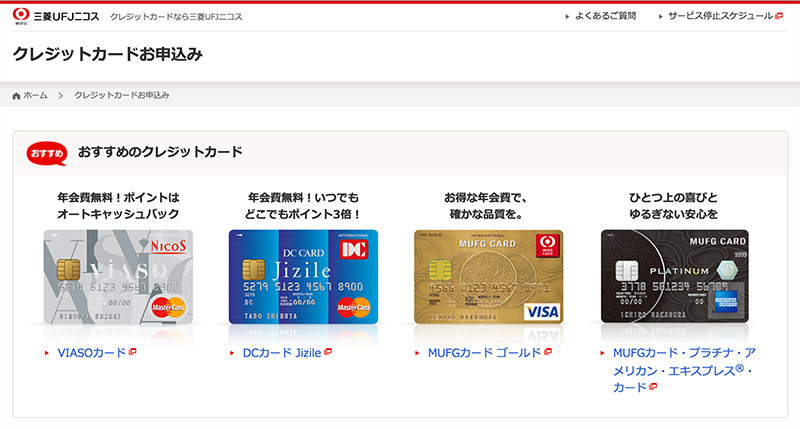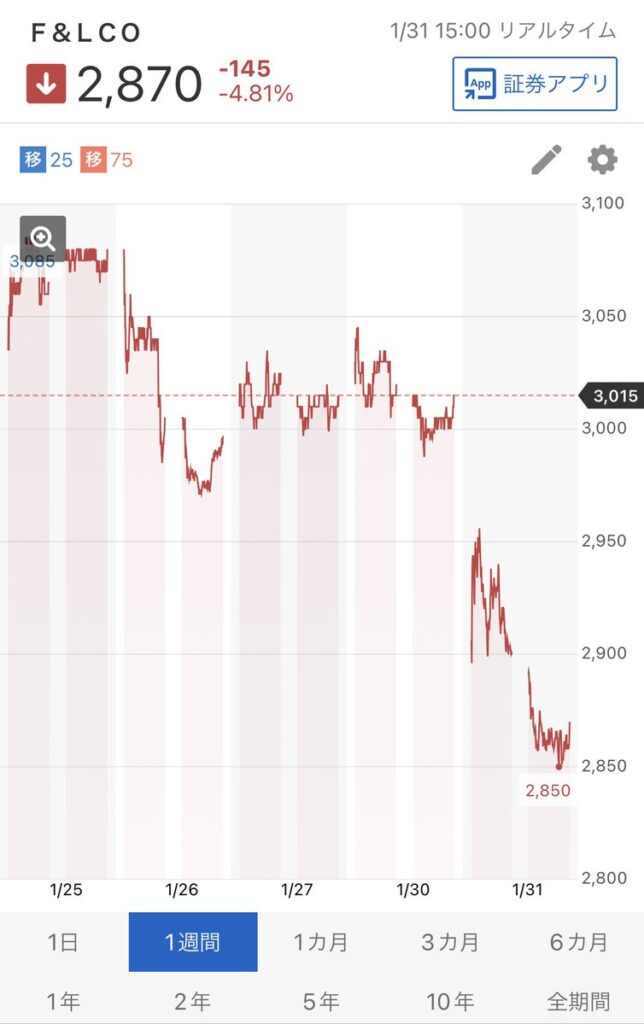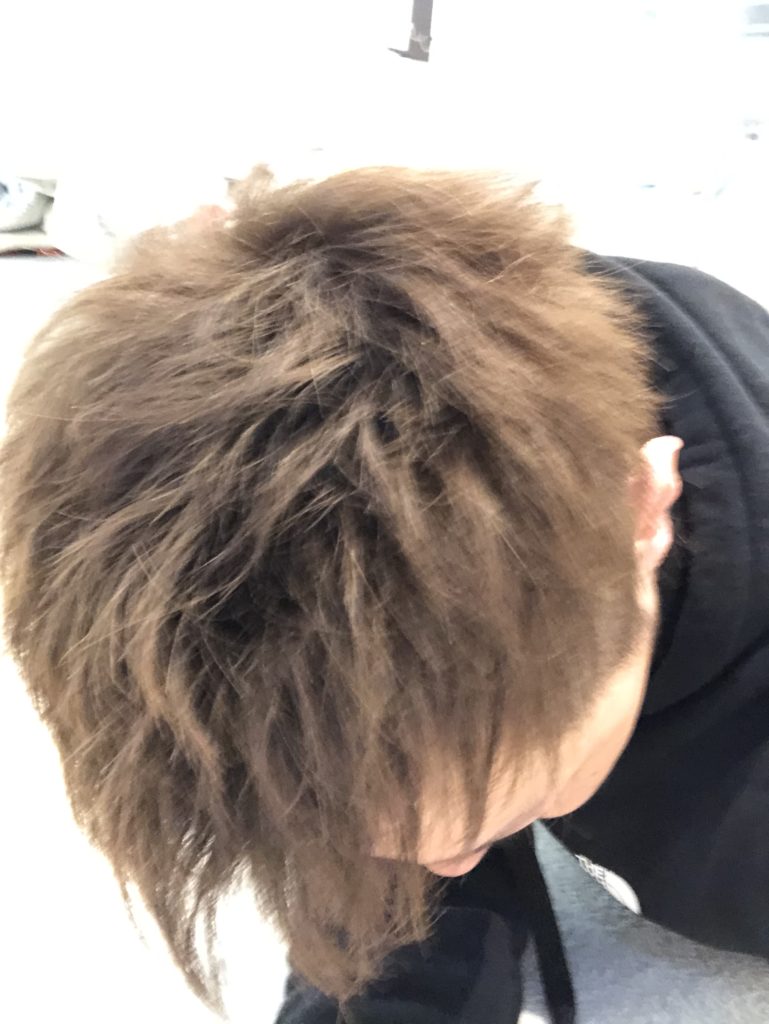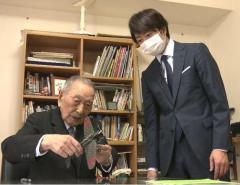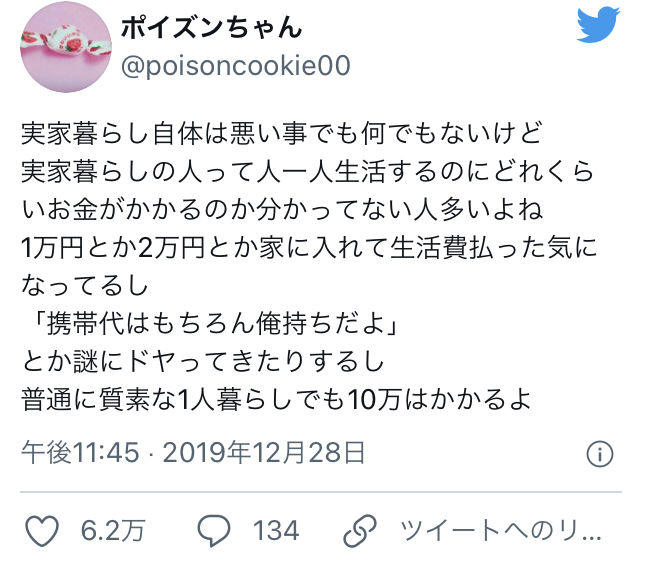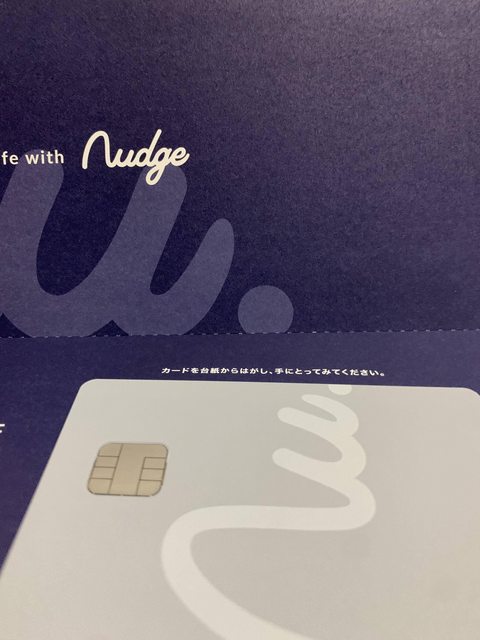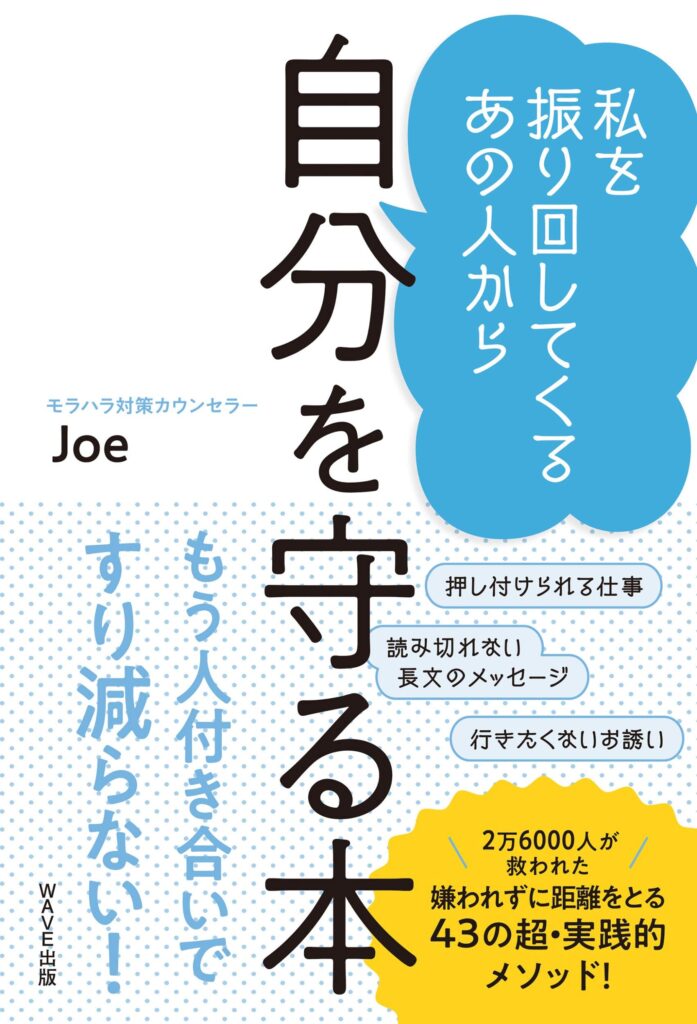戦国時代における日本の歴史は、数々の名将と彼らの野望によって彩られました。その中でも、秀吉の名前変遷と彼が「豊臣秀吉」と名乗るようになった背後にある複雑なドラマが際立っています。この記事では、秀吉の人生の転機とその意義に焦点を当て、彼が天下人への道を歩んでいく過程を紐解いてみましょう。
秀吉はもともと「羽柴秀吉」として知られており、その名前がいかにして「豊臣秀吉」と変わったのかは、彼の人生の中で重要な出来事です。秀吉の名前の変化は、彼が天下人としての地位を確立していく一環としての意味を持っています。
織田信長の死後、秀吉は明智光秀を討ち、織田家の混乱を収拾するために清洲会議が開催されました。この会議は、秀吉が発言力を高める契機となりました。しかしながら、反対派との抗争は続き、賤ヶ岳の戦いにおいて秀吉はその勢力を打ち破り、自身の地位を確立する過程が見られます。
その後、秀吉は徳川家康と織田信勝に対抗し、小牧・長久手の戦いが勃発しました。この戦いは、秀吉の発言力を一層強固なものとする契機となりました。秀吉は織田信勝との戦いを通じて、彼自身のリーダーシップと統治能力を証明し、天下人としての地位を確立していきました。
秀吉はその発言力と正当性を示すために、朝廷から与えられる位や称号を活用しました。特に、「授産民オン大納言」という位を得ることは、秀吉の野望の証であり、彼の力と地位の象徴となりました。この正当性を手に入れることで、秀吉は信勝を超え、自身の地位を強固なものとしました。
戦国時代の舞台裏では、秀吉の名前変遷は単なる名前の変化だけではなく、彼の野心と戦略の結晶でした。秀吉は、名前を通じて自身の地位を示し、その発言力と影響力を確立しました。彼の努力と戦略は、その後の日本の歴史に大きな影響を与え、戦国時代の舞台を鮮やかに彩りました。











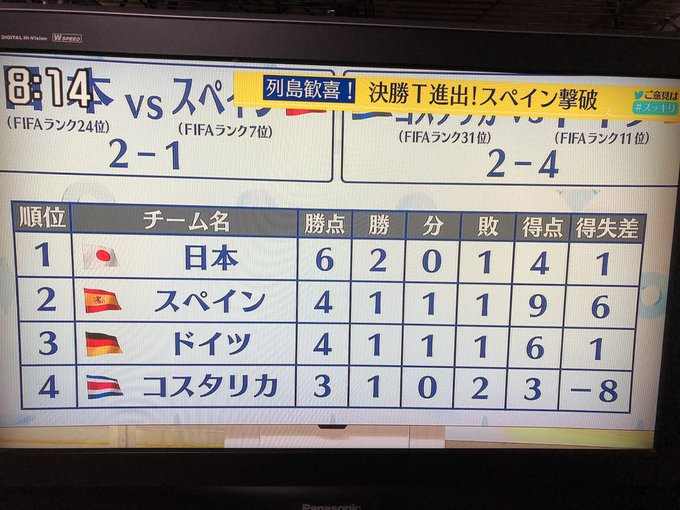



















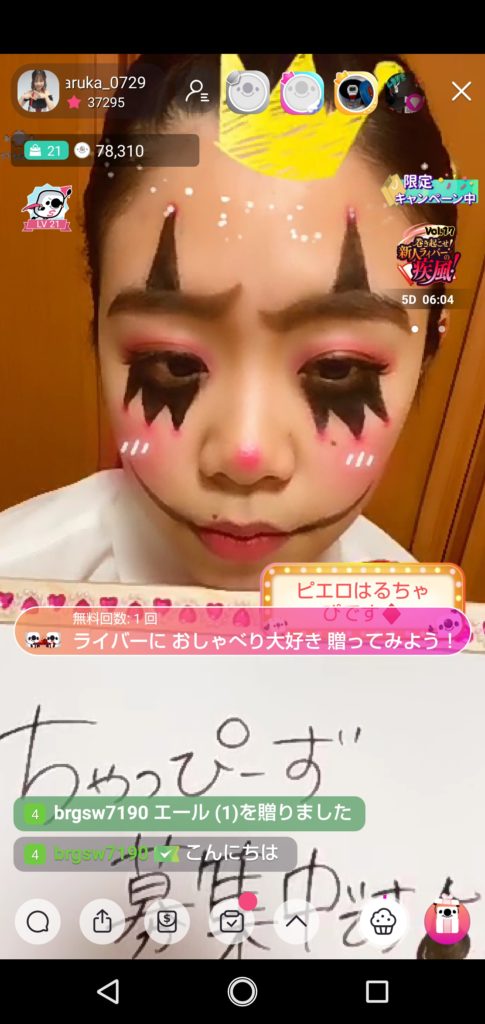


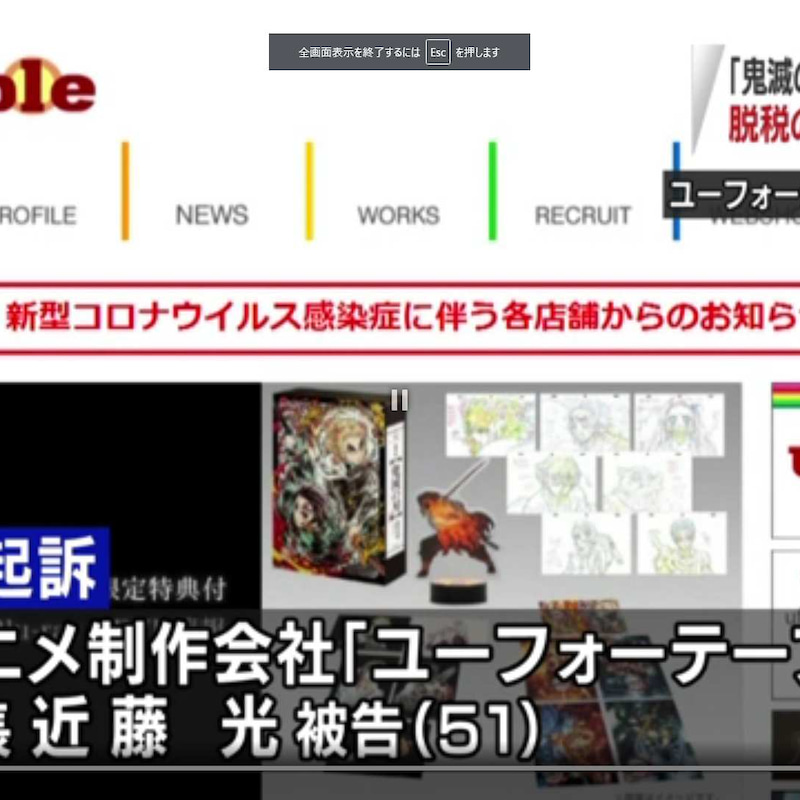







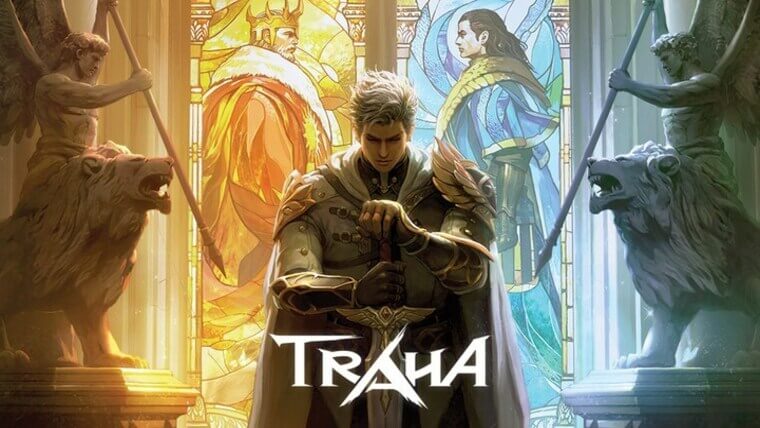





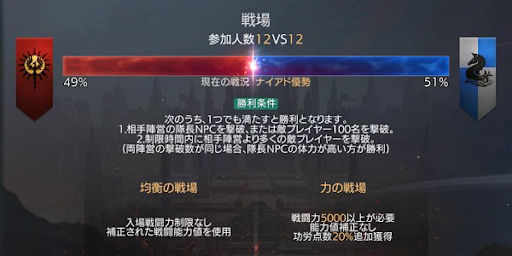
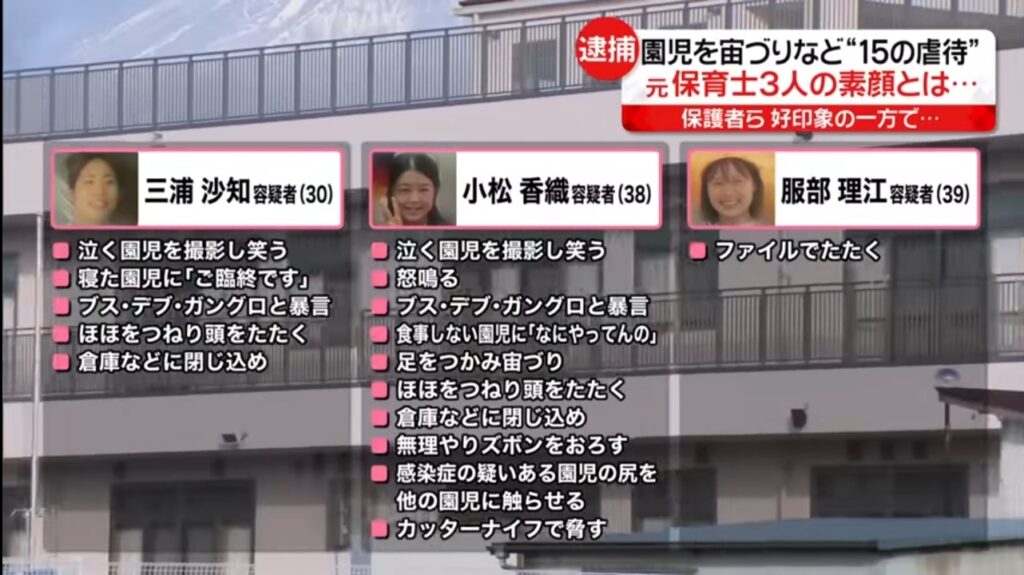




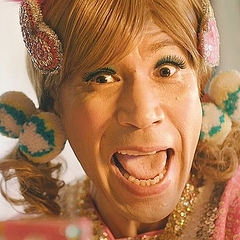


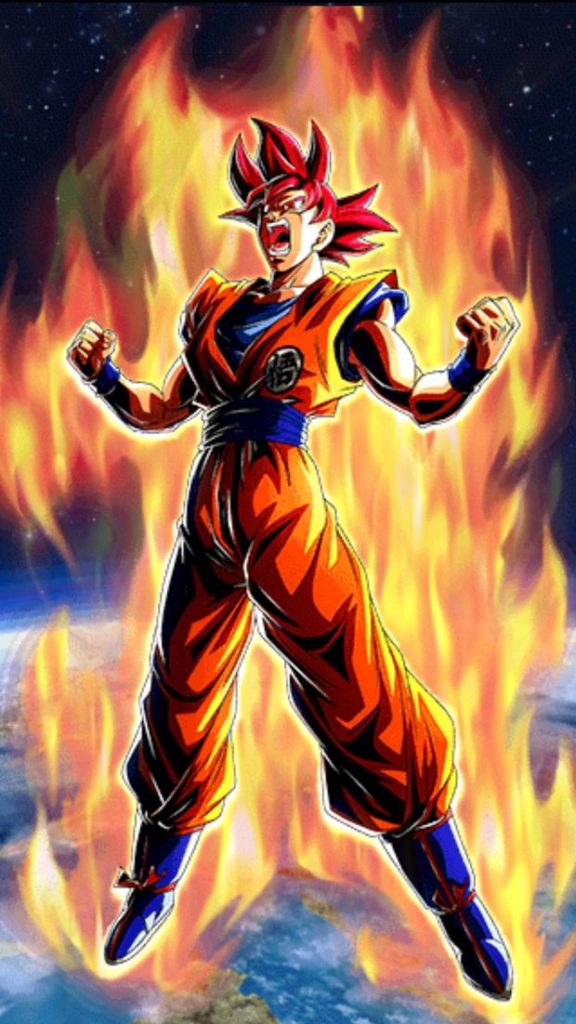
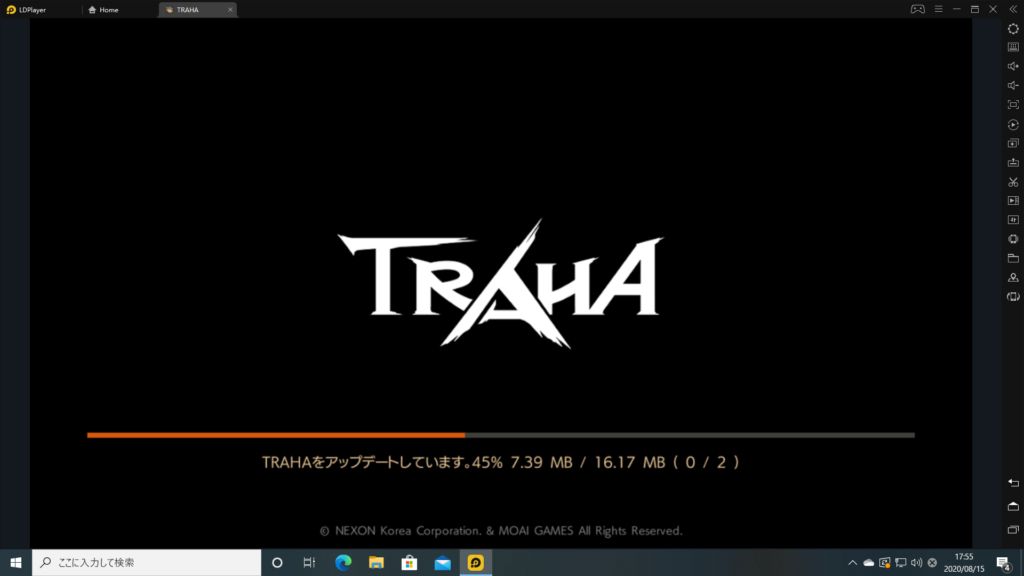















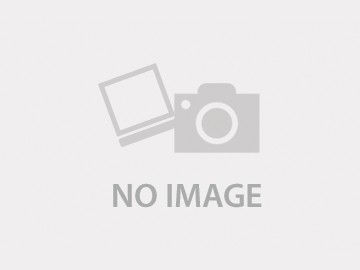


背中か・・・胸にすればおっぱい見れたよな?.jpg)