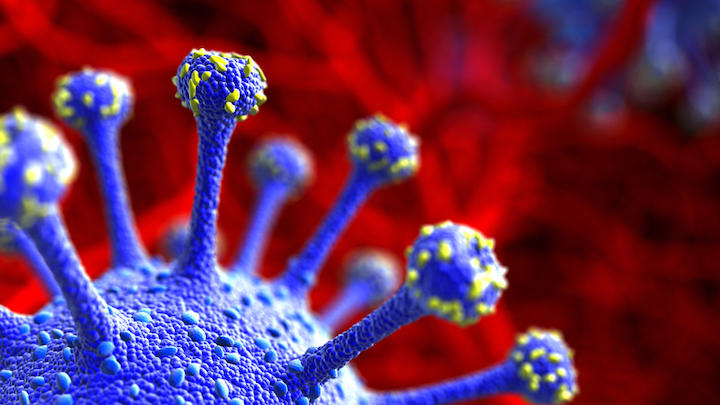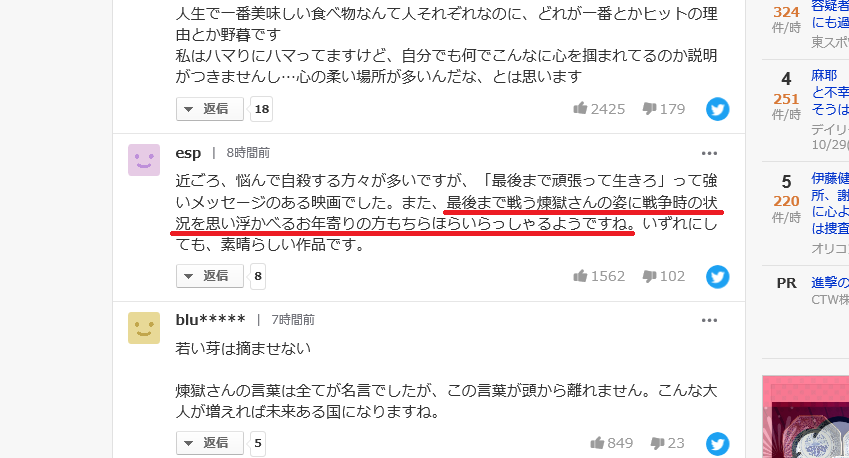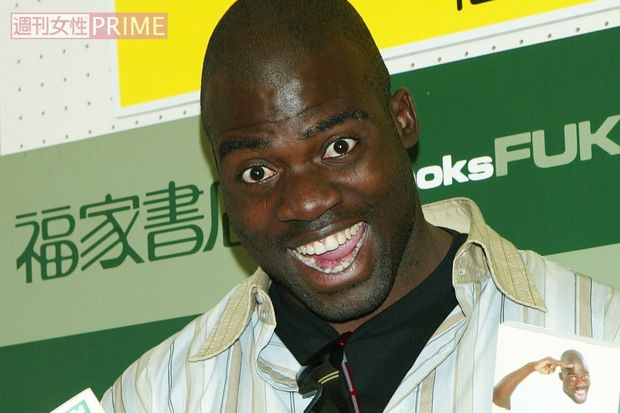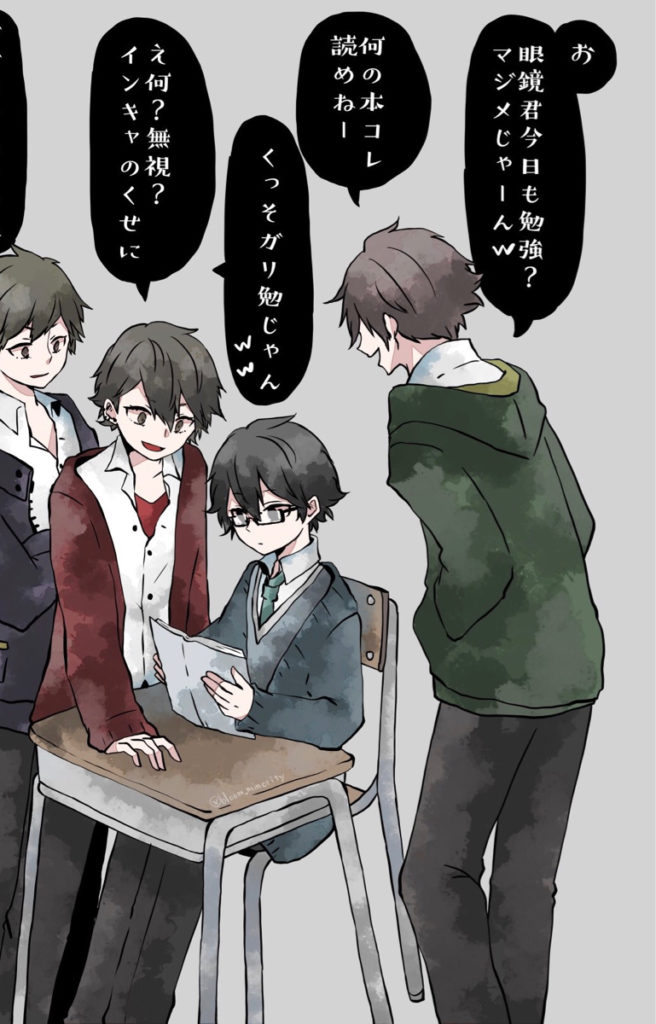この記事ではブラック企業を辞める際に考慮すべき重要なポイントについて、岡田斗司夫氏の意見を交えながら詳細に解説します。辞めた後には人間関係の破壊や過去の努力の無駄といった不安があるかもしれませんが、実際には半年後にはこれらのことがどうでもいいことになることが多いという事実を示します。さらに、ブラック企業の見分け方として、岡田氏が提唱する3つのタイプについても詳しく解説します。
【本文】
1. ブラック企業を辞める際の心配と真実
ブラック企業を辞める際には、人間関係の破壊やこれまでの努力の無駄になるのではないかという不安が頭をよぎることがあります。しかし、岡田氏によれば、実際には辞めた後の半年後にはこれらのことがどうでもいいことになることが多いとのことです。心配に囚われるのではなく、自分の将来に向けて積極的な一歩を踏み出すことが大切なのです。
2. 岡田氏によるブラック企業の3つのタイプと見分け方
岡田氏はブラック企業を3つのタイプに分類しています。それぞれのタイプについて詳しく見ていきましょう。
2.1 理想が高いがブラックスペックの企業
このタイプの企業は、理想が高く評価も高い一方で、ブラック企業のスペックに近い特徴を持っています。多くの場合、アニメ会社などがこれに当たります。絶大な人気と評価を受けながらも、厳しい労働環境に直面することがあります。
2.2 悪い経営陣によるブラック企業
このタイプの企業は、経営陣が悪いやつであり、社員をこき使う悪質なブラック企業です。こうした企業では従業員の労働条件や給与が不適切であり、働く人々の負担が非常に大きくなります。
2.3 普通のブラック企業
このタイプは、一見普通の企業に見えるが、実際には社員同士がお互いを遠慮して残業が増えるなど、ブラック化している企業です。誰も悪意を持っているわけではないが、結果的にブラックな状態に陥っているケースです。
3. 自分の会社がどのタイプに該当するか考える
岡田氏は読者に対し、自分が所属している会社がどのタイプに該当するかをよく考えるように促しています。それぞれのタイプに応じた対処法が異なるため、自分だけはサボっても居心地が悪くならない方法を見つけることが重要だと述べています。自身のキャリアを見つめ直し、前向きに未来を切り開くための一歩として、自分の置かれた環境をよく理解することが必要です。
4. ブラック企業の見分け方としての参考例
岡田氏は、ジブリやカラー、プロダクションIDなどの一部の企業が確実にブラックだと考えられると指摘していますが、一般的な企業の見分けは難しいことを述べています。ただし、ブラック企業である可能性が高いと感じる場合には、労働条件や給与の面で注意深く調査することが大切です。
5. ブラックな事態を見過ごす経営者と株主の利益
ブラックな事態を見過ごしたり黙認したりするのは、会社が成長して現場がブラック化していく結果として起こります。経営者や株主は、利益を最大化するために、従業員との対立関係を受け入れることがあると指摘されています。このような状況下で、会社の人間として自覚を持ち、ブラックな状態に対して率直に向き合うことが求められるのです。
【まとめ】 ブラック企業からの脱出には、辞めた後の不安を乗り越える勇気と、自分の会社がどのタイプに該当するかを正確に見極める洞察力が必要です。岡田氏が提供するブラック企業の3つのタイプと見分け方は、脱出するための道しるべとなるでしょう。
一つ目のタイプでは、理想が高く評価も高いがブラックスペックに近い企業が挙げられます。絶大な人気を持つアニメ会社などがこれに当たりますが、良い評価に惑わされず、労働環境を見極めることが大切です。
二つ目のタイプは、経営陣が悪いブラック企業であり、社員をこき使う不正な状態です。こうした企業では、適正な労働条件や給与が欠如していることが多く、離職を考える要因となるでしょう。
三つ目のタイプは、見た目は普通の会社に見えますが、従業員同士がお互いを遠慮し、残業が増えるなどブラック化している場合です。互いに良い関係を築くことが大切で、ブラックな事態を改善するために協力することが必要です。
自分の会社がどのタイプに該当するかを考えることで、脱出への第一歩を踏み出すことができるでしょう。それには、自分だけはサボっても居心地が悪くならない方法を見つけることが大切です。無理な残業や過度なストレスを避け、自分のキャリアを健全に育てることが重要です。
また、ブラック企業の見分け方として、特にジブリやカラー、プロダクションIDなど一部の企業は確実にブラックである可能性が高いと指摘されていますが、一般的な企業の見分けは難しいこともあります。その場合には、労働条件や給与などの点に注意を払い、ブラック企業との違いを見極めることが求められます。
最後に、ブラックな事態を見過ごす経営者や株主の利益追求に対して、会社の従業員として率直に向き合う姿勢が必要です。ブラックな状況に対して無関心でいることは、会社全体の健全な発展を妨げることとなります。したがって、各個人が意識的に改善を促し、ブラック企業としての問題点を解決するために積極的に関わることが重要です。
辞めれないは危険信号⁉ 辛い時は逃げても良い 辞める時の3つの事【ブラック企業】「3種類のブラック」「絶対やめるべき会社」「楽しいブラック」「ブラックからの抜け出し方」






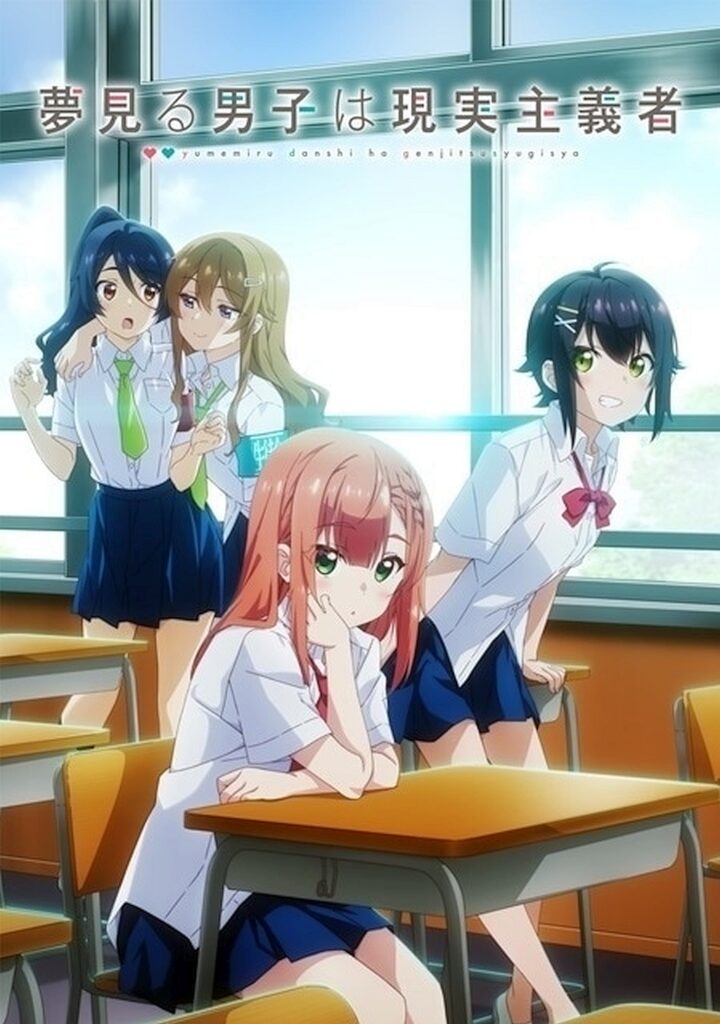










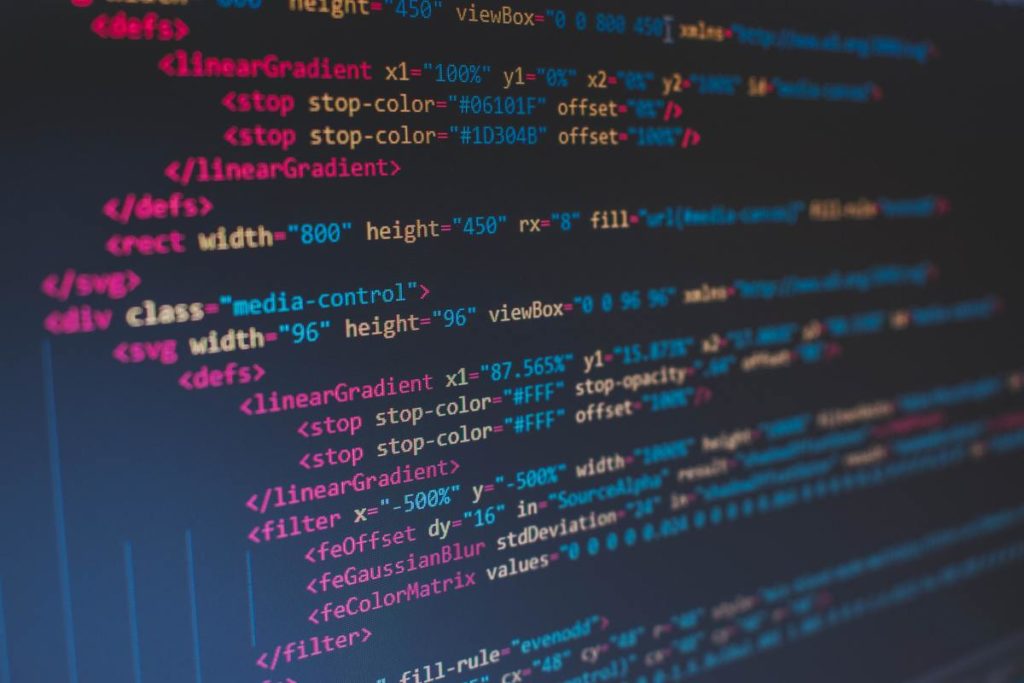


















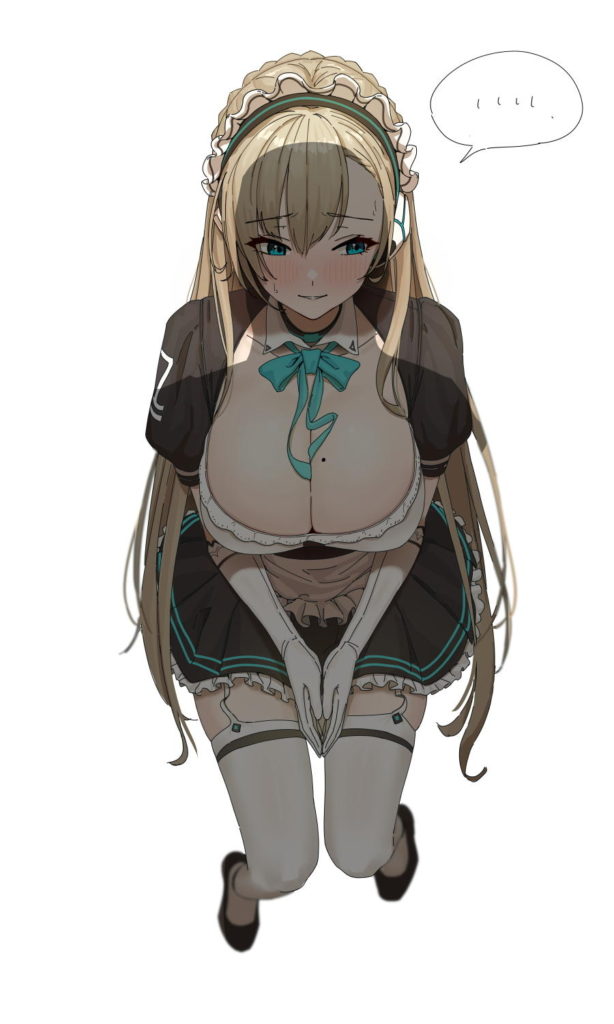



















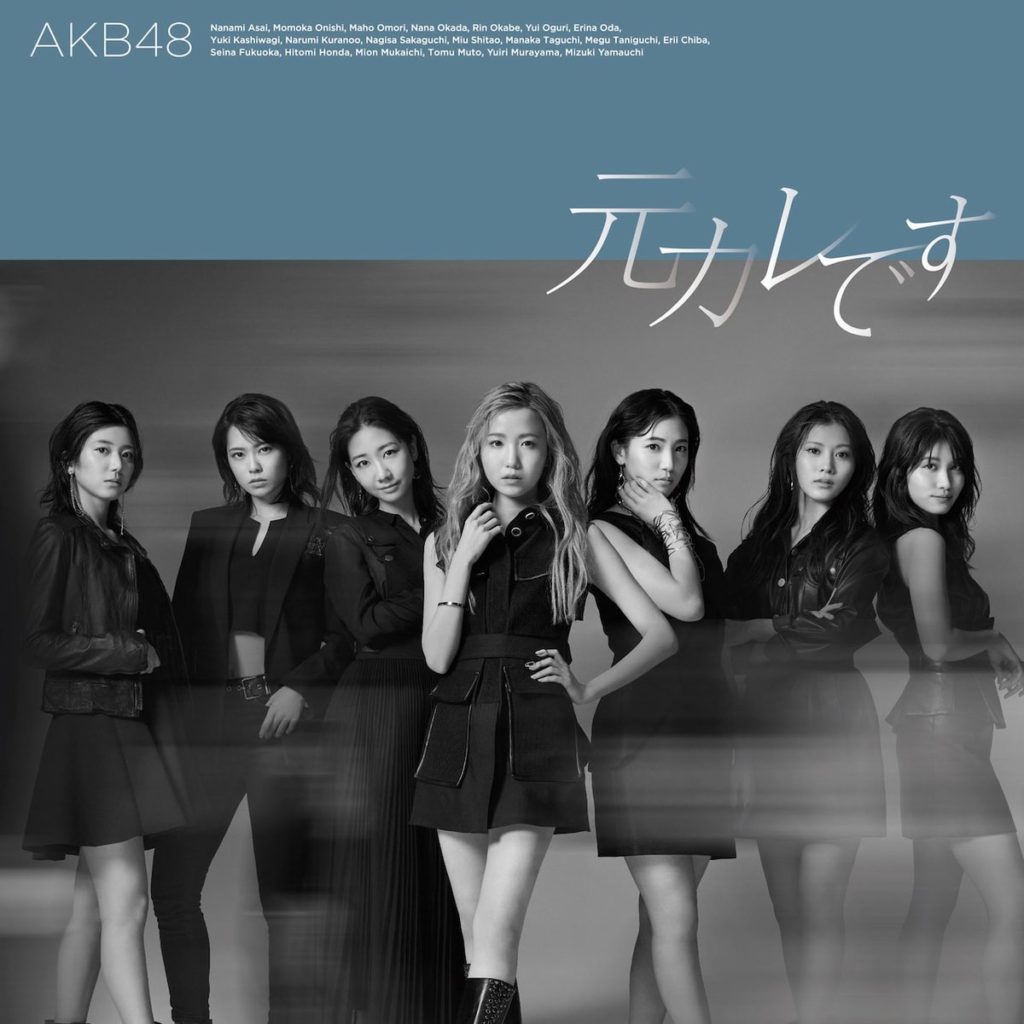

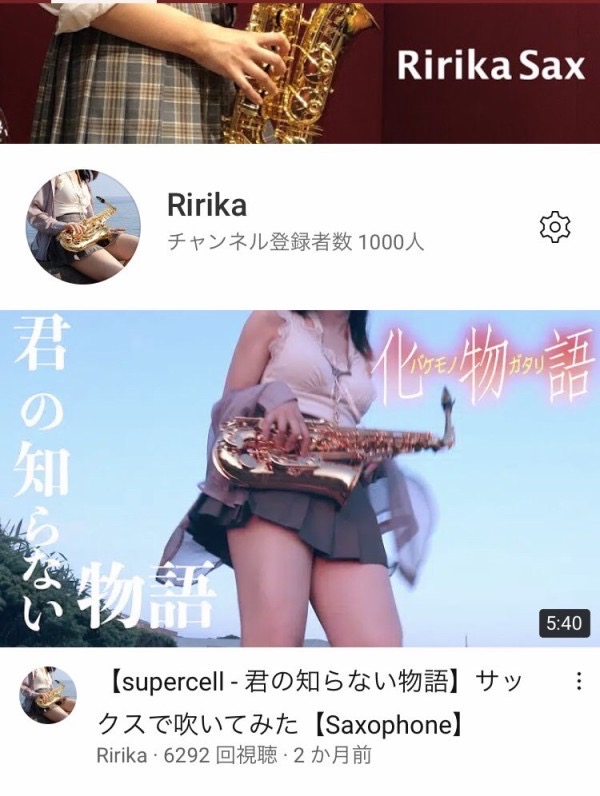





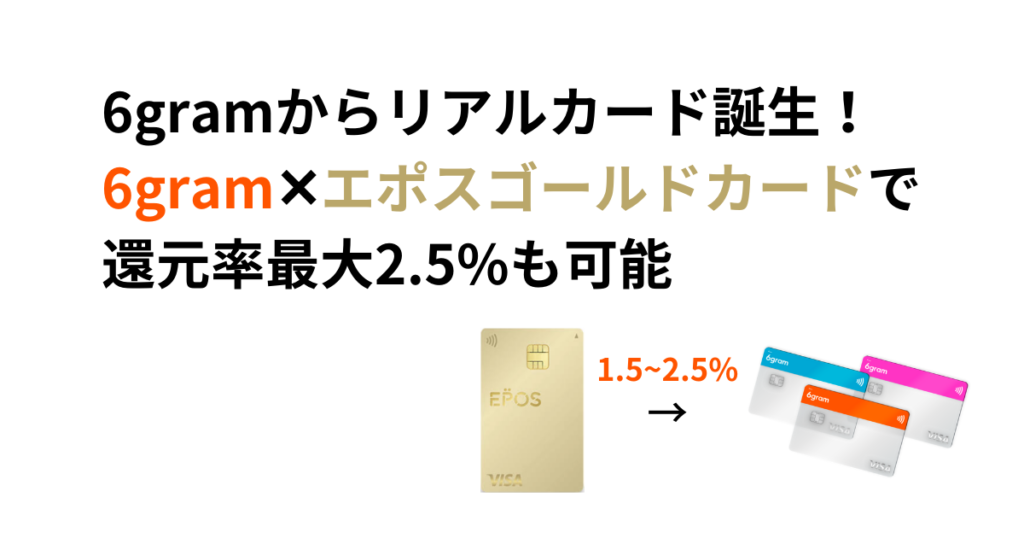














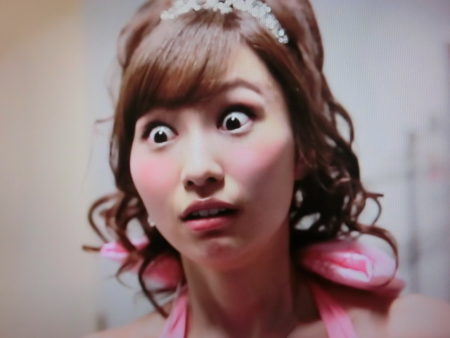

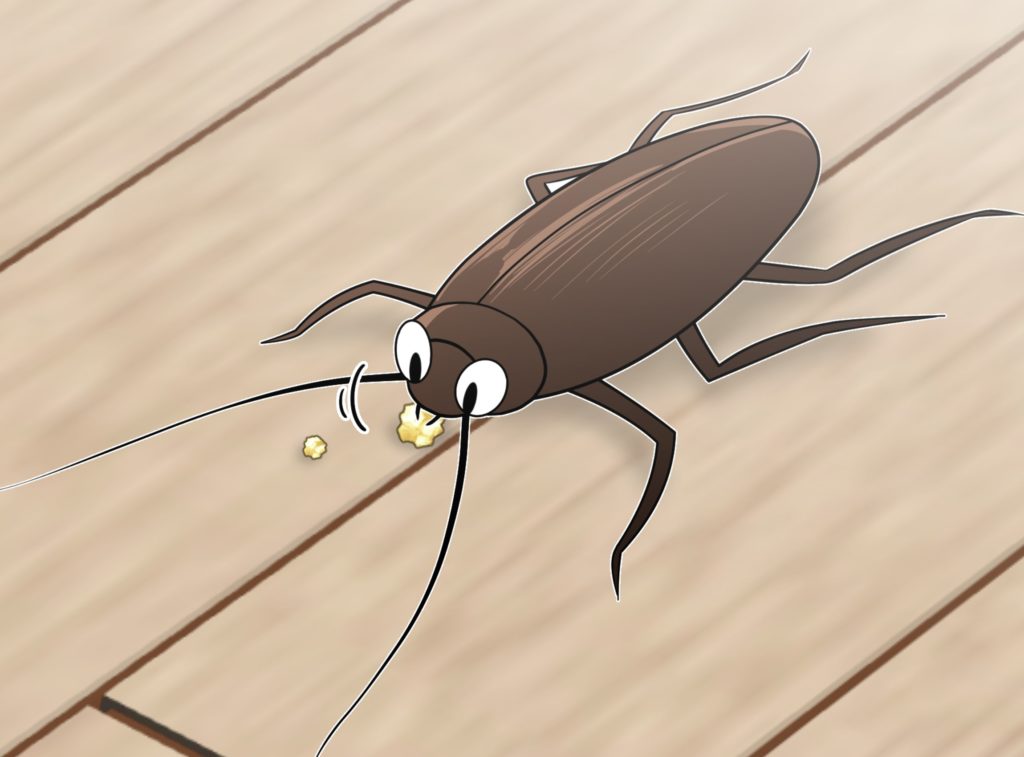





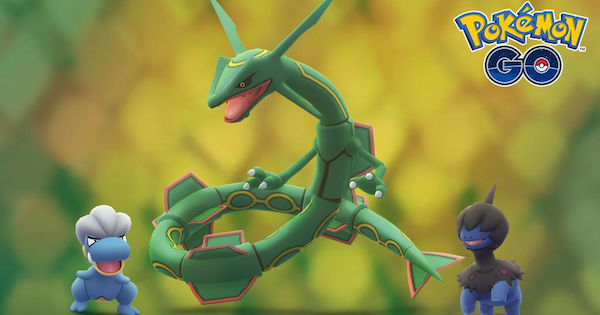



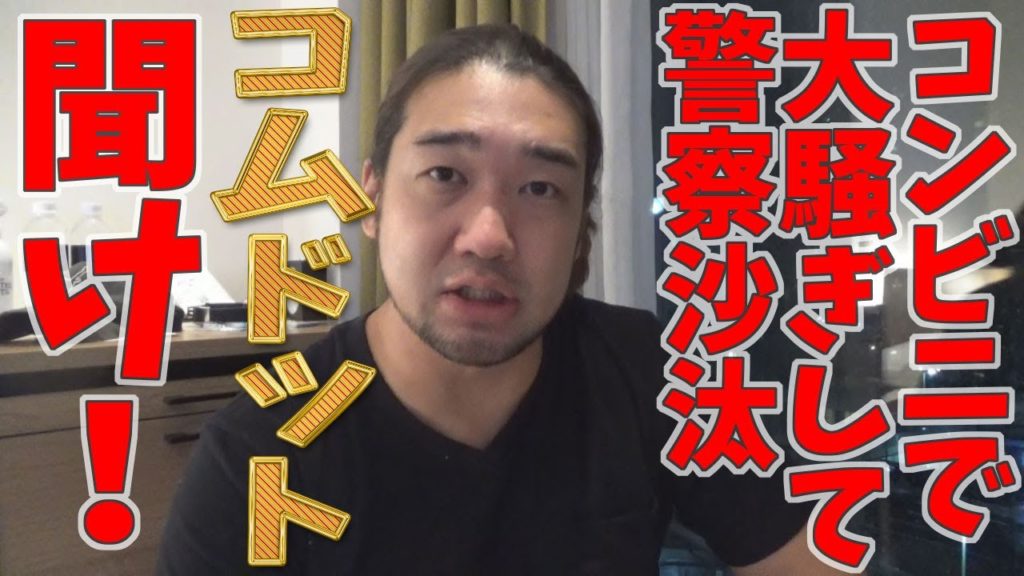







(わが国で未承認の難治性ニキビ治療薬).jpg)


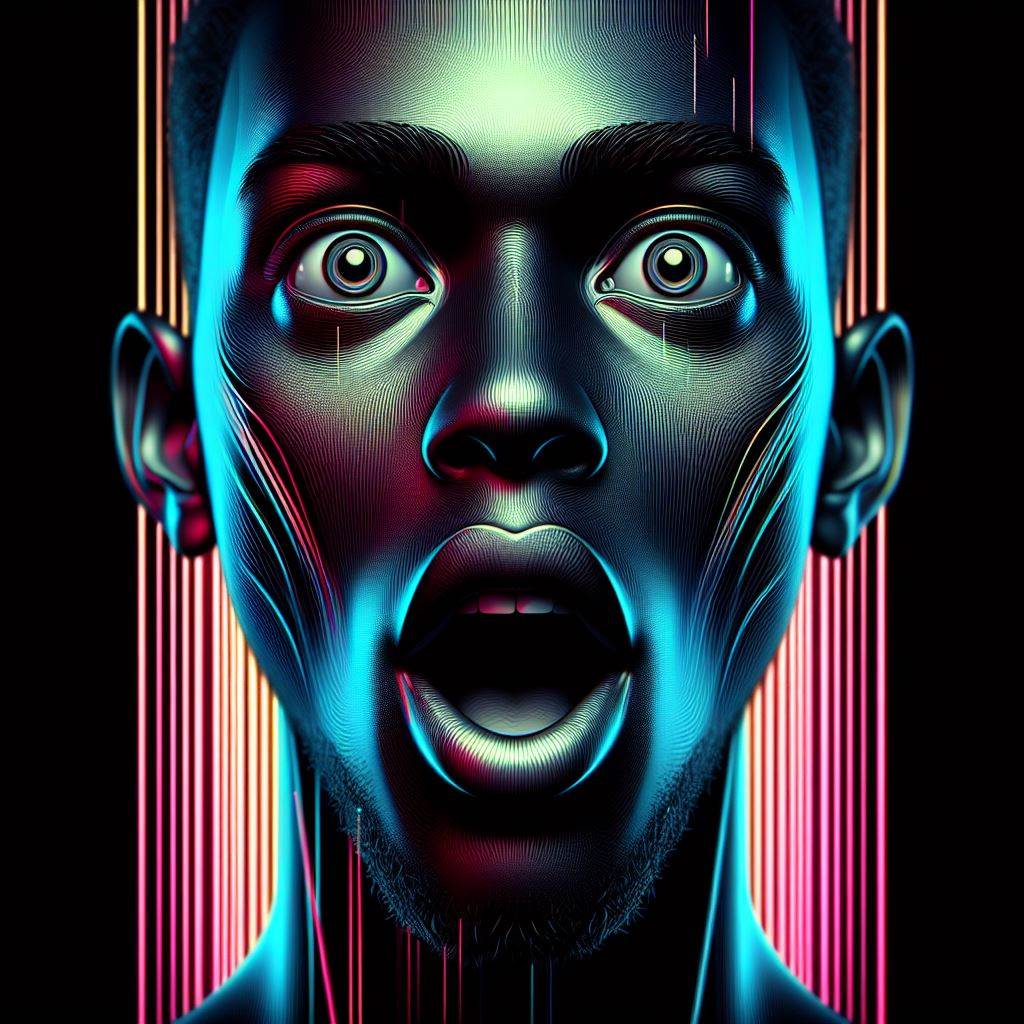







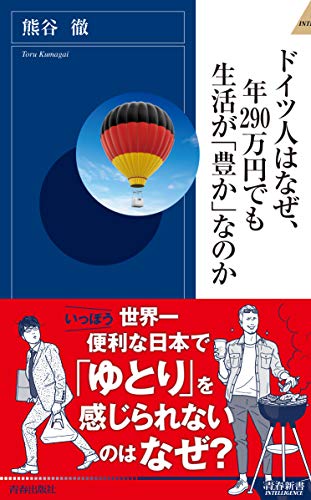







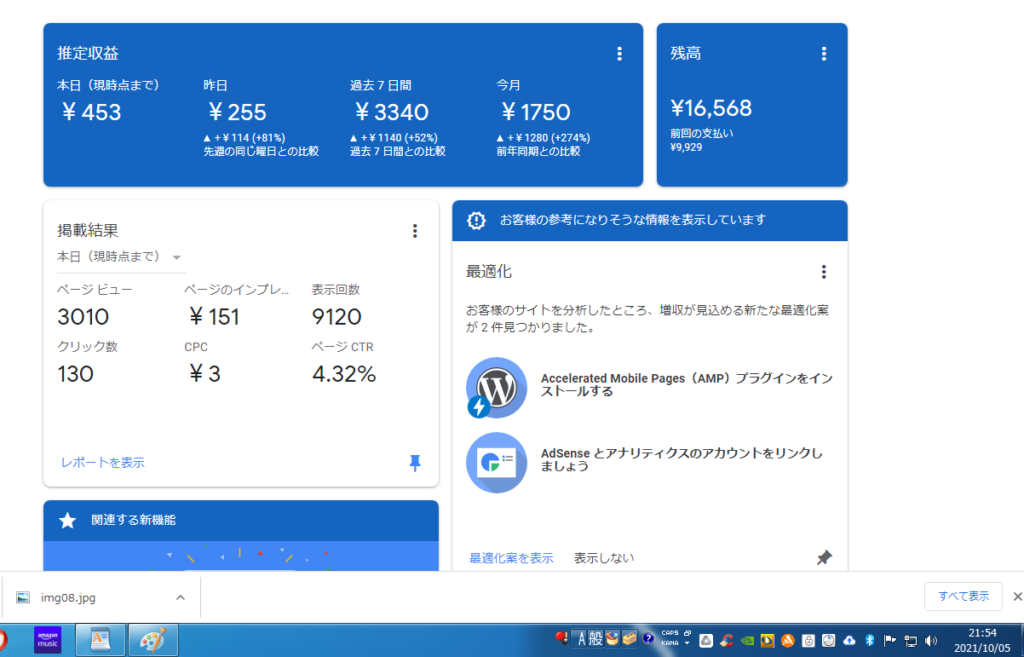
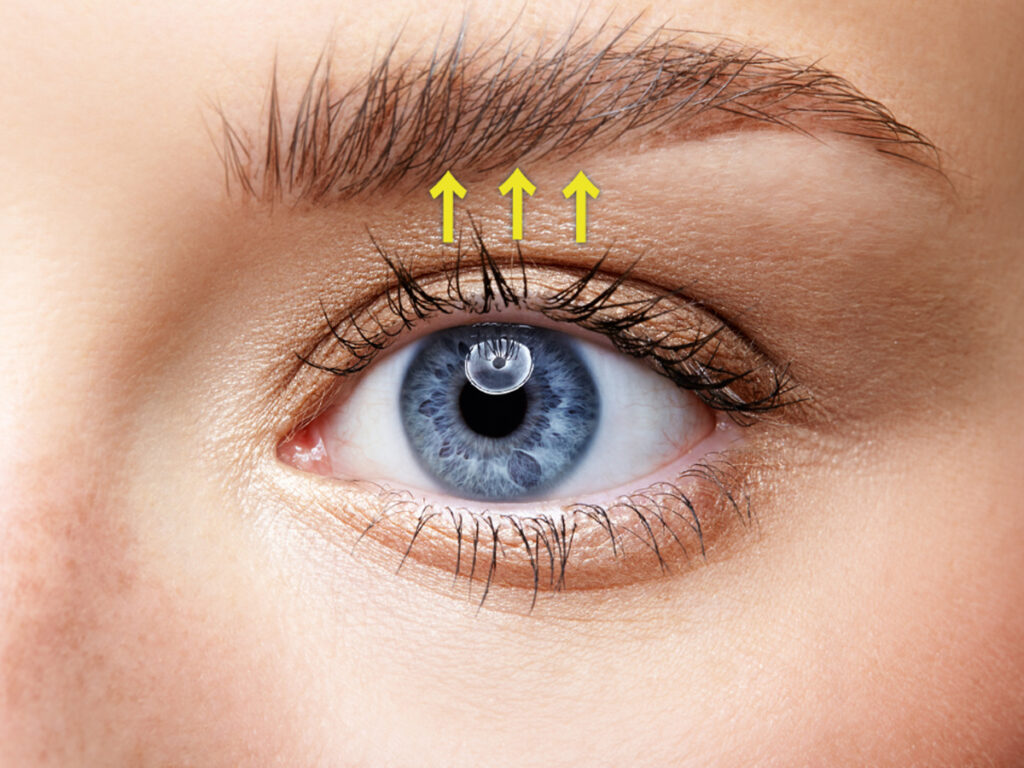

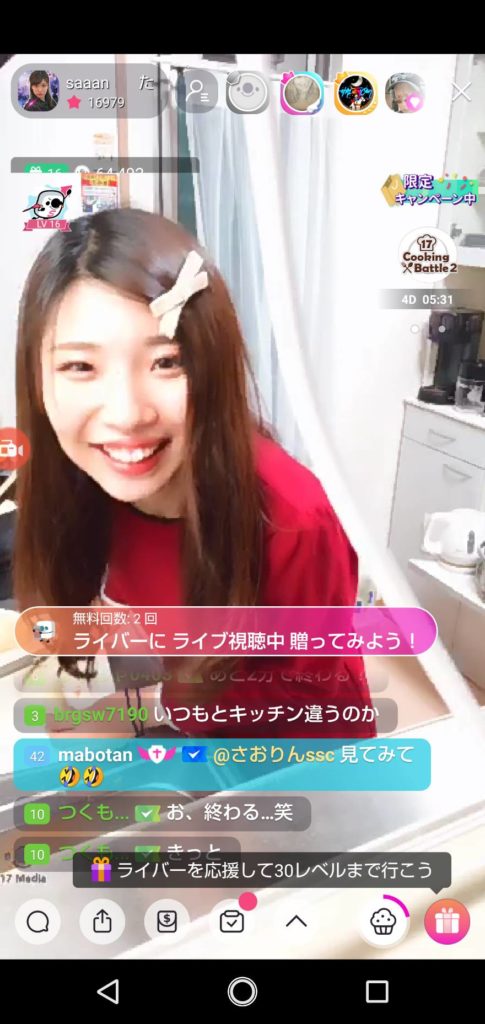







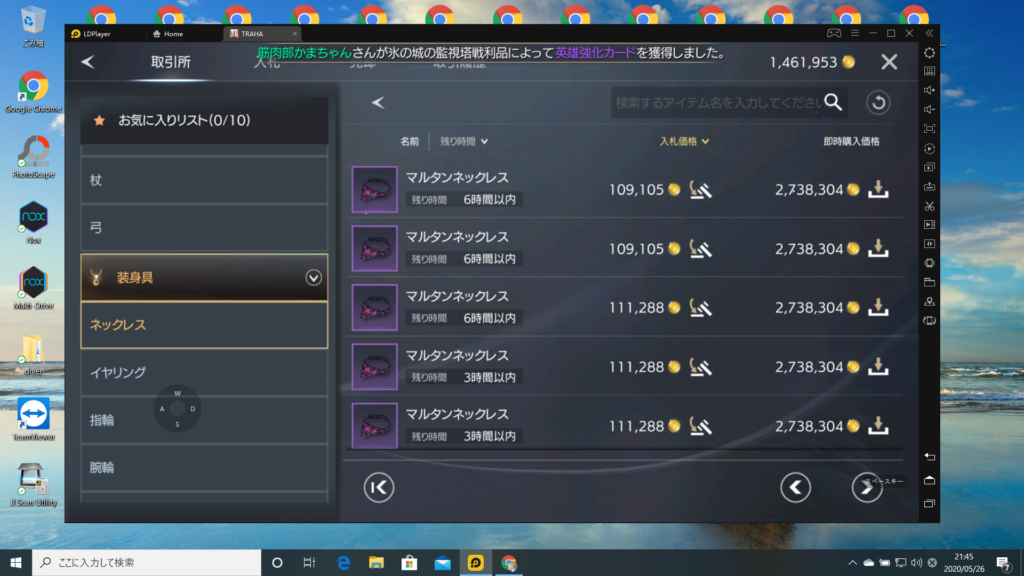

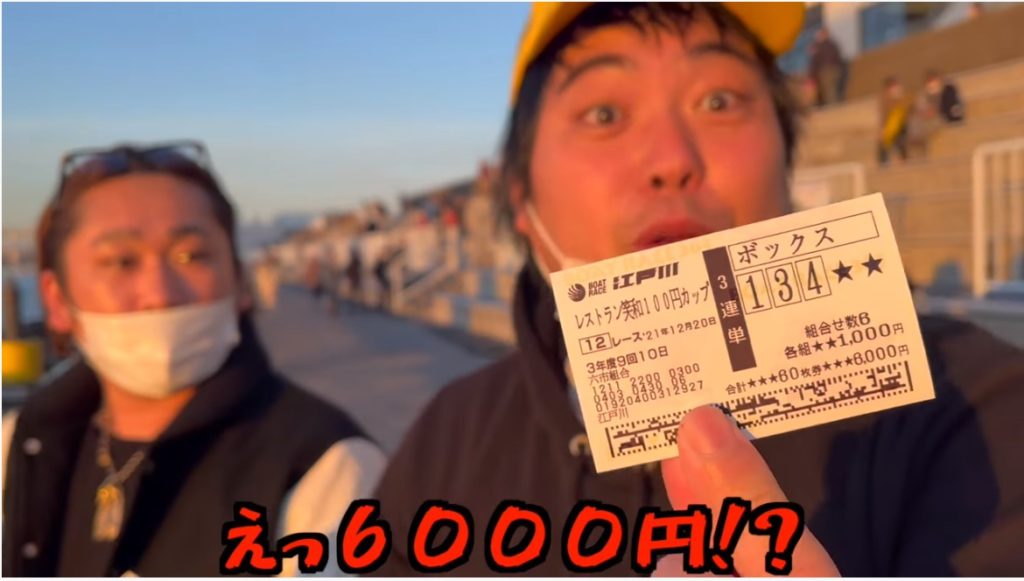

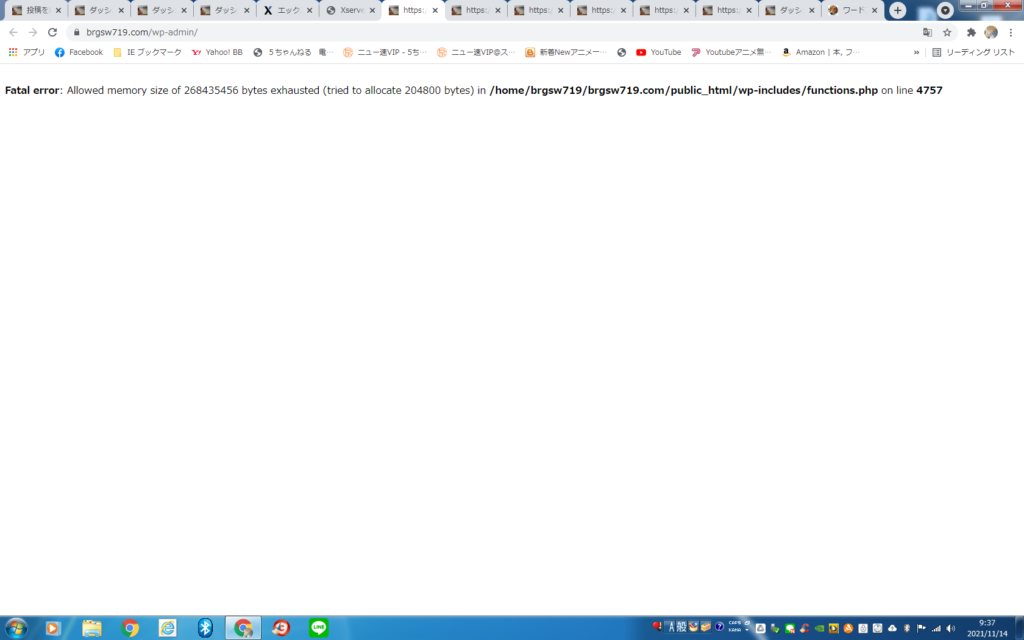

















のチアガールさん美人すぎる!!.jpg)
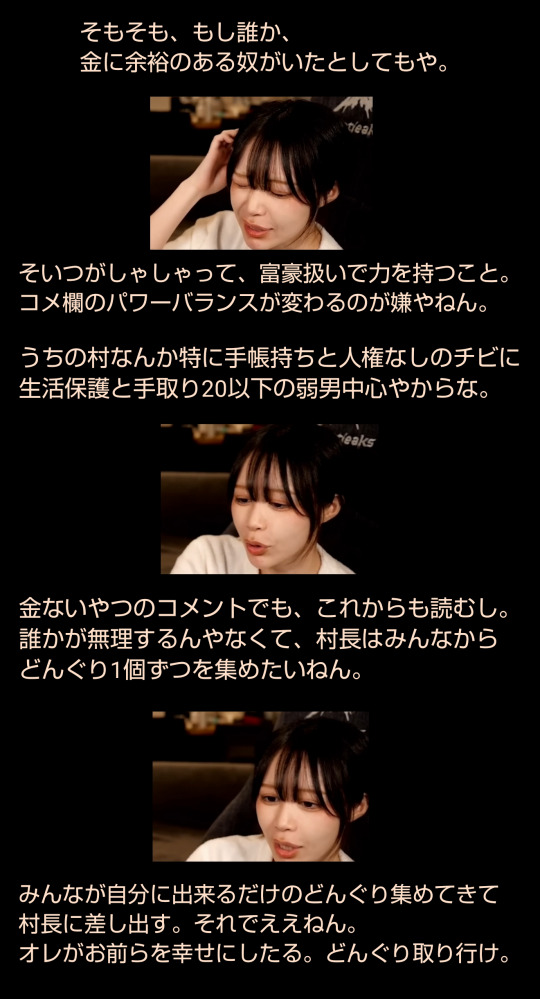




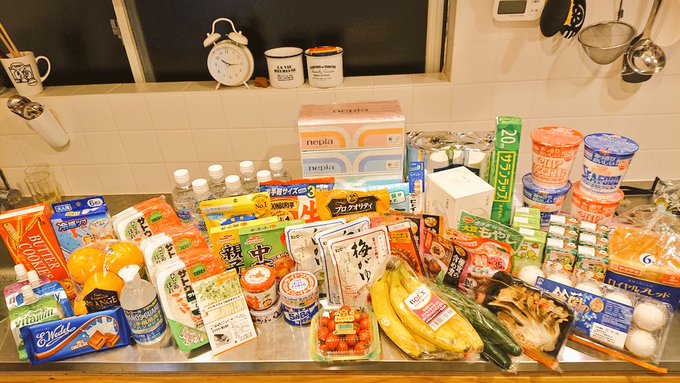

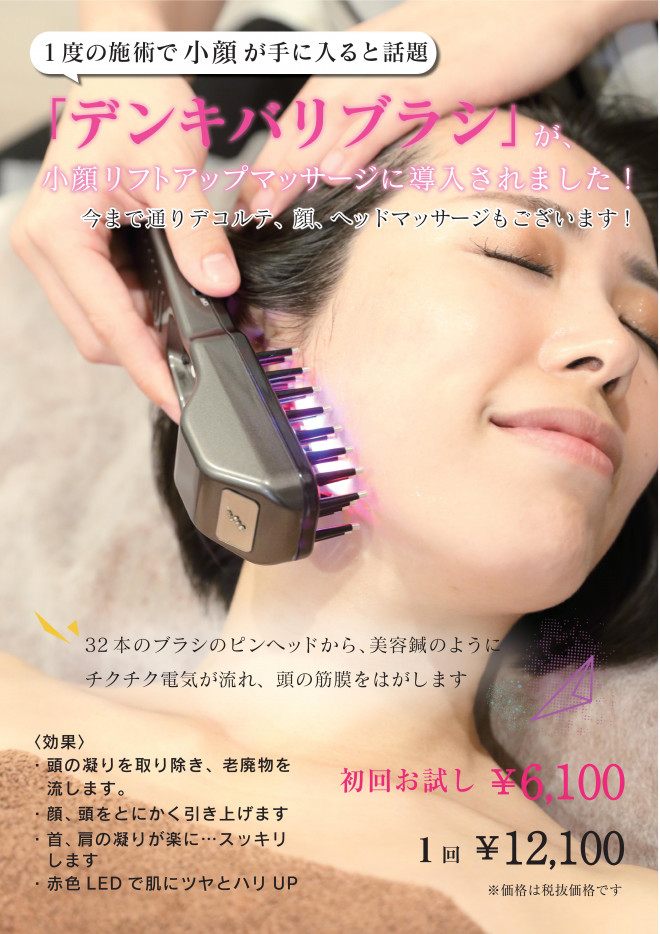















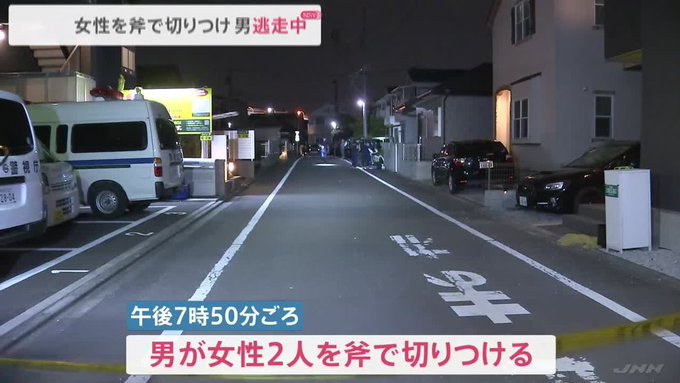






、初写真集が予約好調!発売前重版で11万部スタート ドキドキの泡風呂カット公開-683x1024.jpg)

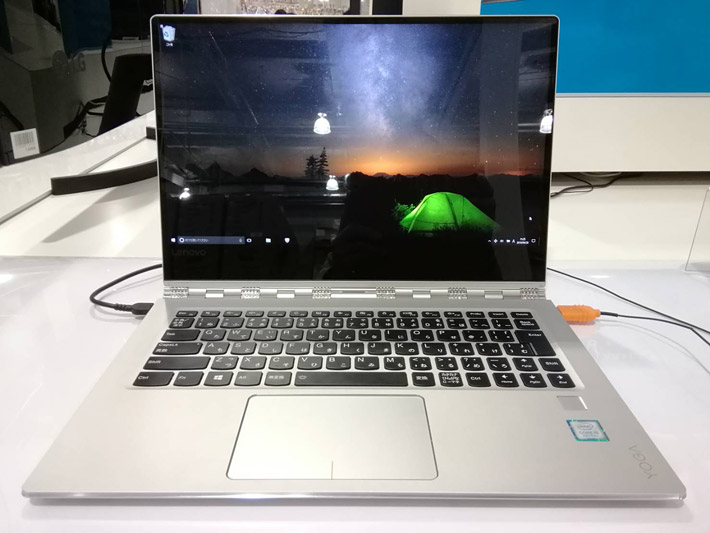







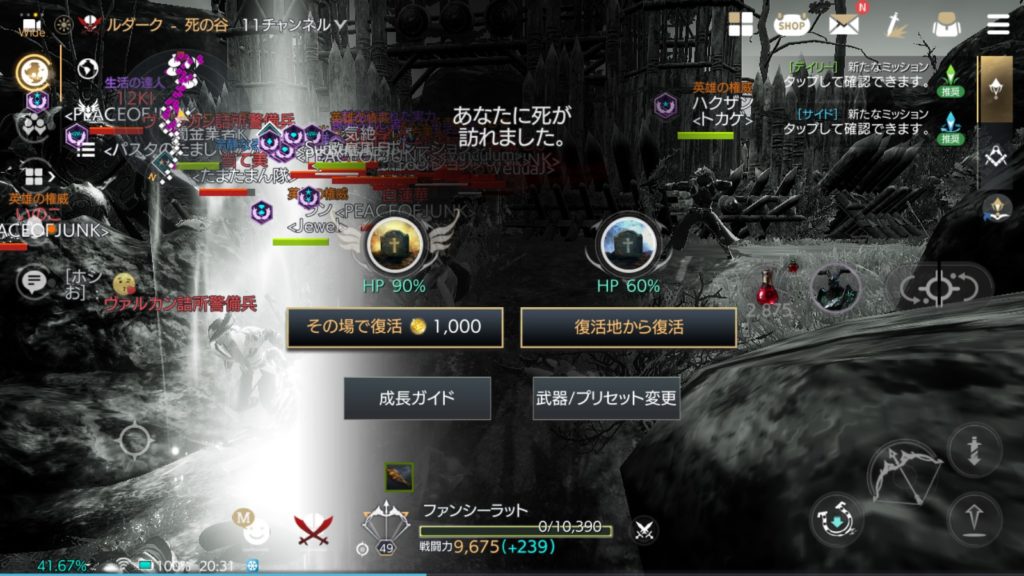





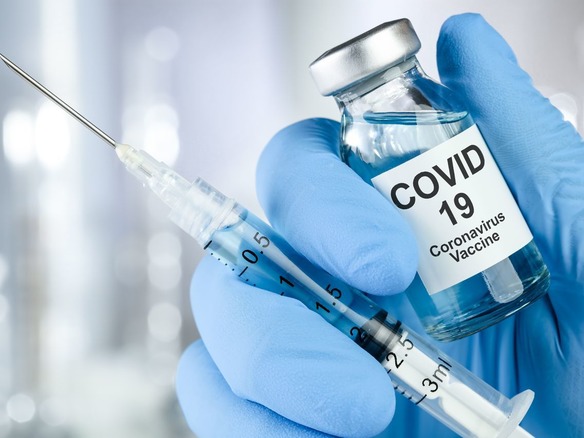






















































の年俸が4億7500万円から2億円以上の大幅減? 楽天を追いつめる資金難という大ピンチ「親会社が2000億円以上の赤字、観客もワースト…」.jpg)




とみられる男の身柄確保-818x1024.jpg)