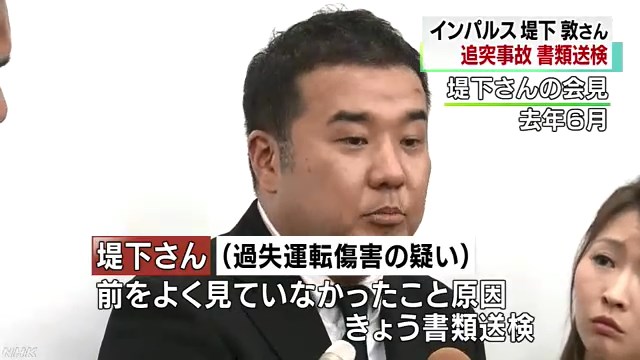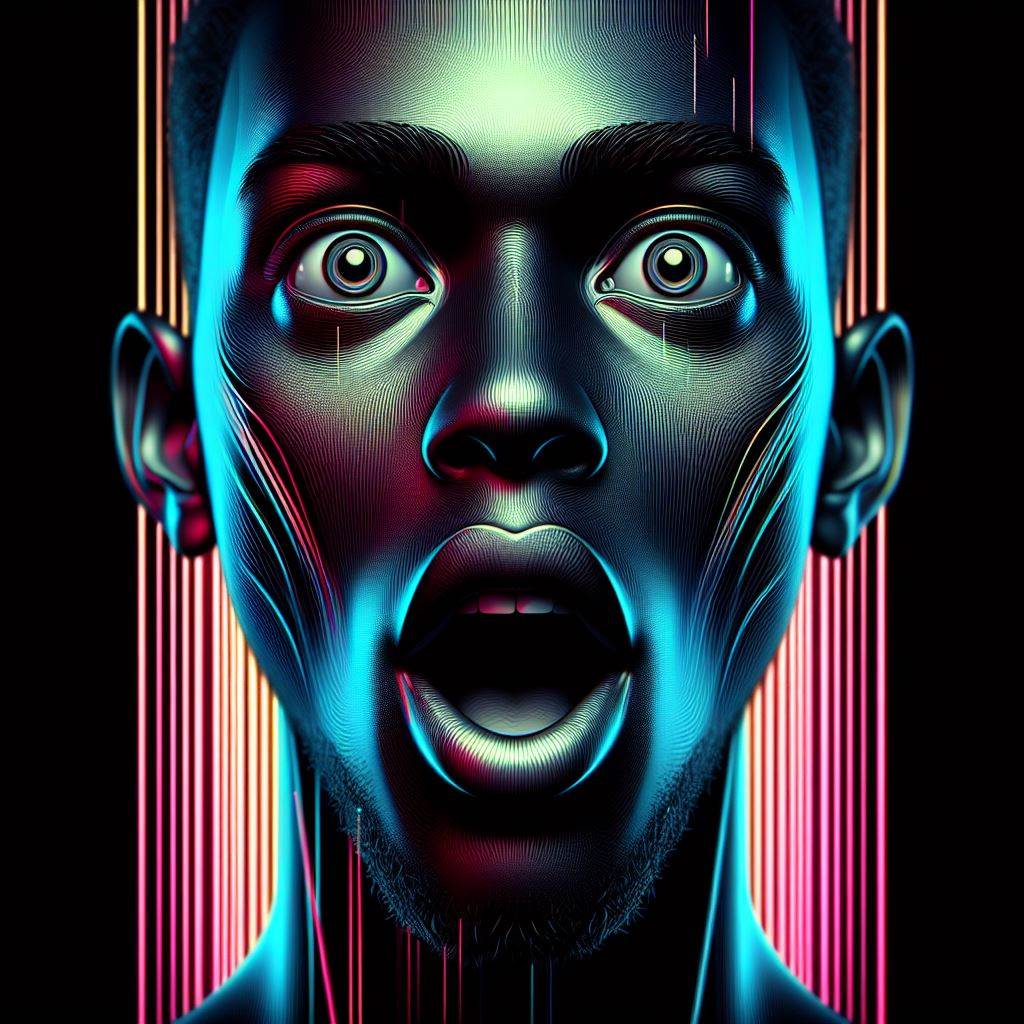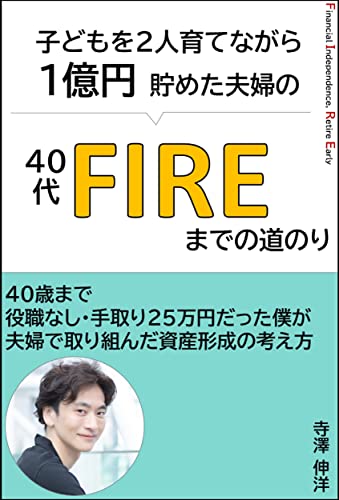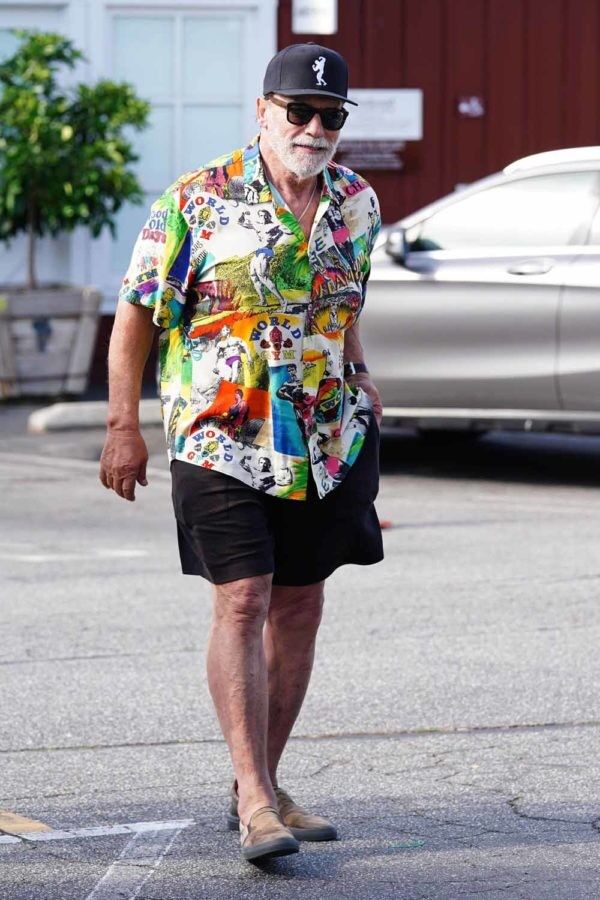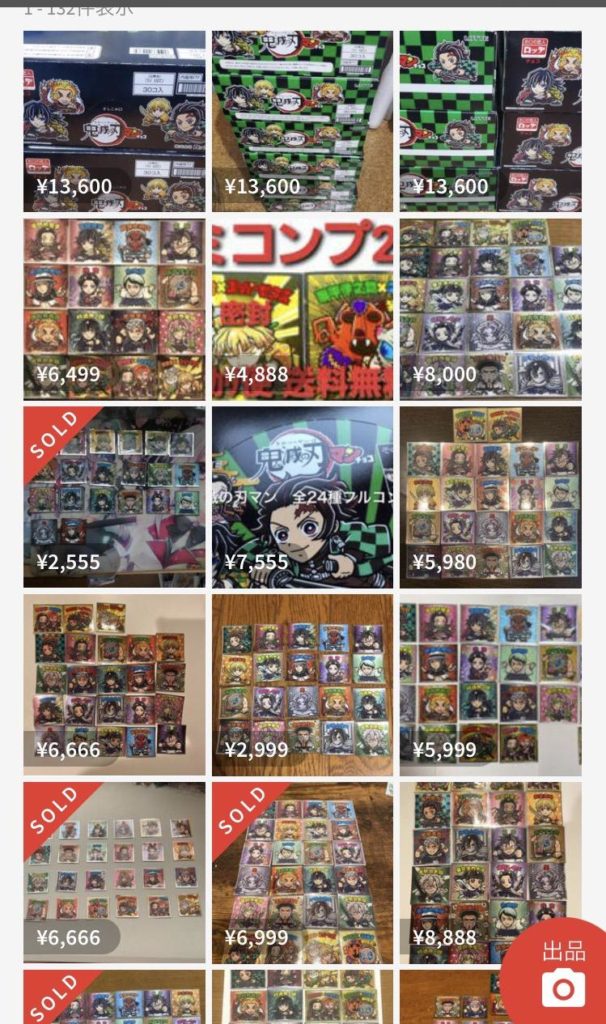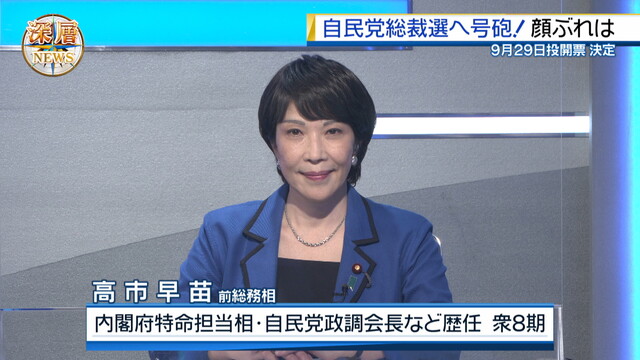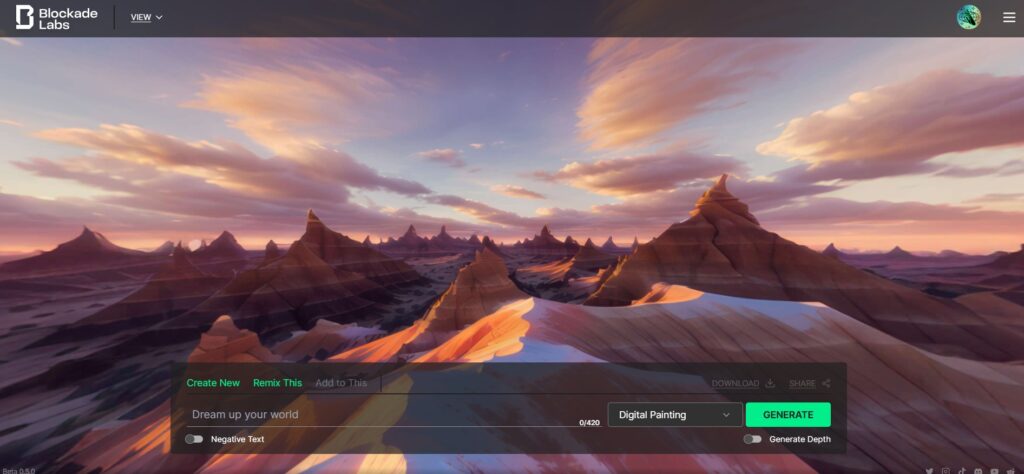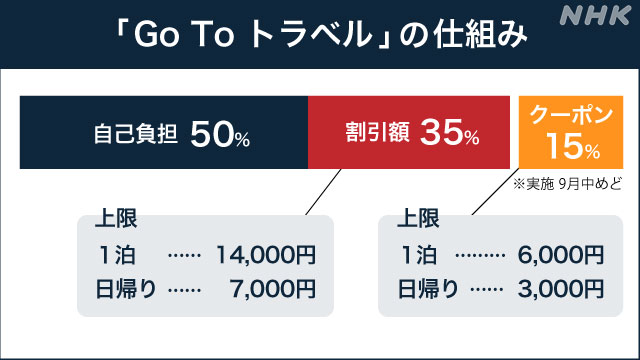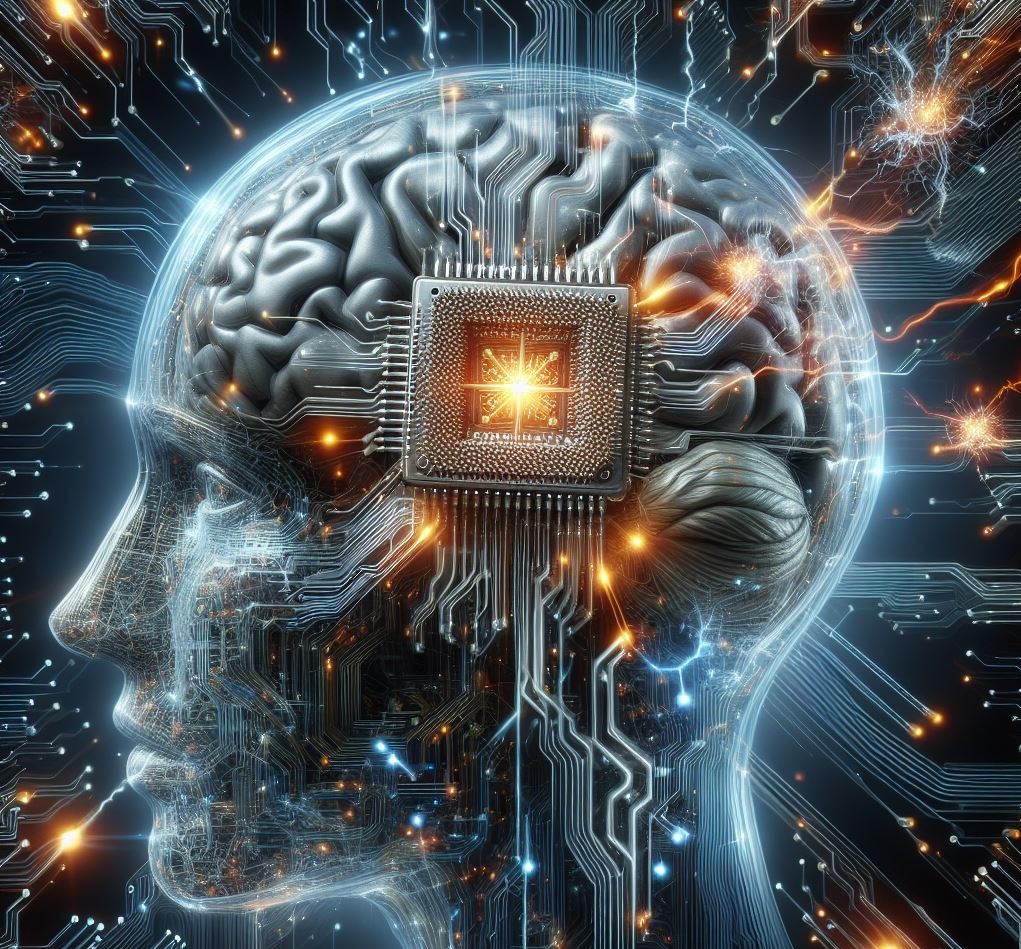本屋が非効率でコスパが悪いことから、なぜ成田悠輔は本屋を良いと考えるのか。彼の独特な視点から、本屋の魅力を探ってみたい。
成田悠輔は、自身が胃もたれ系の好みを持つ人物であり、非効率なものに魅力を感じる傾向がある。彼は本屋において、その非効率さが魅力となる要因であると考えている。本屋は、他の手段に比べて情報の収集や本の選択が非効率であり、コストパフォーマンスも良くないかもしれない。しかし、それが本屋ならではの魅力なのだ。
彼は自身が淡泊な性格であることを自覚しており、自分の文章があまり読む気を引かないと語っている。そのため、彼の文章が非効率な表現を用いることが多く、一般的にはあまり見られないスタイルとなっている。このような視点から見れば、成田悠輔の言葉は一部の人には馴染みにくいかもしれないが、その独自性こそが彼の魅力であり、彼を本屋の良さを語る者として際立たせているのだ。
本屋の魅力は、フォントの出会いや本の選択の非効率さが、人々の生き方に影響を与え、人生を変えるきっかけとなることにある。成田悠輔は、自身が人生を変えた本を紹介することで、本屋の重要性を訴えている。彼が紹介する本は、自己啓発のような明確な目的を持つものではないかもしれない。しかし、そのニッチな本が人々の心に響き、新たな視点や価値観を提供することがあるのだ。
近年、電子書籍の普及により本屋への来店は減少している。成田悠輔自身も、電子書籍やオンラインショッピングを利用することが多い。しかし、彼も本屋の存在意義を否定するわけではない。成田悠輔は、本屋と電子書籍を両方利用することで、気分や状況に合わせて選択肢を使い分けている。彼は、一つの媒体に飽きることなく、本屋と電子書籍の両方を通じて読書の楽しみを追求することを好む。
彼は、本屋が非効率であることや飽き性の性格を持つことを理由に、本屋への愛着やこだわりを持つことはない。むしろ、本屋をあくまで一つのモードとして位置付けており、便利さや効率性に執着しない自由なスタンスを取っている。彼は法律やコストパフォーマンスにこだわるタイプではなく、さまざまな要素やパターンを組み合わせて自分自身のスタイルを形成したいと考えているのだ。
成田悠輔の視点は、一般的な主義主張とは異なるかもしれない。彼は最短ルートや効率主義よりも、自分自身のペースで進むことを重視している。彼の意外な一面に驚かれるかもしれないが、彼自身も効率主義者ではなく、個別のパターンを独自に組み合わせることを好むのだ。
成田悠輔の視点から見れば、本屋が非効率でコスパが悪いことこそが本屋の魅力であり、その非効率さが独自の体験や思索の場を提供しているのだ。彼は、本屋が持つニッチな本や抽象的な哲学的要素に価値を見出し、そこから新たな気づきや洞察を得ることを求めている。彼の独特な視点は、本屋の魅力を再評価し、個々の読書体験に多様性と柔軟性をもたらすのである。
成田悠輔のような視点は一般的ではないかもしれないが、彼の言葉は新たな視座や議論のきっかけとなるかもしれない。本屋が非効率でコスパが悪いとされる中でなお魅力を持つ理由は、成田悠輔が本屋を単なる情報の提供場所ではなく、個々の人生に影響を与える場として捉えているからである。彼は本屋によって出会うフォントや本の選択の非効率さが、人々の生き方や思考の転機となる可能性を秘めていると信じているのだ。
また、彼が紹介する本は、自己啓発や明確な目的を追求するものではないかもしれない。それでもなお、そのニッチな本が読者の心に響き、新たな気づきや洞察をもたらすことがあるのだ。成田悠輔自身の人生や経験を抽象化し、謎の哲学に変換したような本が彼の関心を引き付けるのである。
成田悠輔が本屋に対して特別な愛着やこだわりを持たないのは、彼が飽き性であり、異なるモードや経験を求める性格だからだ。本屋は彼にとって、あくまで一つの選択肢の一環であり、便利さや効率性への追求は重要ではない。彼は多様な要素やパターンを組み合わせて自身の読書スタイルを編み出すことを好むのだ。
最後に、成田悠輔の視点は一般的な効率主義とは異なるが、その異質性こそが彼の魅力の一つである。彼は自分自身のペースで本屋や読書を楽しみ、独自の視点や価値観を追求しているのだ。そのような個別のパターンを独自に組み合わせることで、彼は自身の読書体験を豊かなものにしているのである。
成田悠輔の視点から見れば、本屋の非効率性やコスパの悪さこそが本屋の魅力であり、そこから得られる非凡な体験や思索の場が彼を惹きつけるのだ。彼の言葉は、本屋の再評価や多様性を提案し、読書体験に新たな展望をもたせるものとなるでしょう。成田悠輔のような視点は、私たちにとって新たな視座や議論のきっかけをもたらします。
本屋が非効率でコスパが悪いと一概に否定されることもありますが、成田悠輔の視点を通じて本屋の魅力を再評価することができます。本屋は単なる商品の提供場所ではなく、個々の人生に深い影響を与える場として存在しているのです。
成田悠輔が述べるように、本屋の非効率さやコストパフォーマンスの悪さが、本を手にする喜びや思考の転機をもたらすのかもしれません。本屋に足を運ぶことで、予期せぬ出会いや意外な選択によって、私たちは新たな発見や成長を経験することができるのです。
本屋は個々の読書体験に多様性と柔軟性をもたらします。成田悠輔のように、電子書籍やオンラインショッピングを利用しながらも、本屋を訪れることで新たな刺激を受けることができるのです。本屋は、独自のセレクションや雰囲気を通じて、私たちに異なる読書体験を提供してくれる存在です。
成田悠輔が本屋に特別な愛着やこだわりを持たない理由も納得できます。本屋はあくまで一つの選択肢であり、便利さや効率性に囚われることなく、自由なスタイルで本を選びたいという彼の考え方は、個々の読書スタイルの多様性を尊重するものです。
成田悠輔の視点は一般的な効率主義とは異なりますが、それこそが彼の魅力の一つです。彼は自分自身のペースで本屋や読書を楽しみ、異なるパターンや視点を組み合わせることで独自の読書体験を創り出しているのです。








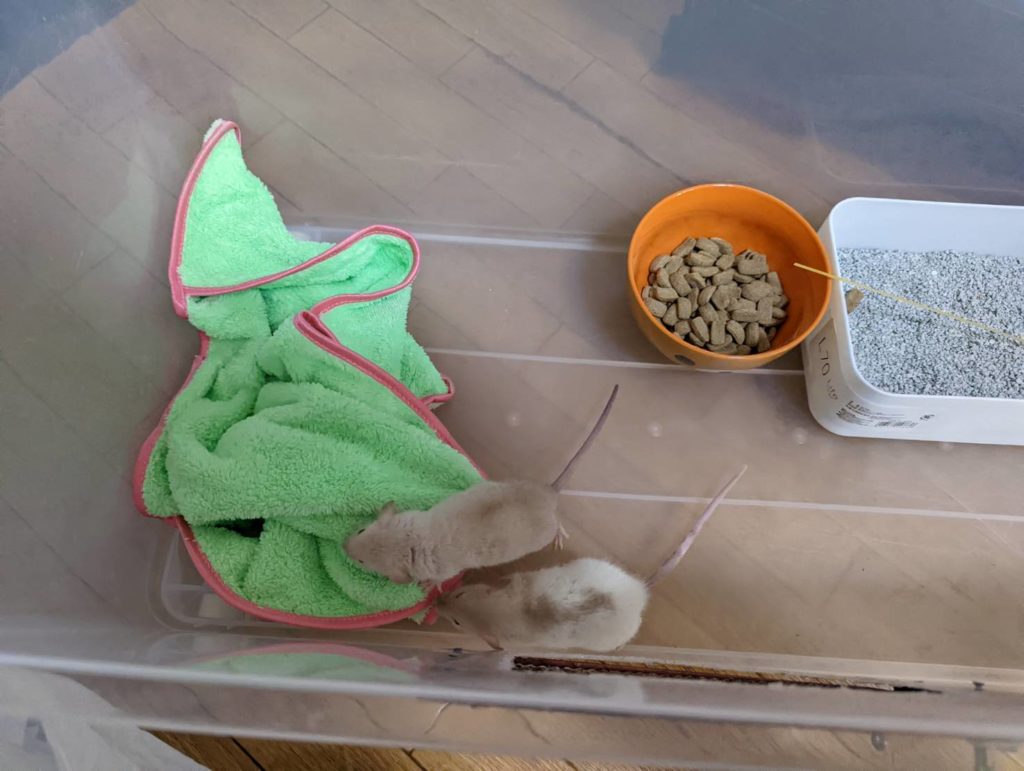
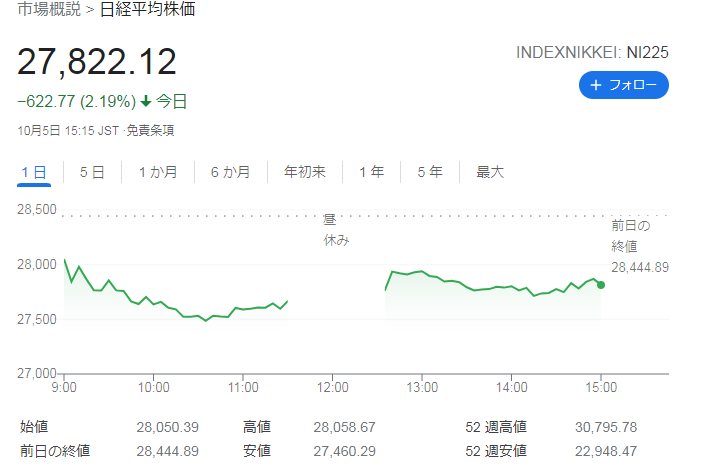












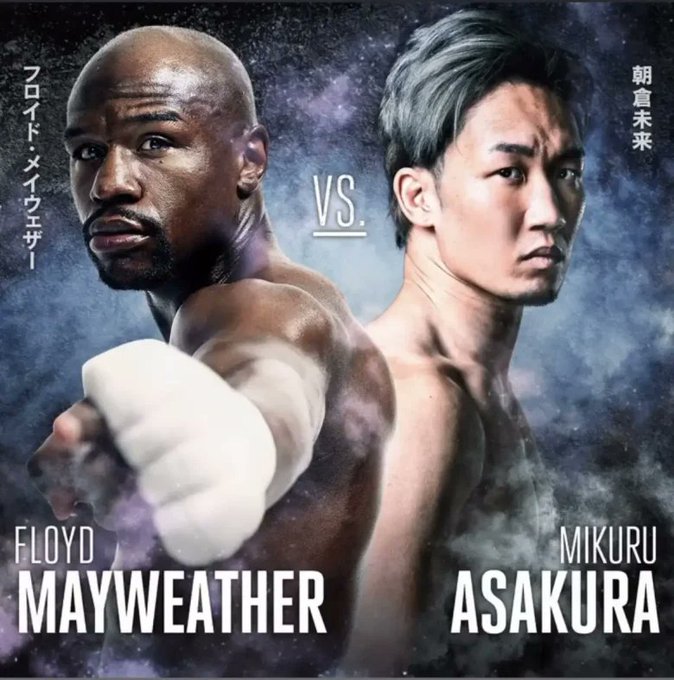























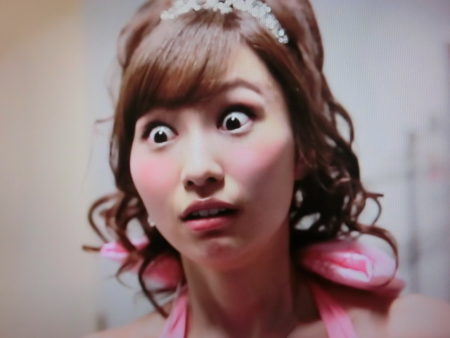



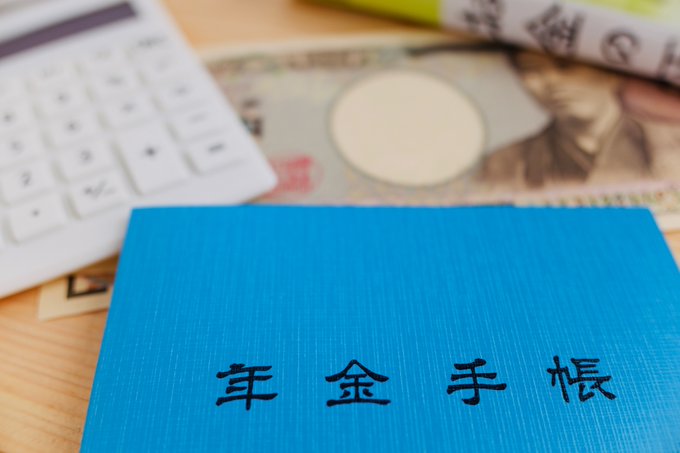


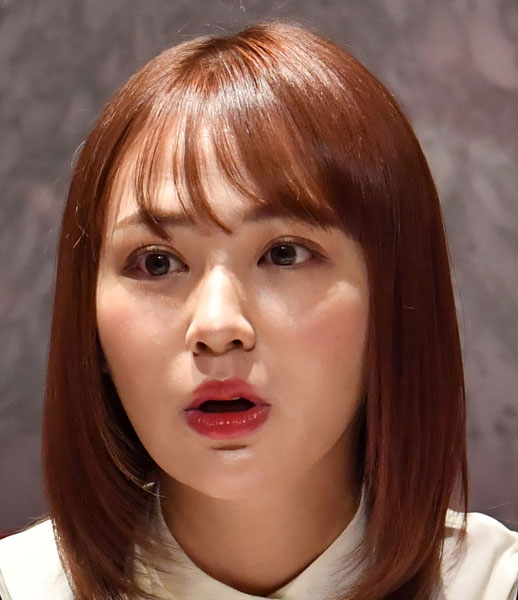


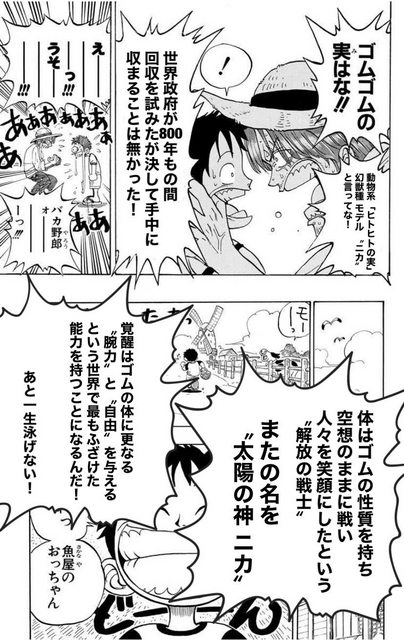


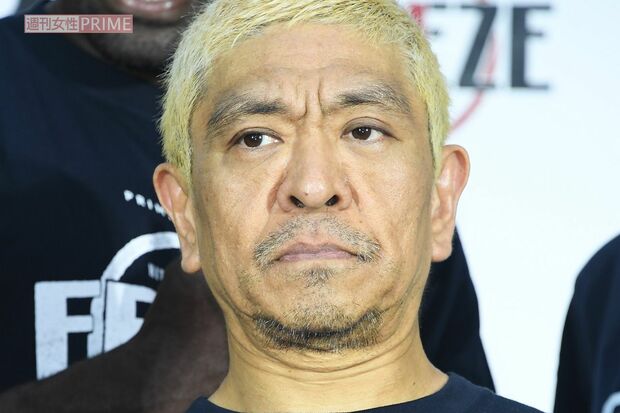


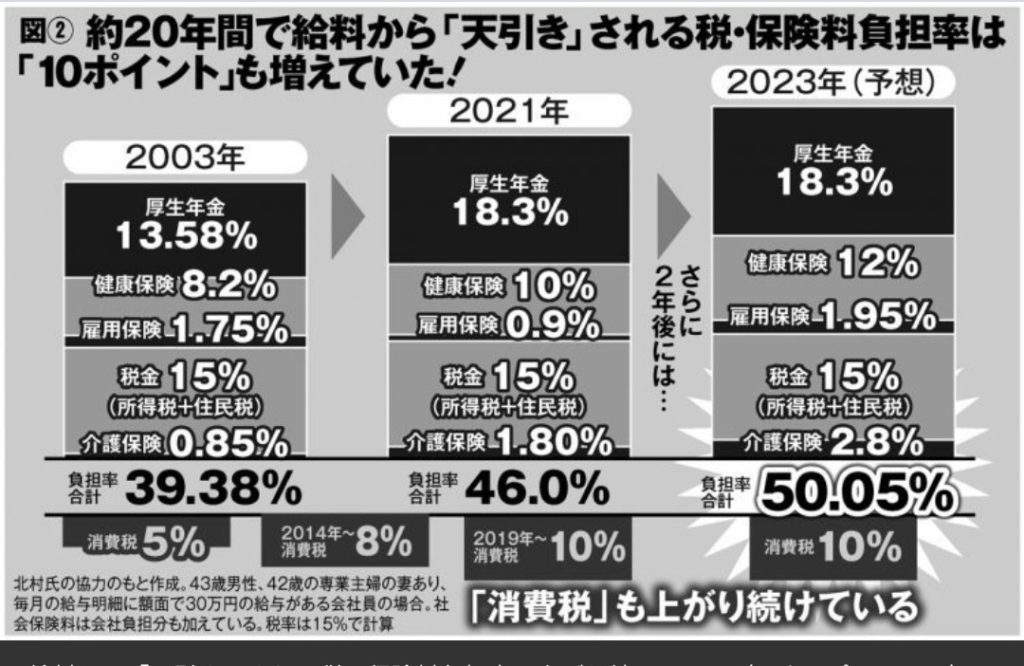

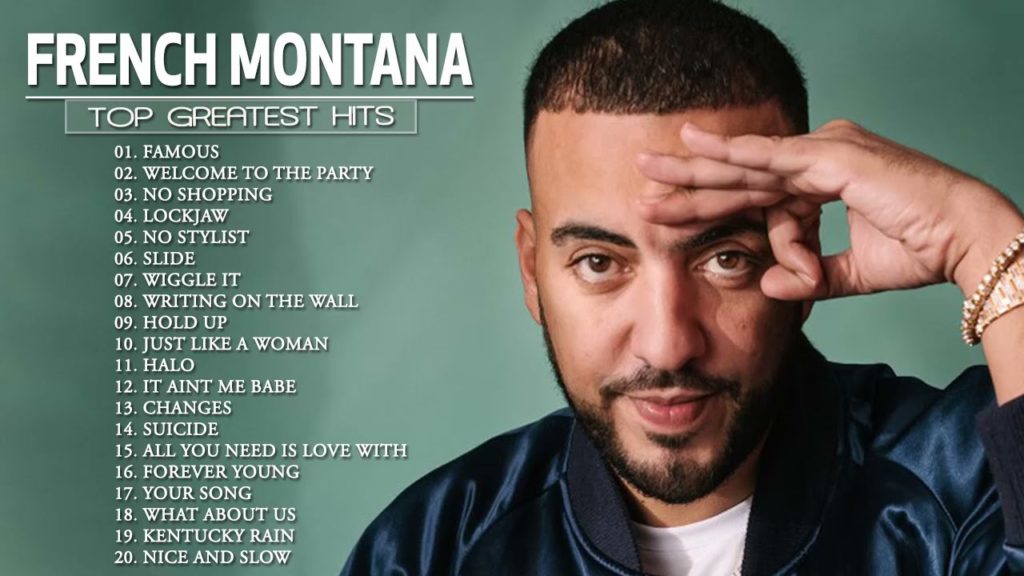

が美しい!大人になって7年ぶり「ヤンマガ」登場 AKB48がグラビアジャック。-768x1024.jpg)



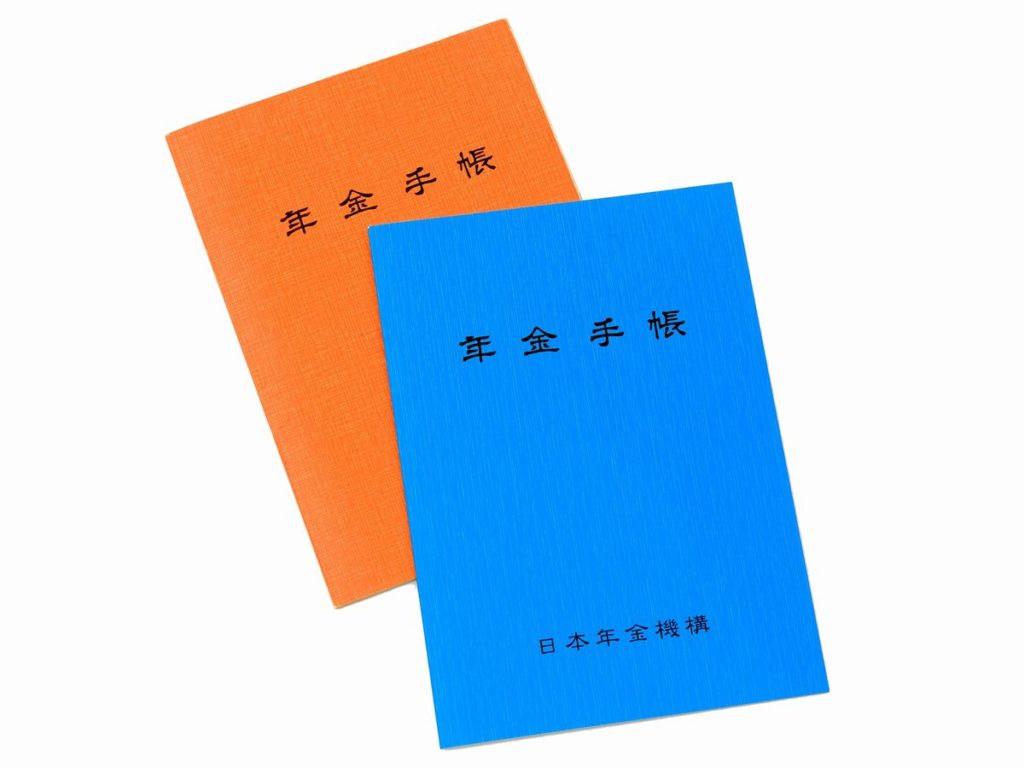

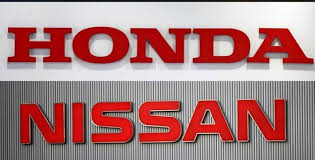







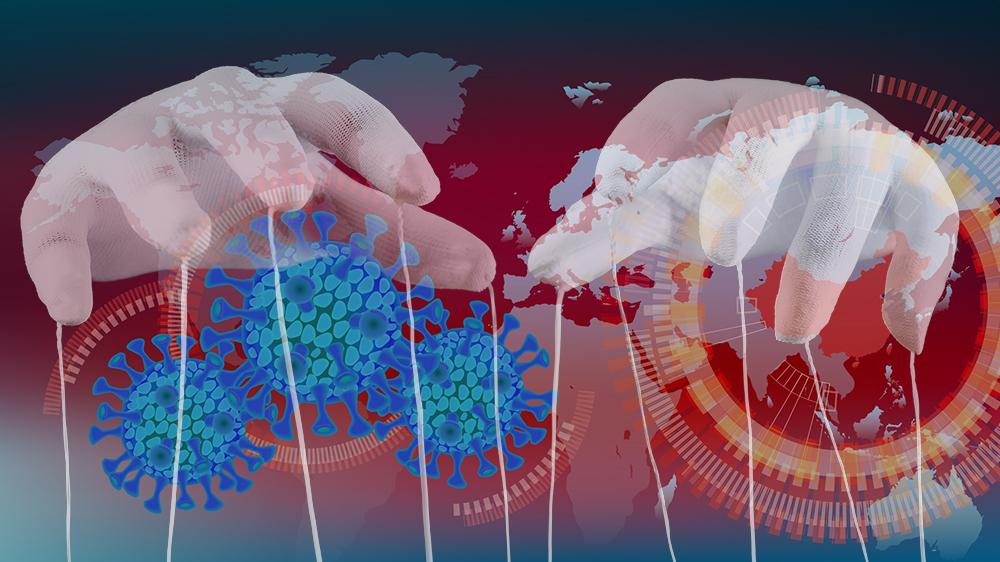

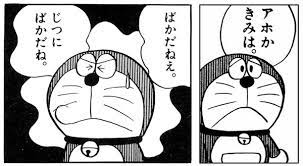









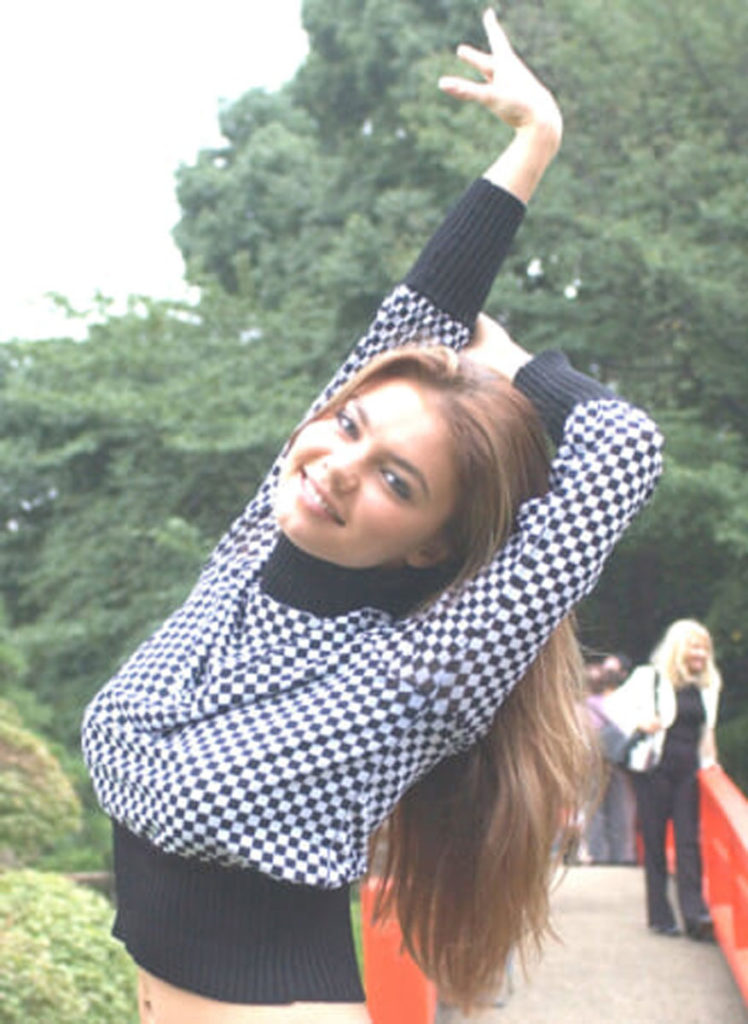







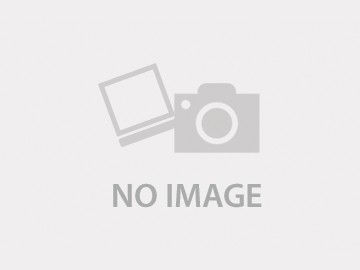
















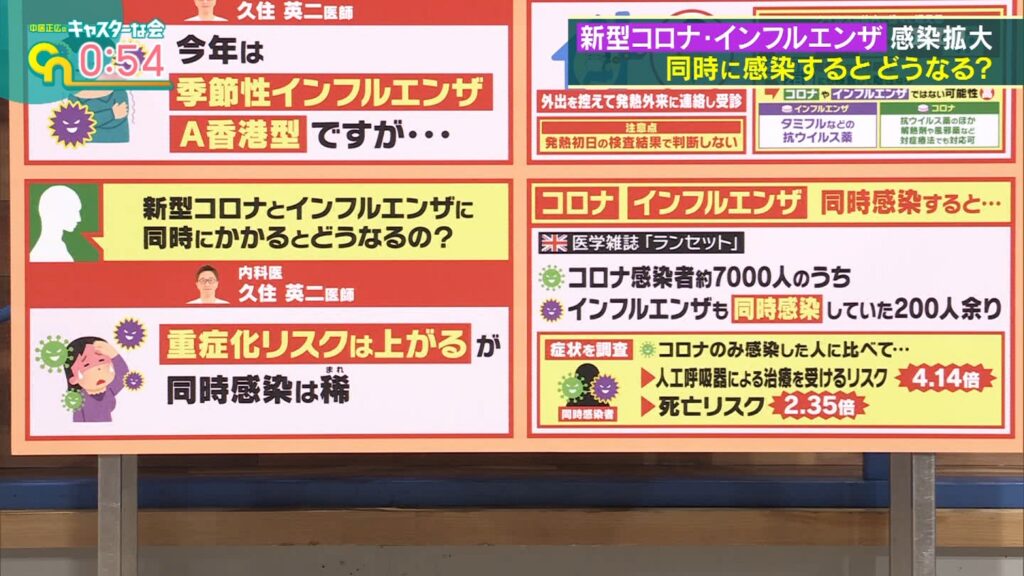












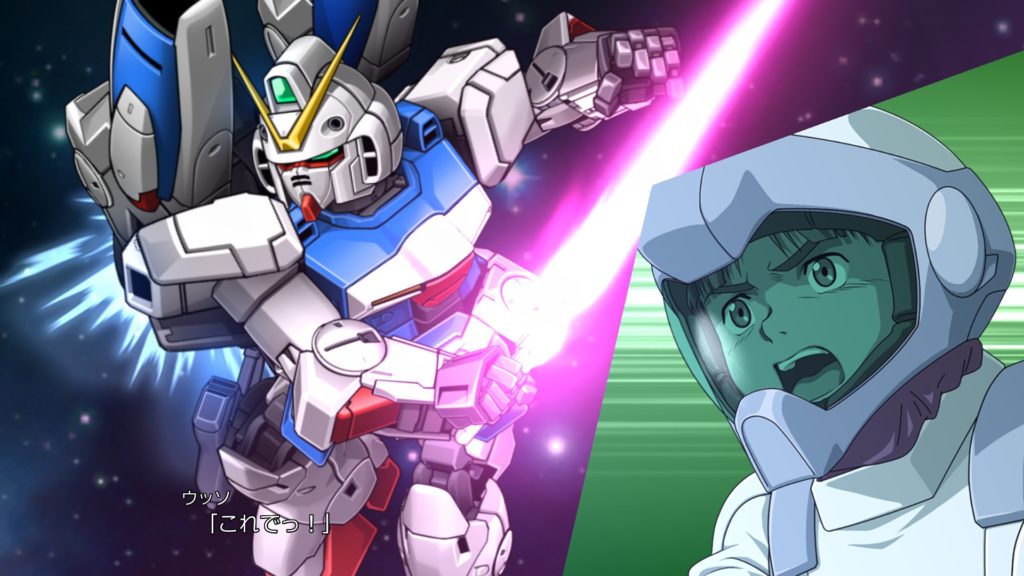











(わが国で未承認の難治性ニキビ治療薬)1-1024x768.jpg)

















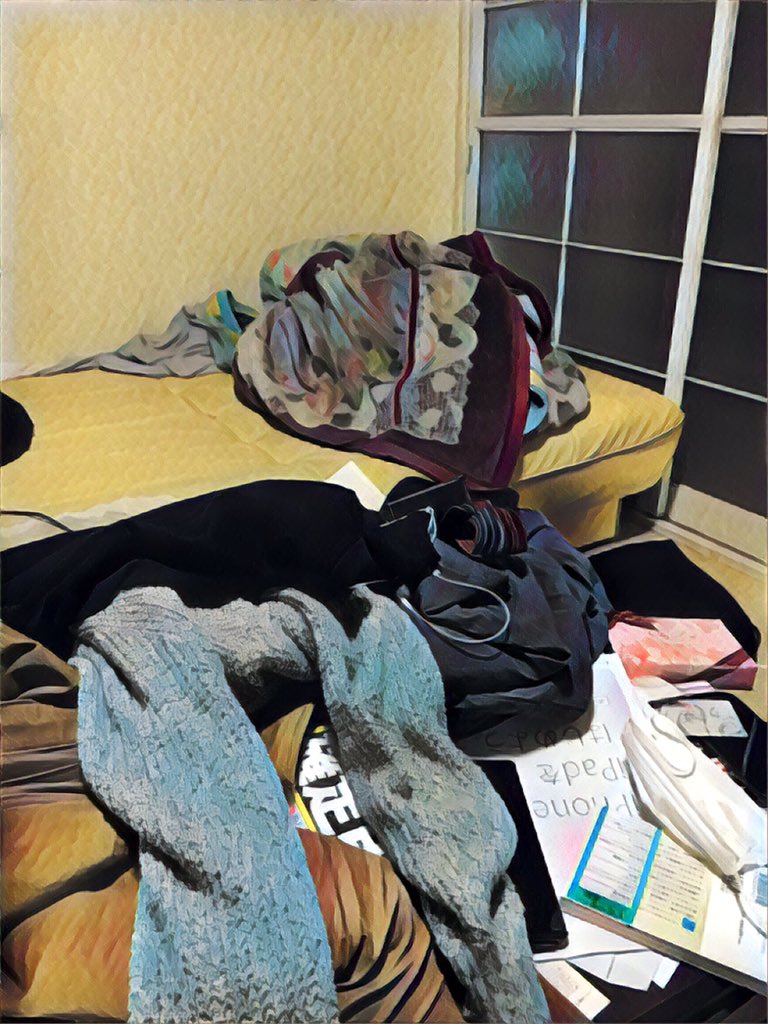






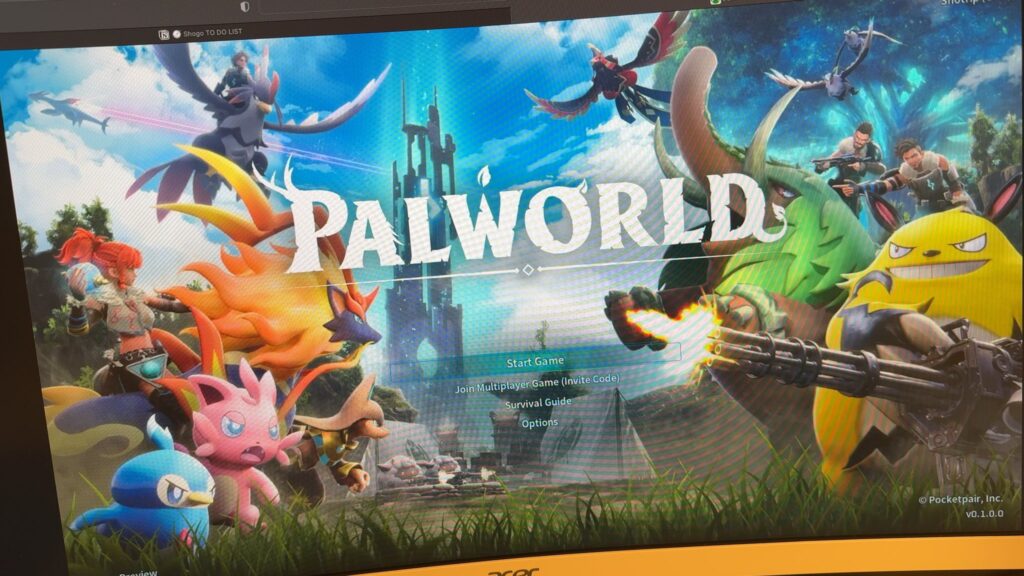









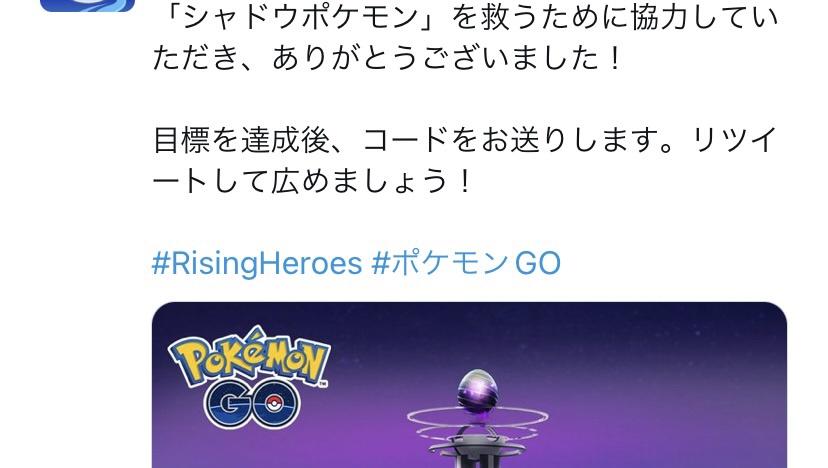





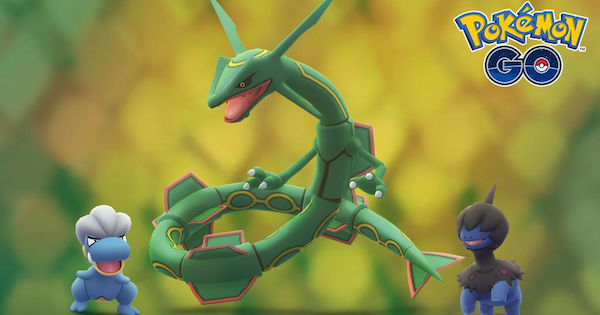

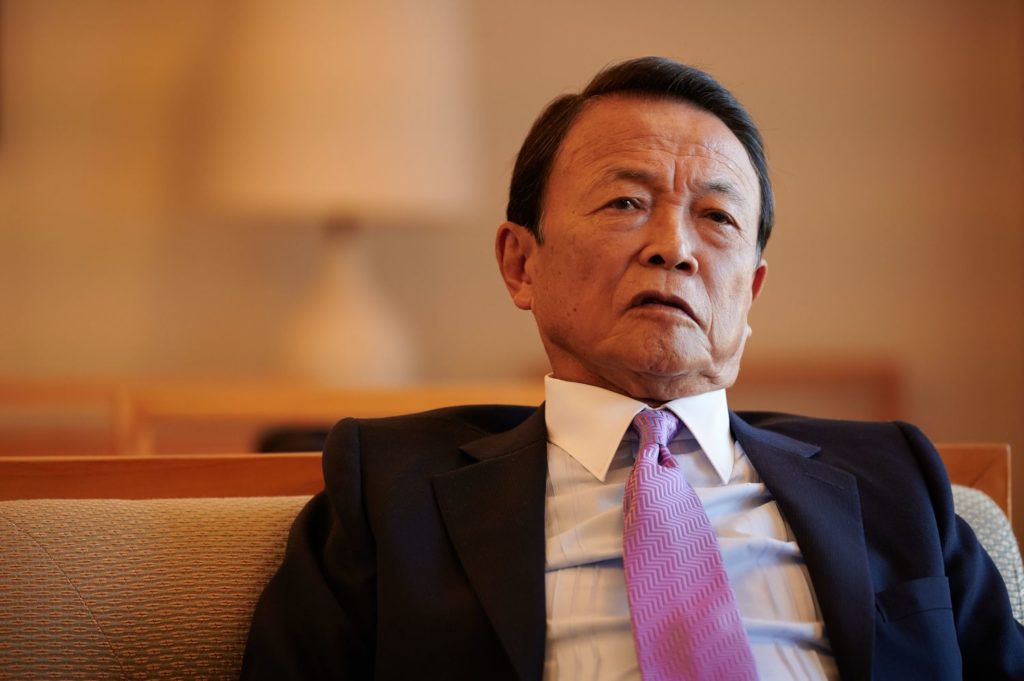


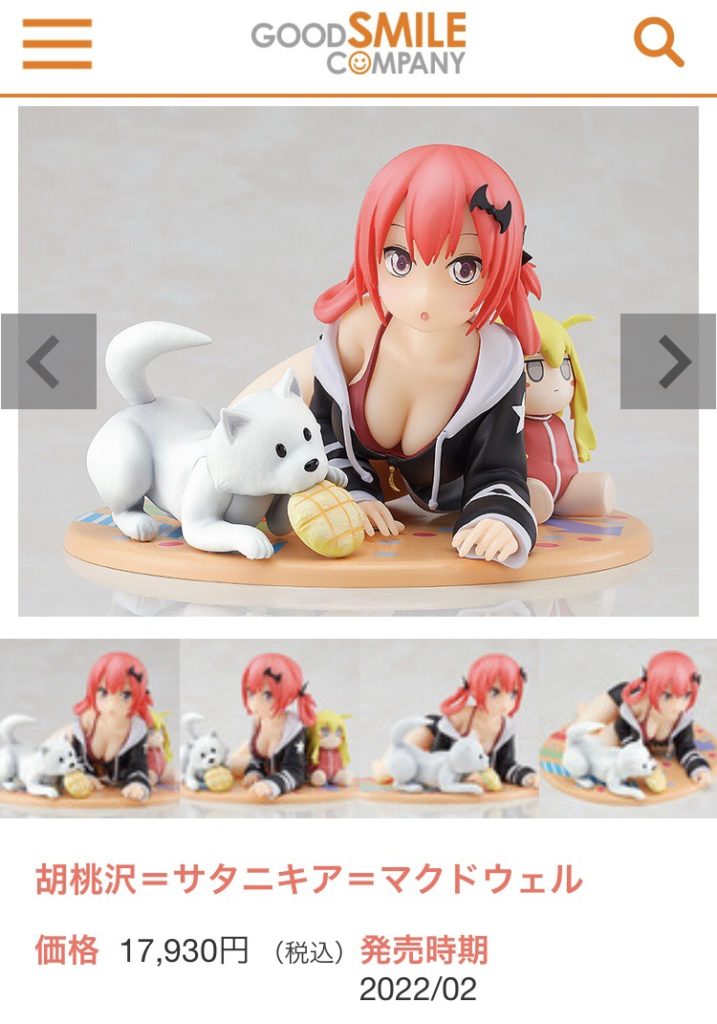

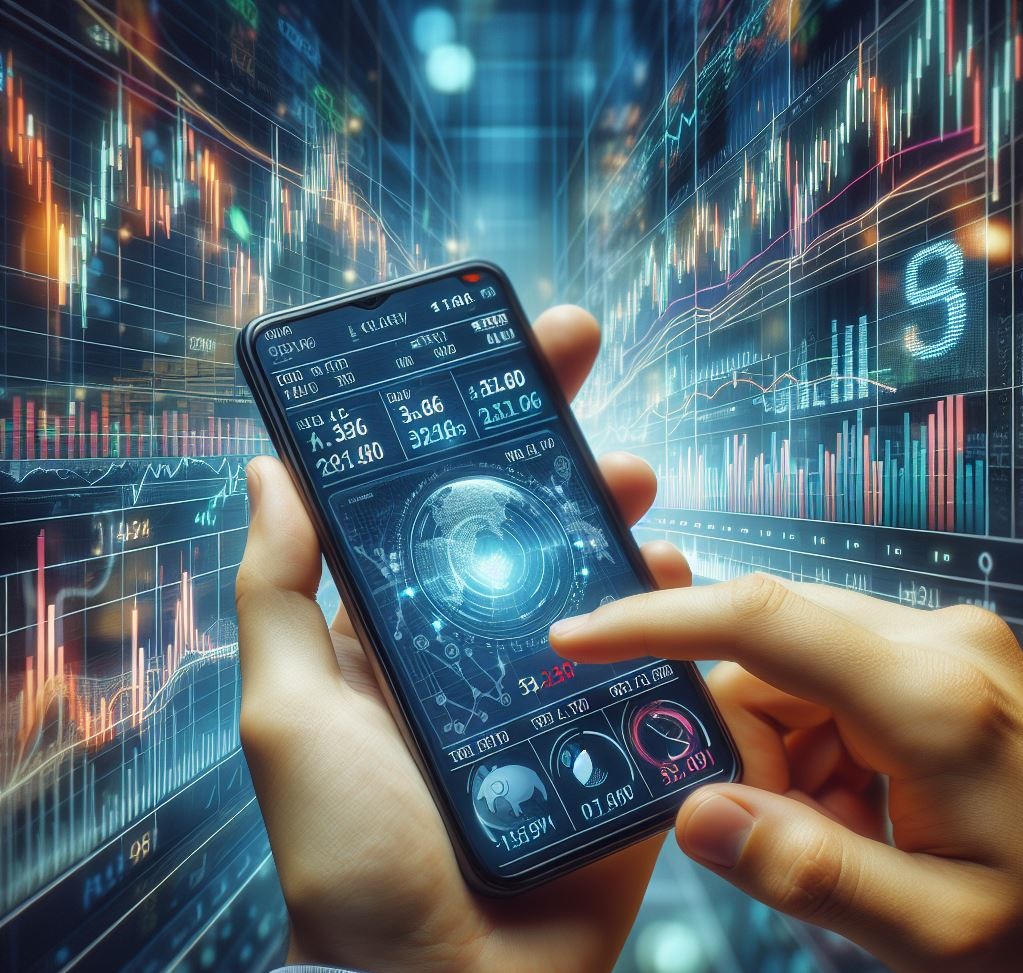
















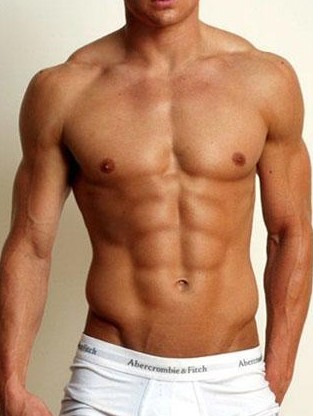

、フジ連続ドラマで初のヒロイン決定!Sexy-Zone菊池風磨と新婚生活-742x1024.jpg)