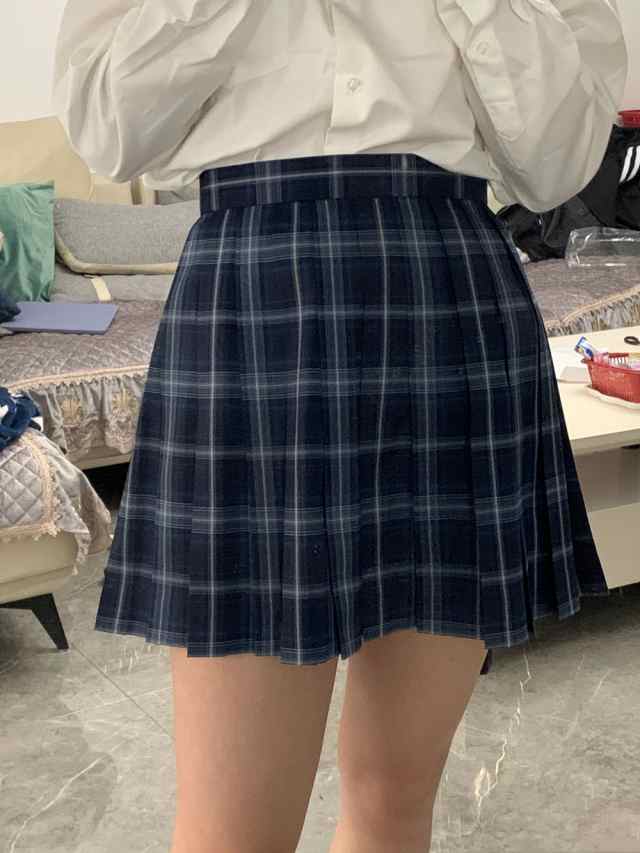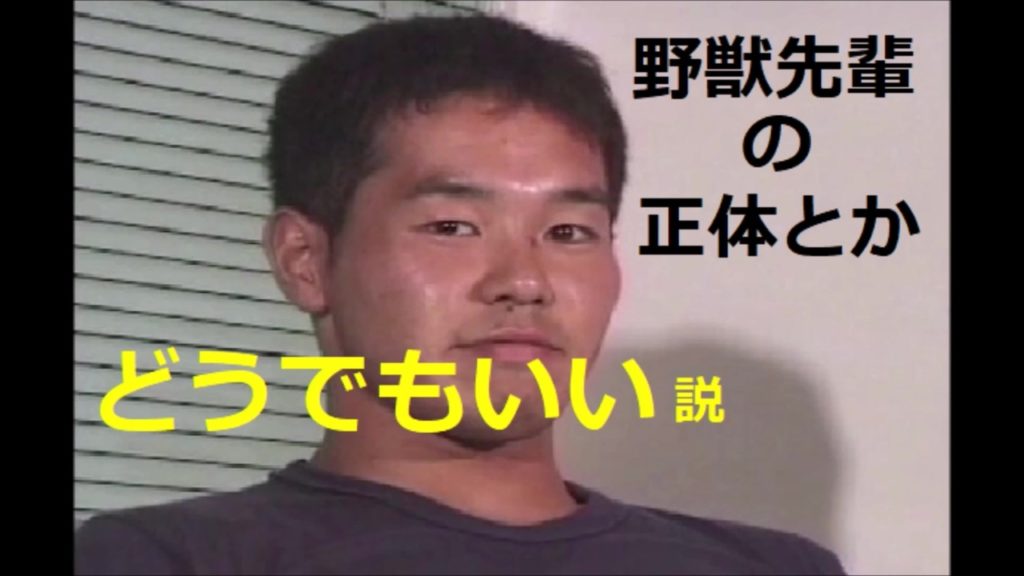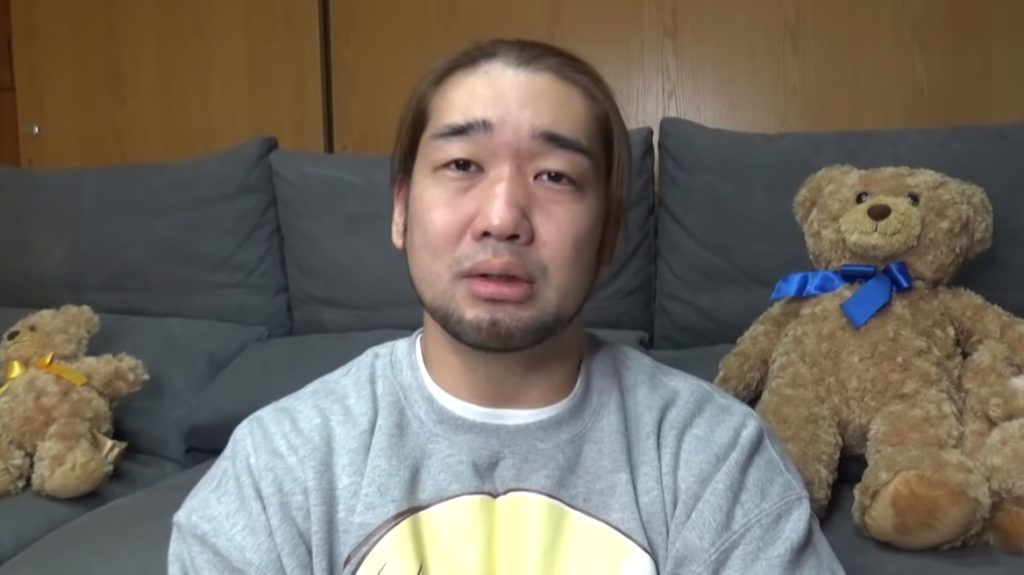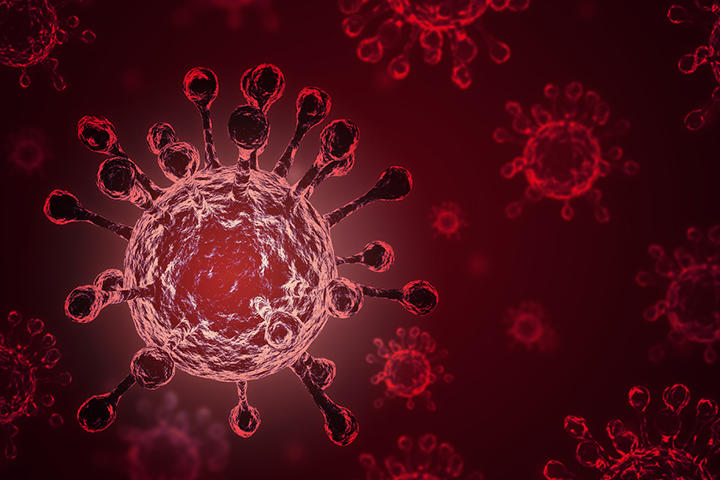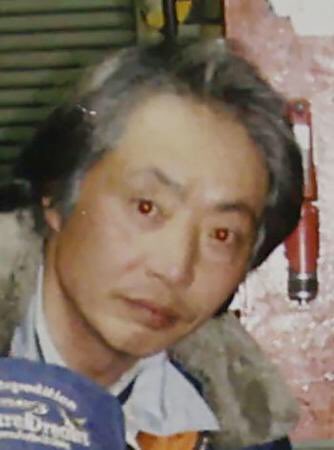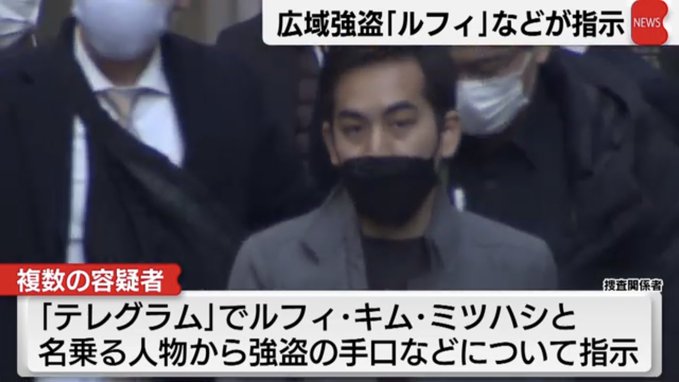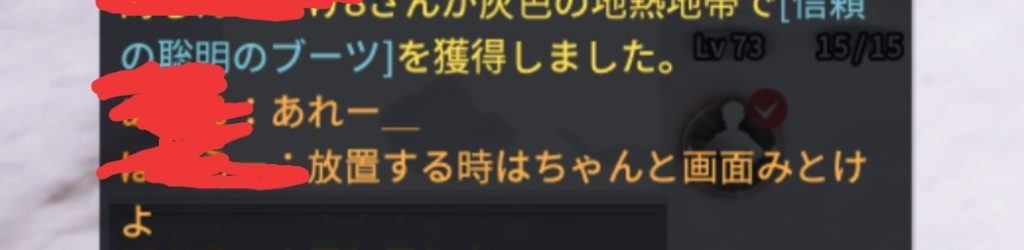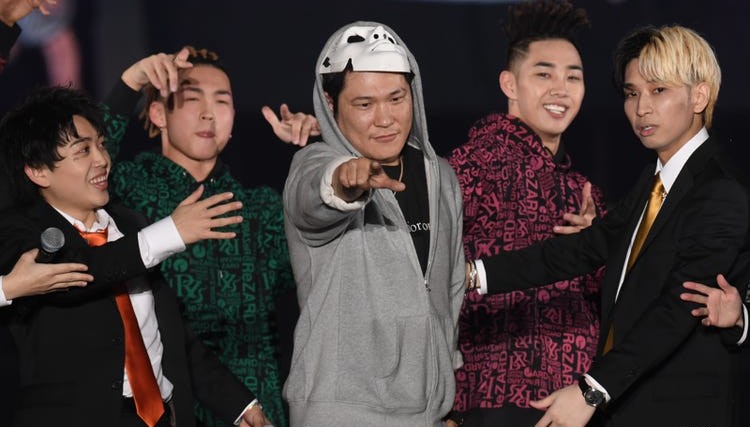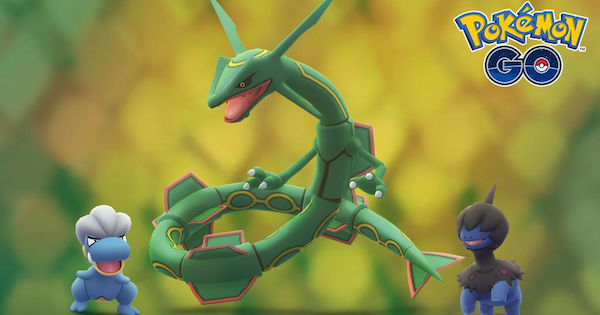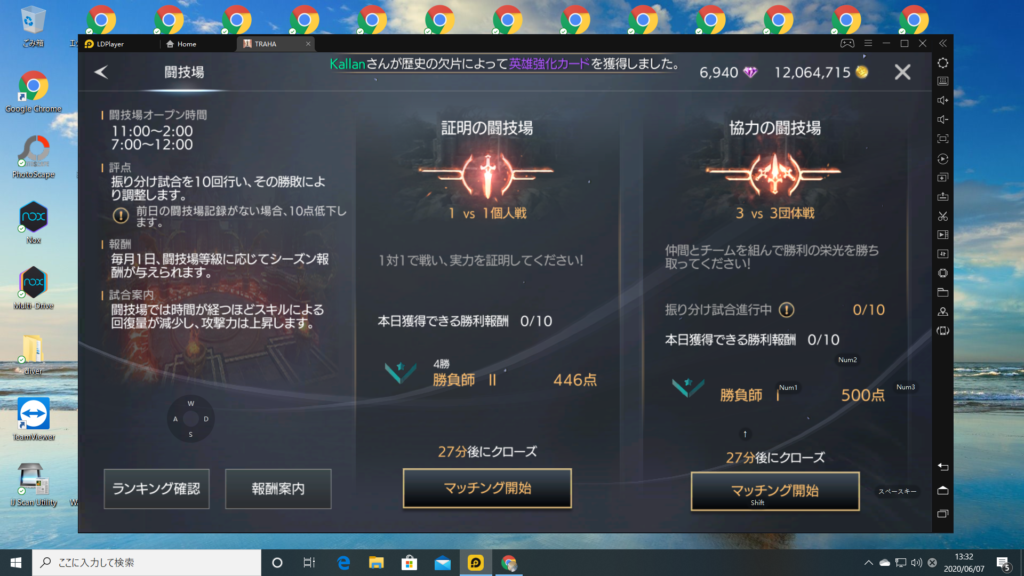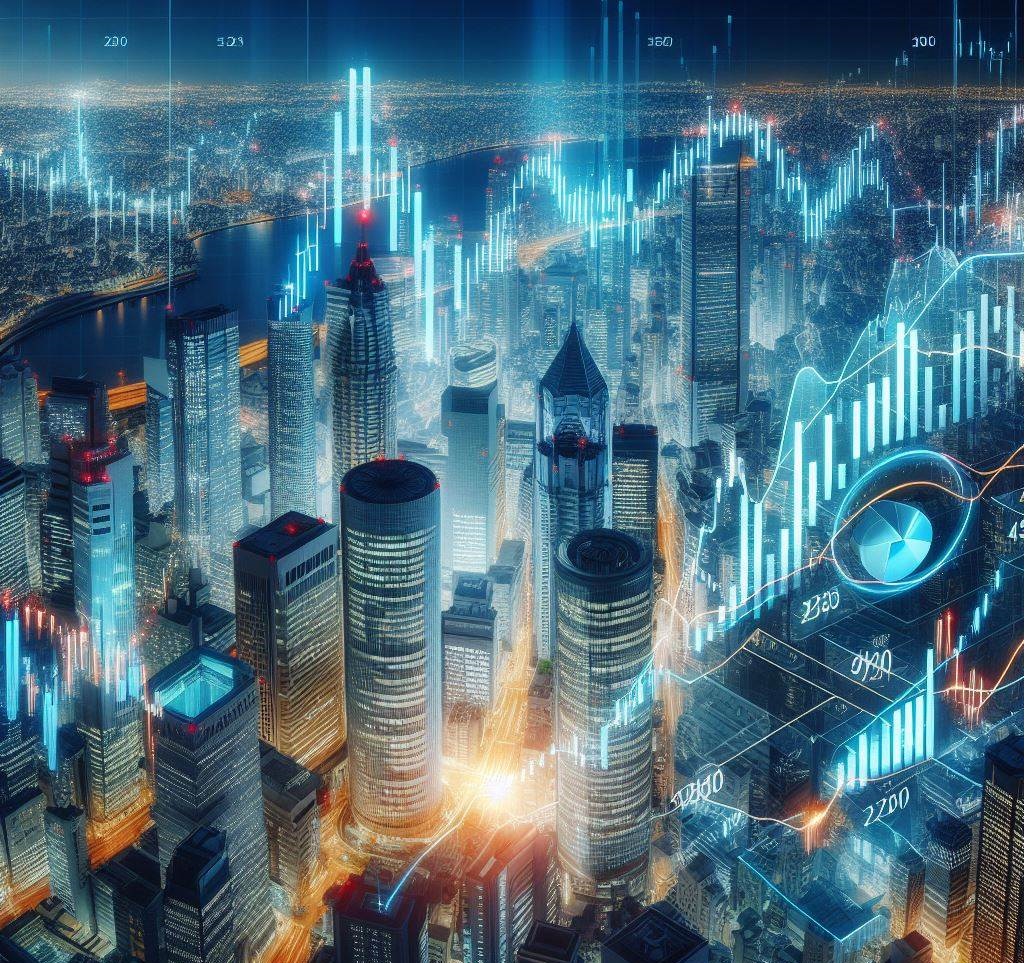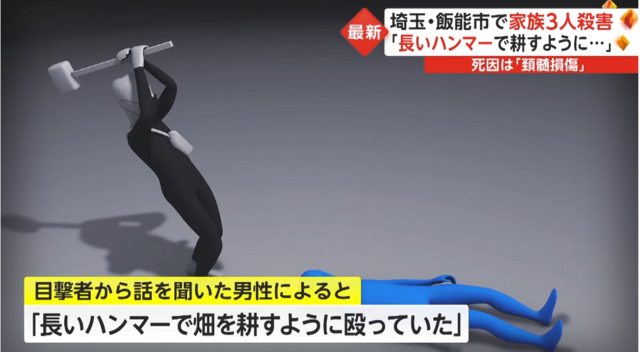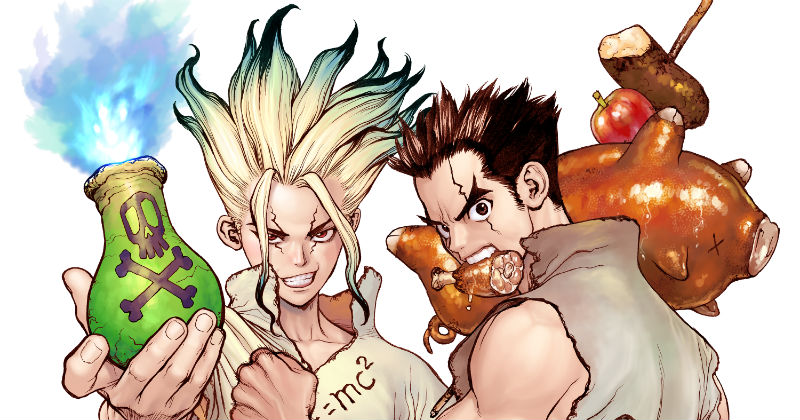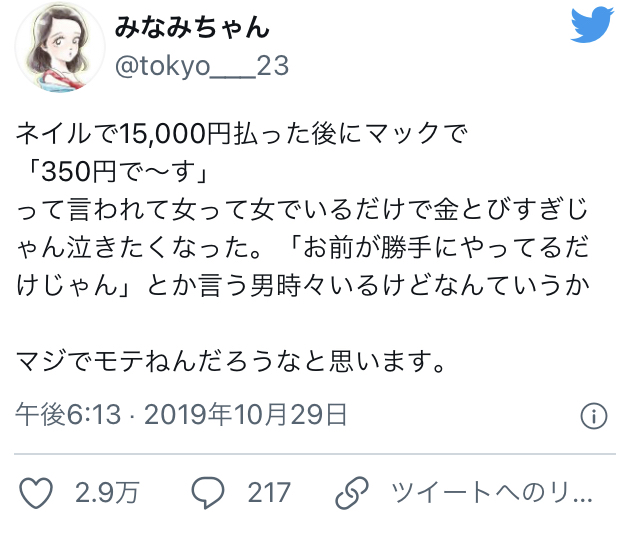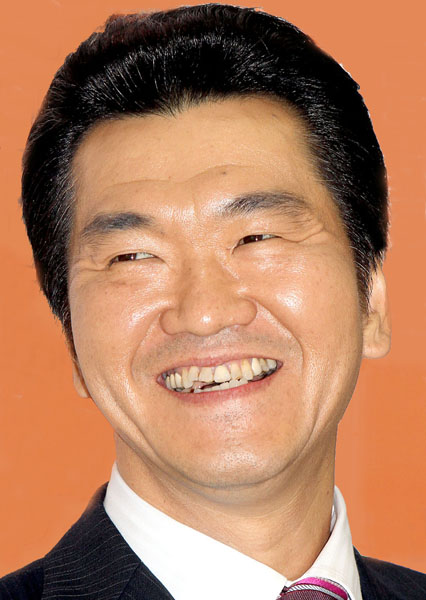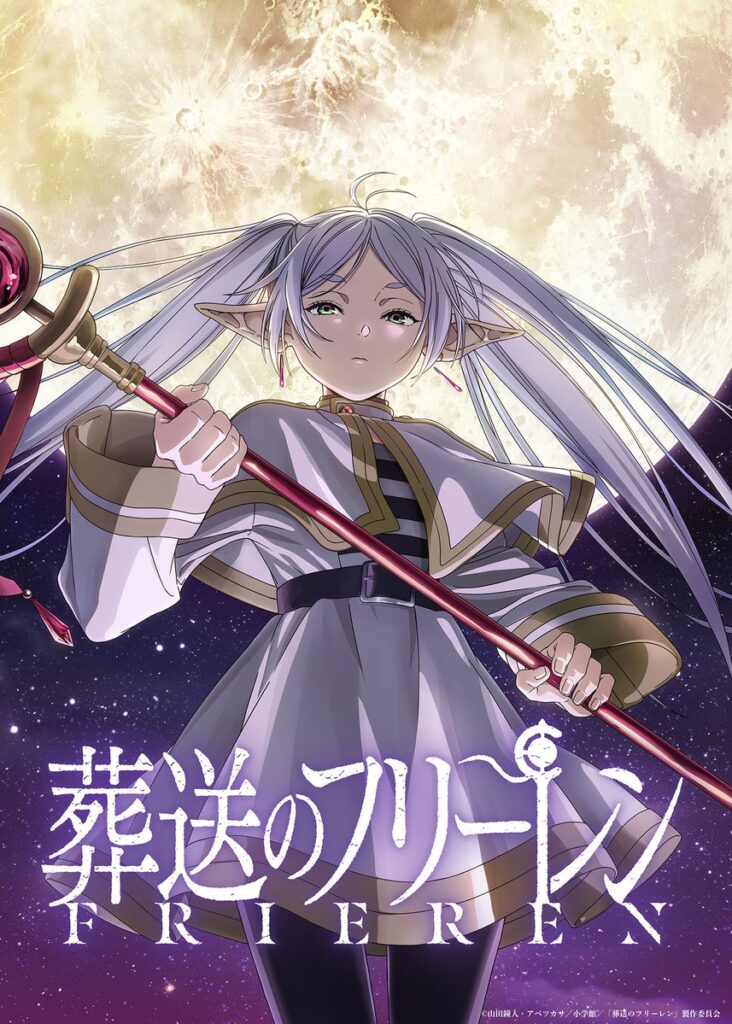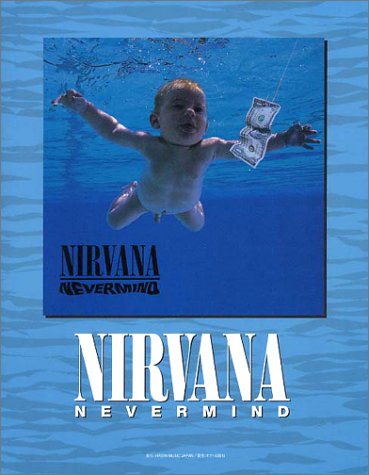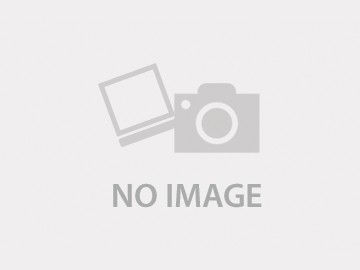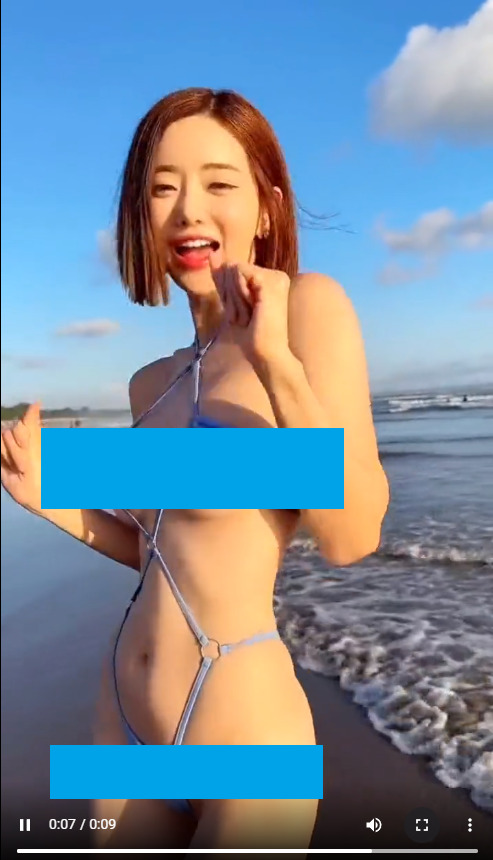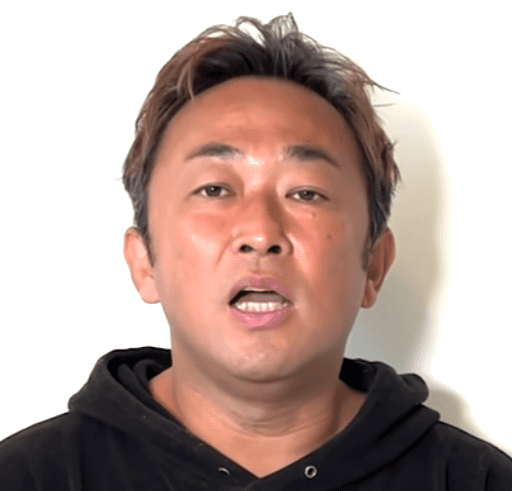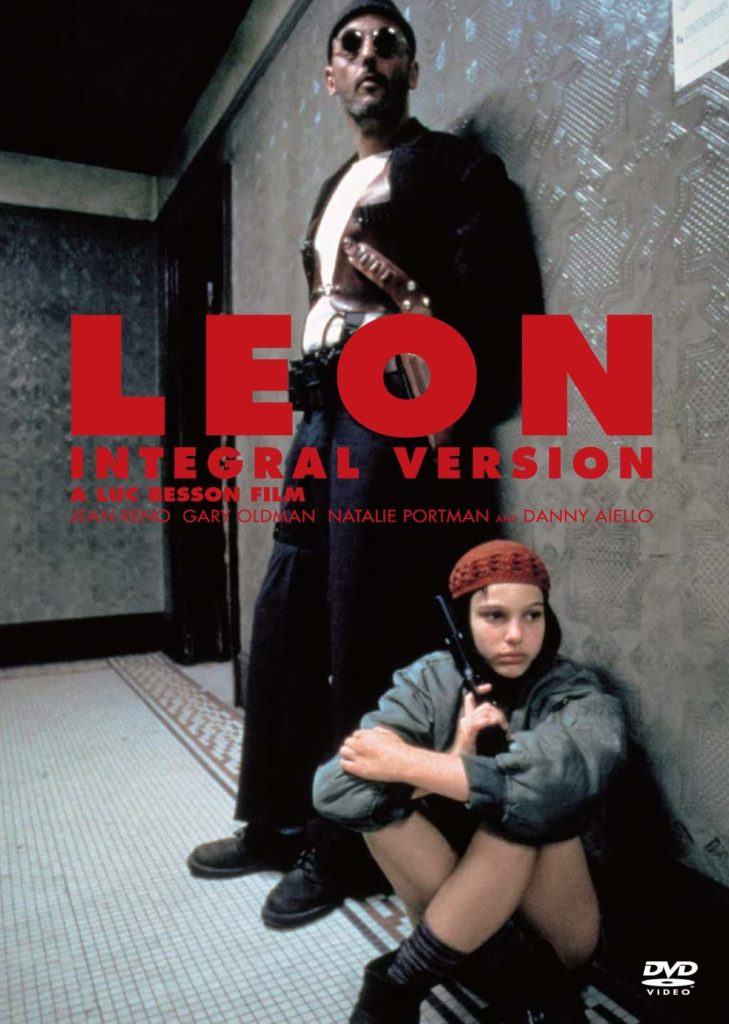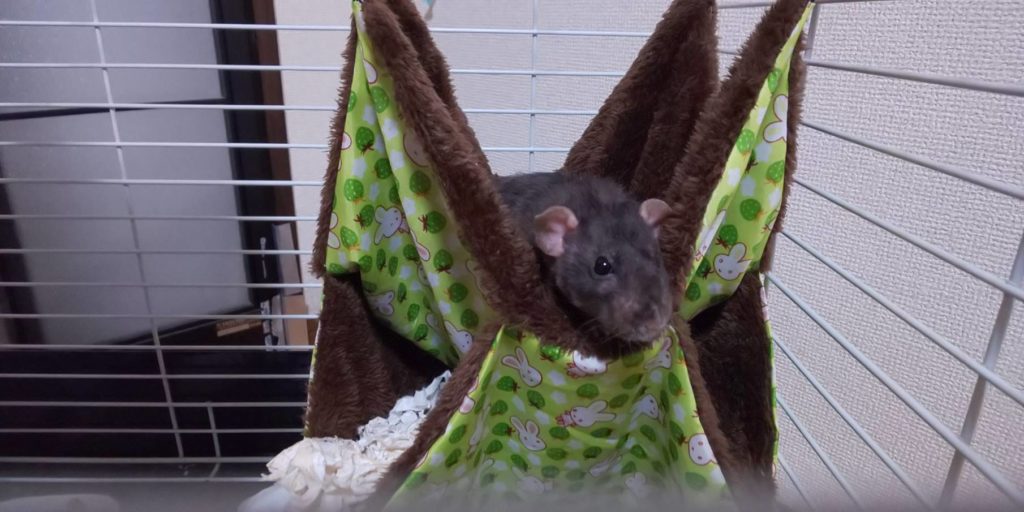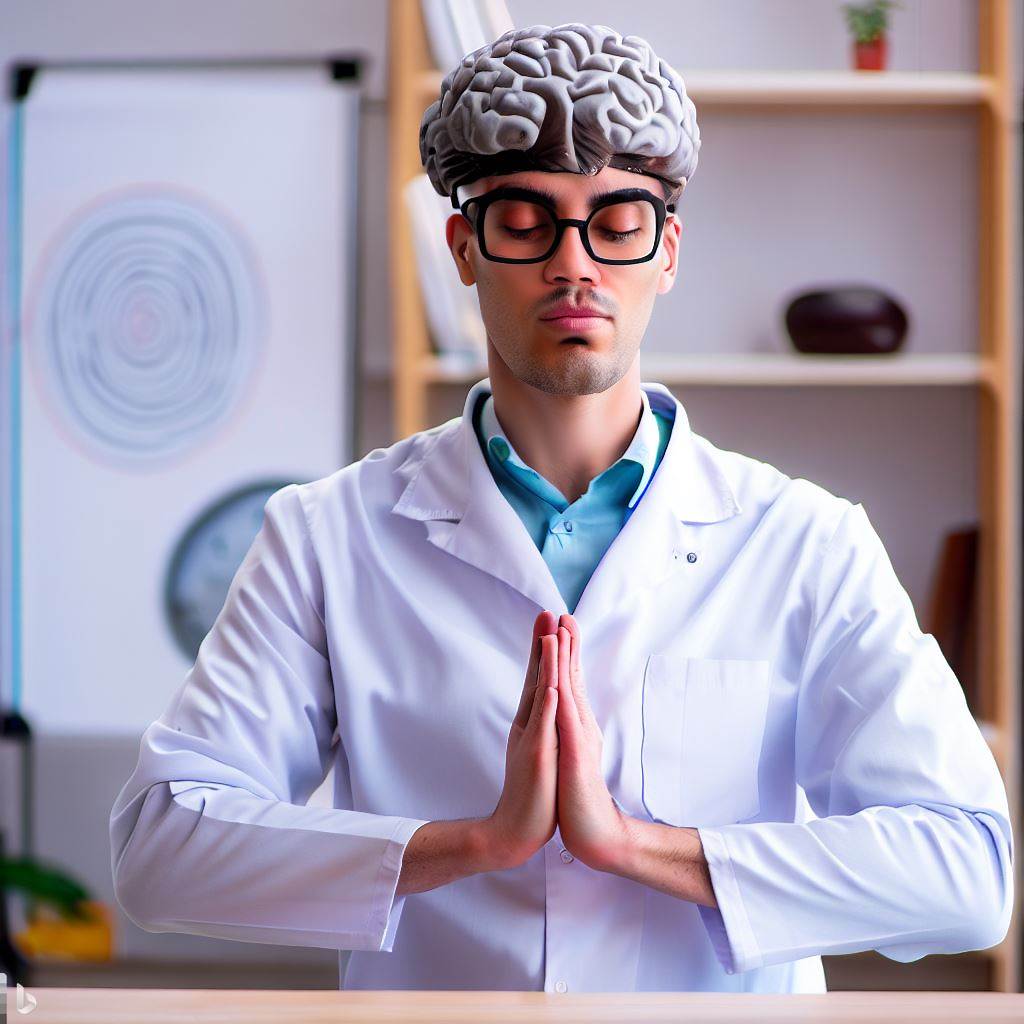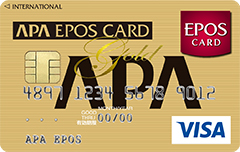はじめに: 近年、発達障害の患者が増加傾向にあります。その中でも、特に重症の発達障害を持つ人々の中には、長期的な引きこもりとなるケースが増えてきました。今回は、精神科医の視点から、その背景や社会復帰における課題について詳しく解説します。
発達障害とは? 発達障害は、言語や社会性、運動機能などの発達に障害が見られる症状のこと。多様性があり、一概に全ての発達障害者が同じ特性を持つわけではありませんが、日常生活や社会生活に支障をきたすことが多い。
重症の発達障害と引きこもりの関連性: 重症の発達障害を持つ人々は、対人関係の難しさや自身の能力の限界を痛感することが多く、それが長期の引きこもりを招く原因となります。特に社会性の発達に問題がある場合、学校や職場での人間関係の構築が難しく、孤立しやすい傾向があります。
社会とのギャップ: 現代社会は情報が溢れ、高速で変わることが求められる場面も多い。発達障害のある人々は、そういった変化に適応するのが難しく、ついていくのが大変だと感じることが多いです。その結果、自分の居場所を失い、社会から離れてしまうことがある。
社会復帰の難しさ: 一度社会から離れてしまった人々が再び社会に戻るためには、多くの支援が必要です。しかし、現状の支援体制は十分とは言えず、専門家もその難しさを痛感しています。特に、長期間の引きこもりとなってしまった場合、再び社会に適応するのは非常に難しい。
家族との関係性: 発達障害を持つ人々の家族も、大きな支えとなる一方で、過保護になることで問題を増幅させることも。家族との適切な関係性の構築は、社会復帰を目指す上での大きなポイントとなります。
専門家の意見: 多くの専門家は、早期の発見と適切なサポートが重要だと指摘しています。また、社会全体での理解と協力のもと、引きこもりの問題に取り組む必要があるとの声も。
まとめ: 発達障害と引きこもりの問題は、個人の問題だけでなく、社会全体での取り組みが求められる課題です。早期の発見や適切なサポート、そして周囲の理解と協力が必要です。一人ひとりがその背景や課題を理解し、温かな眼差しでサポートすることが、真の解決への第一歩となるでしょう。
具体的なサポートの方法: 重症の発達障害者が社会復帰を果たすためには、具体的なサポート策が必要です。以下は、その方法の一部をご紹介します。
-
職場や学校でのサポート: 専門のカウンセラーや支援員が配置され、日常の中での困難に対するサポートを提供することが重要です。
-
コミュニティベースの活動: 地域社会において、発達障害を持つ人々のための活動やグループを増やすことで、彼らにとって安心できる場を提供することができます。
-
情報提供: 発達障害に関する正確な情報を提供し、誤解や偏見をなくすことが求められます。
これからの展望: 近年、発達障害への理解が深まりつつありますが、まだまだ十分とは言えません。全ての人が安心して生活できる社会を目指し、発達障害を持つ人々もその中で輝ける場を増やしていくことが、私たち社会の責務となるでしょう。
終わりに: 発達障害と引きこもりの問題は、ただの「彼らの問題」として捉えるのではなく、社会全体での問題として共有し、解決策を考えていく必要があります。温かな理解と適切なサポートが、彼らの未来を明るくする鍵となることを忘れてはいけません。













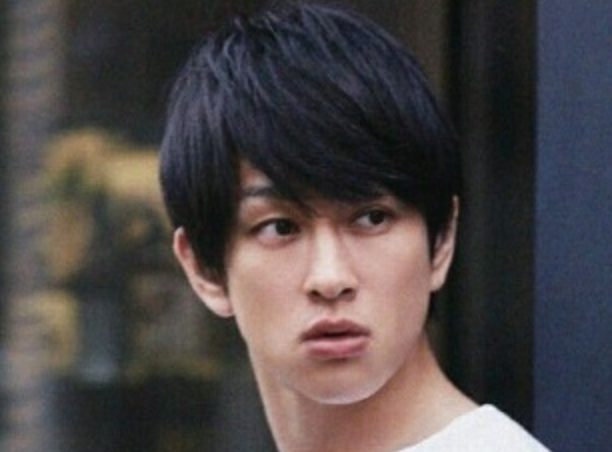








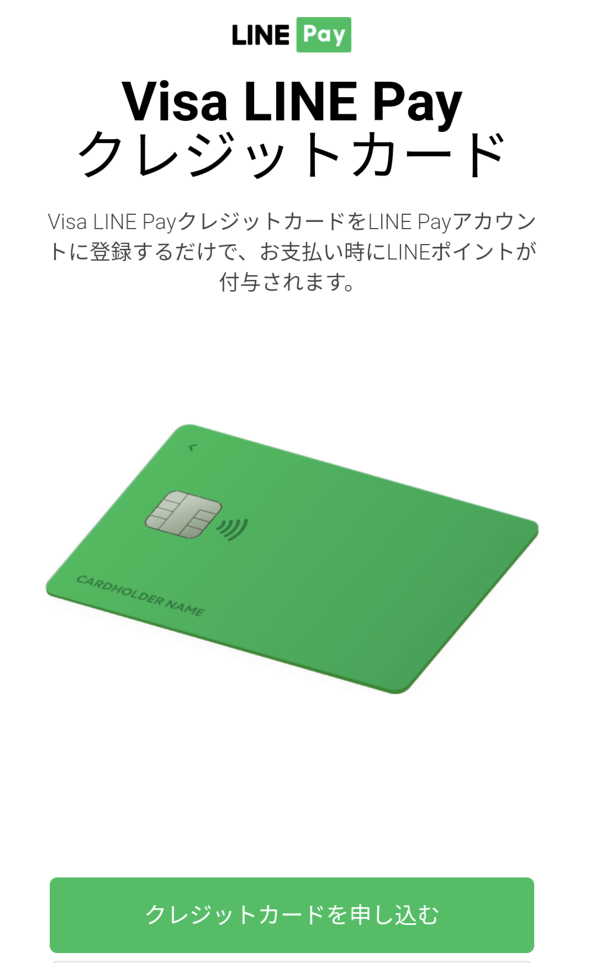
















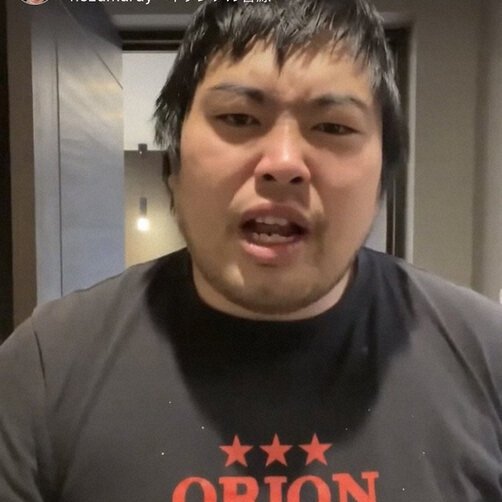

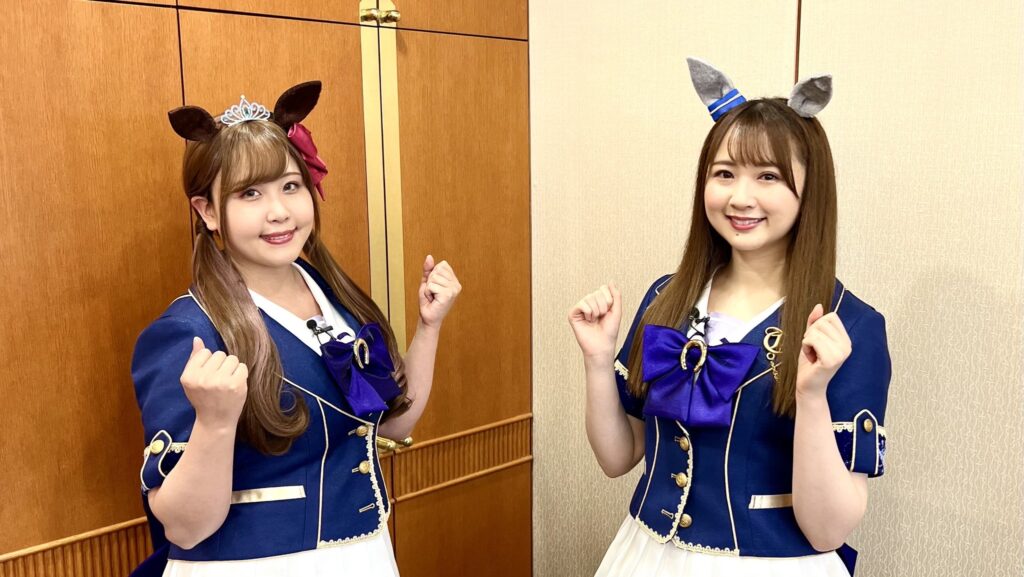


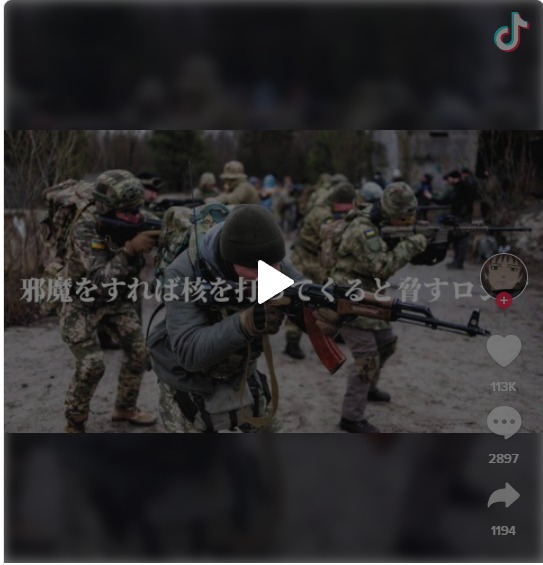









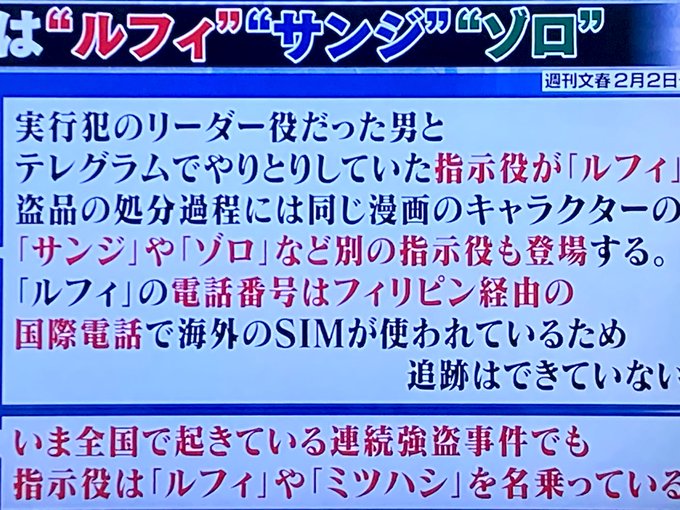



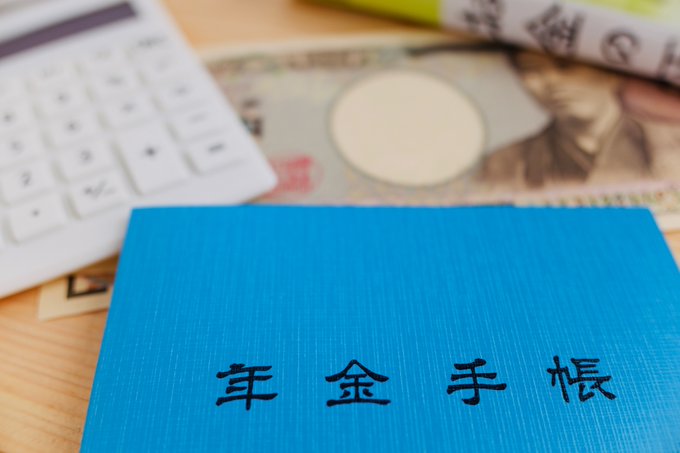















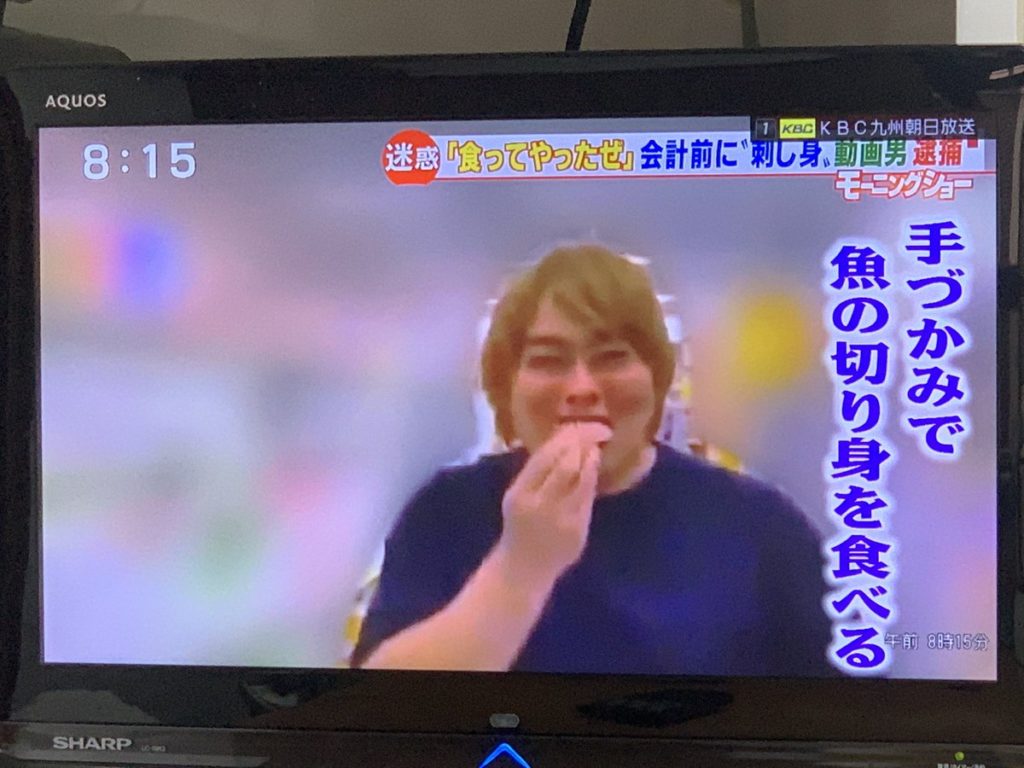












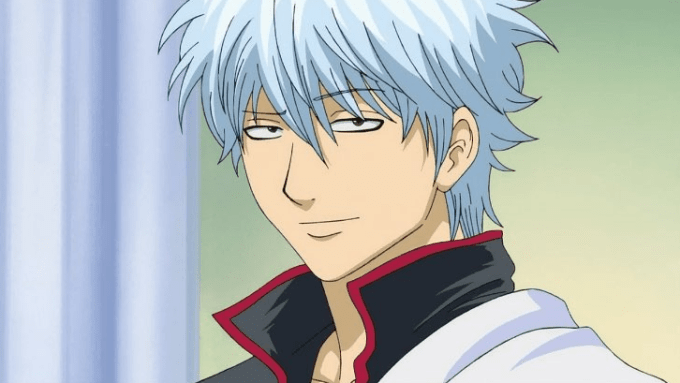

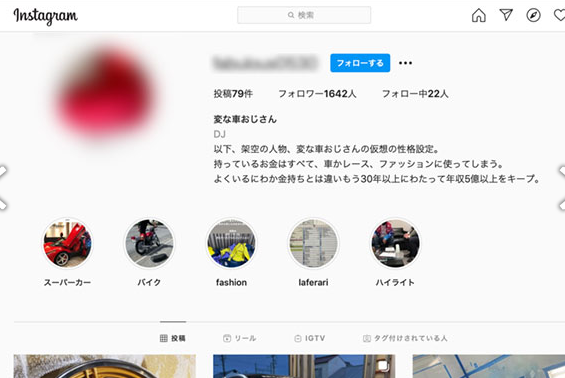






が年下サウナ社長と極秘結婚!-夫は取材に「前回の結婚との重複期間については明確に否定」-723x1024.jpg)









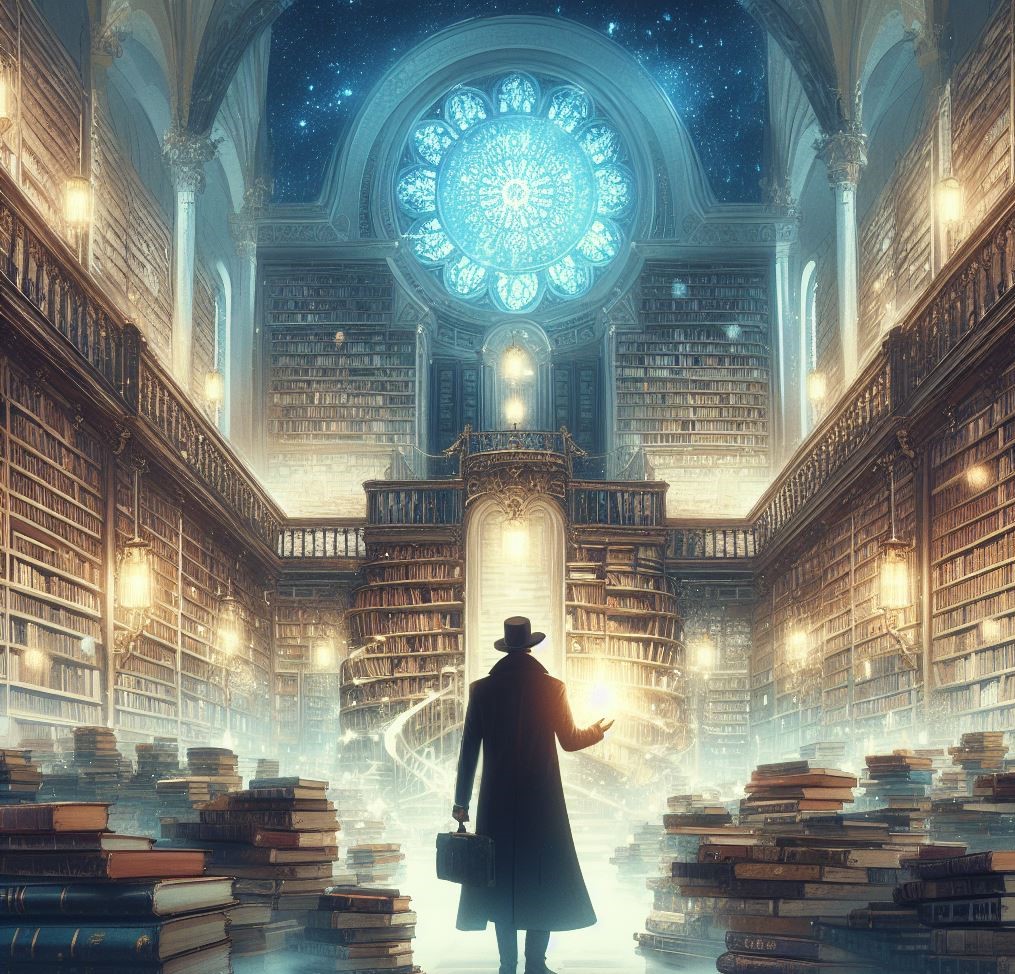
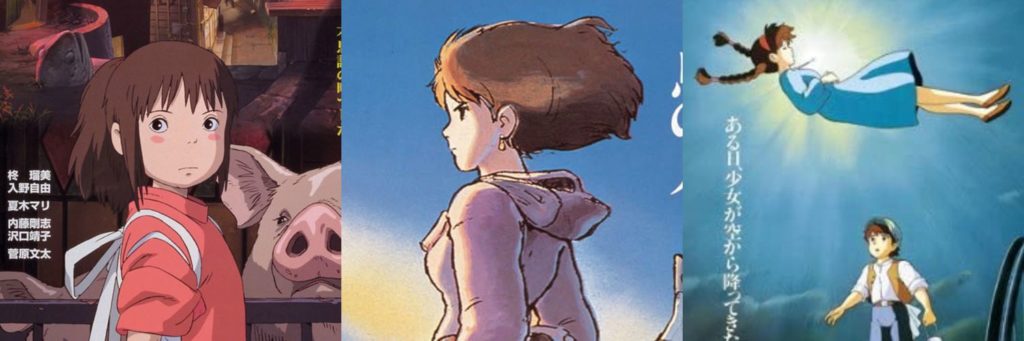




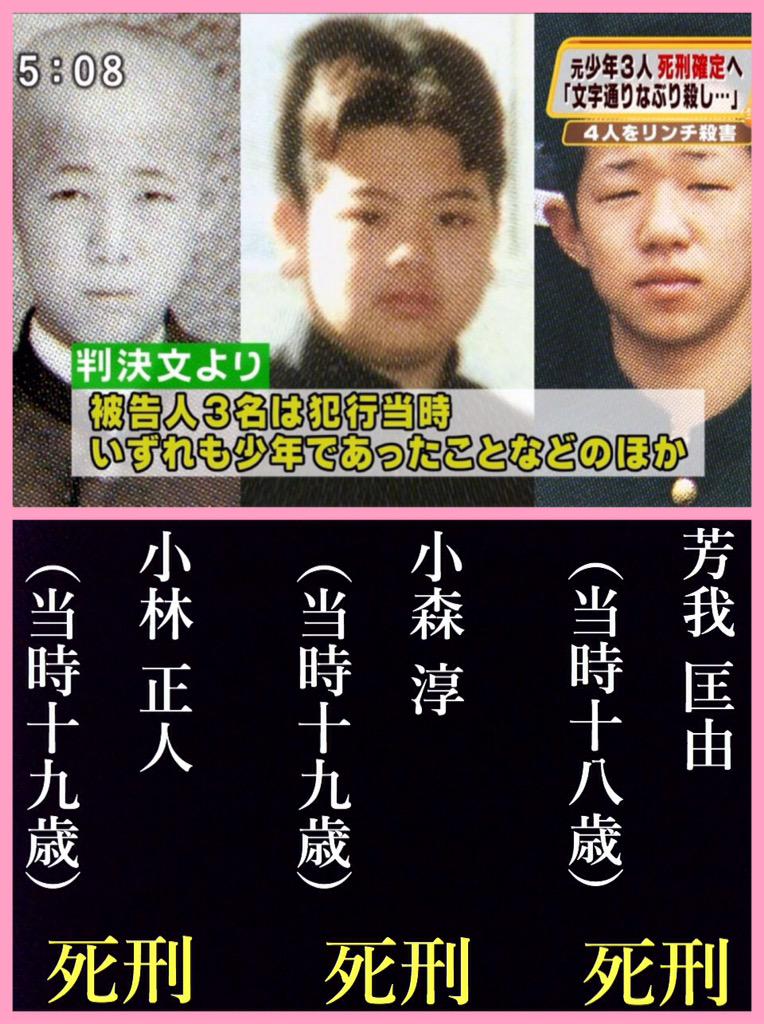
、たわわバストにくぎ付け!水着姿で圧倒的プロポーション ファン「メロメロ」絶賛の声殺到-768x1024.jpg)