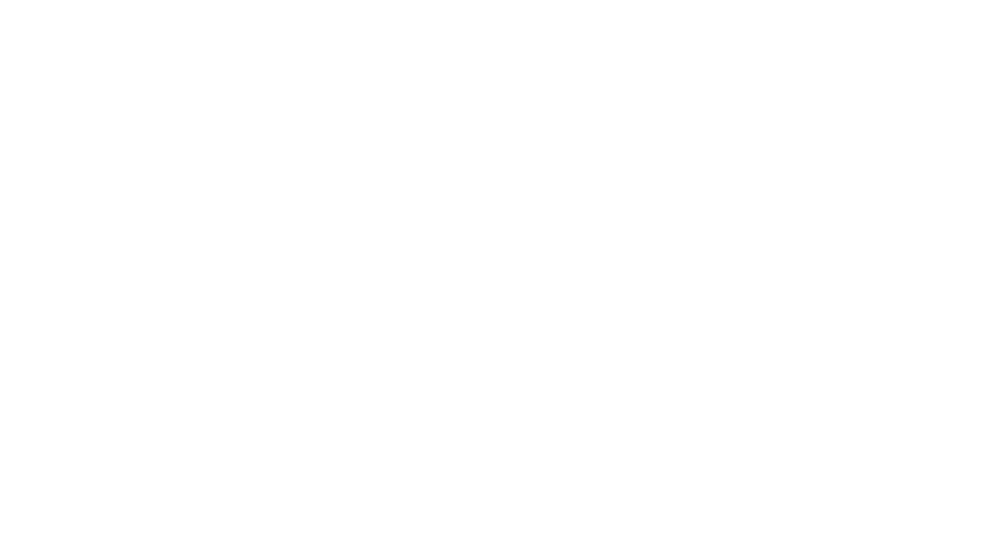【第1章:始まりの歌】
「はるちゃぴ、後ろ!」
大阪の名門劇場、シアター・ブラヴォの舞台裏で、そんな声が響いた。その声主は、グループの最年少、ゆまちだった。
何が起きているのかと思い、緊張と好奇心で舞台裏を見回すと、そこには青白い影が壁をすり抜けて消えていった。その不思議な現象を目の当たりにしたはるちゃぴは、恐怖よりも謎解きへの情熱に火がついた。
「ゆまち、それ見た?」
はるちゃぴは視線をメンバーたちに移し、一人一人の反応を見た。きよたんとゆうも同じように目を丸くしていた。
舞台裏は、青白い影の存在がすっかり空気を変えてしまった。通常であれば、機器のクリック音やスタッフの足音、楽器のチューニング音で賑わっている舞台裏は、まるで時間が止まったかのように静まり返っていた。
「どうするの、はるちゃぴ?」
と、心配そうなゆうの声が響いた。その声は、はるちゃぴの心の中に深く響いた。彼女はリーダーとして、何かアクションを起こさなければと感じた。
そこで彼女は、舞台裏の深部へと足を向けた。怖さを押し殺して前へ進む彼女の姿は、勇敢な戦士そのものだった。
「大丈夫、みんな。一緒に解決しよう。」
その言葉と共に、はるちゃぴはメンバーたちに勇気を与え、新たな物語の幕開けとなった。
【第2章:恐怖の始まり】
公演中止の知らせが流れ、はるちゃぴたちは狼狽えつつも舞台後方の控室へと引き上げた。控室の一室は緊迫した雰囲気で包まれていた。木目調のインテリアがほの暗い光に照らされ、独特な静寂が漂っていた。
「これで、どうなっちゃうんだろう…」
きよたんが小さな声でつぶやくと、ゆうとゆまちもうなずいた。
「でも、私たちだって何とかするよね?」
ゆまちがはるちゃぴを見上げると、はるちゃぴは小さく頷いた。
「うん、怖いけど…これを解決しないと…」
はるちゃぴはその場に深呼吸をして、自分を落ち着かせようとした。その瞳には、恐怖を超えた決意と信頼感が浮かんでいた。
ゆうが軽くはるちゃぴの肩を叩いた
「みんな、はるちゃぴを信じてるから。一緒に乗り越えようね。」
と声をかけた。その言葉に、はるちゃぴは安堵の笑みを浮かべた。
「ありがとう、ゆう。」
と感謝の言葉を返し、はるちゃぴは再び自分自身を奮い立たせた。
「それじゃあ、計画を立てよう!」
と彼女の力強い言葉が、控室内に響き渡った。
この部屋からは、青白い幽霊という未知の存在に立ち向かうための、彼女たちの勇気と決意が溢れ出していた。
「計画って何?」
ゆまちの純粋な問いに、はるちゃぴは思わず微笑む。
「まずは、その…幽霊っぽいものが現れた原因を探ることだよ。」
と、はるちゃぴは力を込めて言った。そして彼女は立ち上がり、胸を張った。
「それから、どうやってそれを解決するかを考える。」
控室は暖色系の落ち着いた色調に包まれ、ふかふかのソファにはゆうときよたんが座っていた。コーヒーテーブルの上には、カップと水筒がほんのりと光を反射していた。その空間は、はるちゃぴたちの緊張感でピリピリとしていた。
「でも、どうやって?」
と、きよたんが尋ねた。はるちゃぴは眉をひそめて考え込み、答えを模索した。
「まずは、あの幽霊が現れたときの状況を思い出してみよう。何か変わったことはなかった?」
言葉を発するたびに、はるちゃぴの中に新たな力が湧き上がってきた。
「それと、劇場のスタッフや、観客に話を聞いてみるのもいいかも。」
ゆうが提案した。はるちゃぴは頷く
「いいね、それ。」
と彼女の提案を受け入れた。
その後、彼女たちは自分たちが見聞きしたことを話し合い、新たな手がかりを探すことに一心になった。それぞれの言葉は、未知の恐怖に対する彼女たちの力強い決意を象徴していた。

【第3章:謎の追跡】
翌日の明るい朝、はるちゃぴたちは大阪市内にある古めかしい喫茶店「カフェ・ミヤコ」に入った。その店内はレトロな雰囲気が漂い、棚には昔ながらの喫茶器具がずらりと並んでいた。大阪の人々が思い思いに過ごす中、はるちゃぴたちは自分たちの捜査を開始した。
「ちょっと、おじちゃん。この辺りで、何か変なこと起きてないですか?」
はるちゃぴが背中を丸め、バーカウンター越しに店主に尋ねた。
店主は中年の男性で、白髪が頭の一部を覆っていた。彼はゆっくりとコーヒーカップを下ろし、思案の眼差しを向けた。
「変なこと、かぁ…」
彼の声はゆったりとしていて、まるで時間を刻む振り子のようだった。
はるちゃぴは、この探求の旅が自分に与える新たな経験を楽しむことを決めた。奇妙な現象に直面した恐怖と混乱が、彼女の好奇心と情熱をかき立てた。
「最近では…そうだな。」
店主がふと思いついたかのように言った。
「実は、この近くの公園で夜中になると奇妙な光が見えるという噂があるんだ。」
「えっ、本当に?!」
はるちゃぴの顔が驚きで見開かれた。この情報は、彼女たちの捜査に新たな糸口を提供してくれたかもしれない。
「うん、でもそれが真実かどうかはわからないよ。」
店主は再度コーヒーを注ぎながら言った。
「ただ、噂を信じる人たちが夜中に公園を散歩する姿を見ると、なんだか微笑ましい気がするよ。」
これ以上の情報を得るために、はるちゃぴは次の行動を考える。自分の心の中に迸るエネルギーと、彼女自身の未知への興奮を感じながら。
【第4章:公園の夜】
その夜、はるちゃぴとメンバーたちは指定された公園に足を運んだ。公園はひっそりとしており、唯一の光源は遠くに見える街灯だけだった。木々の間から月の光がほんのりと漏れ、不思議な雰囲気を醸し出していた。
「ここが、おじちゃんが言ってた公園かな?」
ゆうが疑問を投げかけた。その声は暗闇の中で反響し、一行に緊張感を高めた。
「うん、そうみたいだよ。」
はるちゃぴが答えた。
彼女は周囲を見回しながら進んだ。
「それに、奇妙な光を見るためには、もっと深く入らないといけないんじゃない?」
心配そうに見つめるきよたんに対して、はるちゃぴは自信満々の笑顔を向けた。
「心配しないで、きよたん。何かあったら、私が先に行くから。
」彼女の勇気ある表情は、他のメンバーたちにも力を与えた。
そして彼女たちは公園の深部へと進んで行った。
静かな夜の中で、彼女たちの足音だけが響き渡った。
そんな中、はるちゃぴは公園の何かに引きつけられるような感覚を覚えた。
「あれ、見て! あそこに光が…!」
とゆまちが指を指した方向に、はるちゃぴたち全員が視線を向けると、確かに何か輝くものが見えた。
「これが…噂の光?」
ゆうが囁いた。
はるちゃぴは不思議そうに眉をひそめ、さらにその光の方向に進むことを決断した。
「行こう、これこそが次の手がかりかもしれないよ。」
そんな彼女たちの決意と勇敢さは、探求心を刺激するものだった。だが、その光の正体が何であるかを解明するためには、まだまだ彼女たちには試練が待ち受けていたのだ。
























とみられる男の身柄確保-818x1024.jpg)




















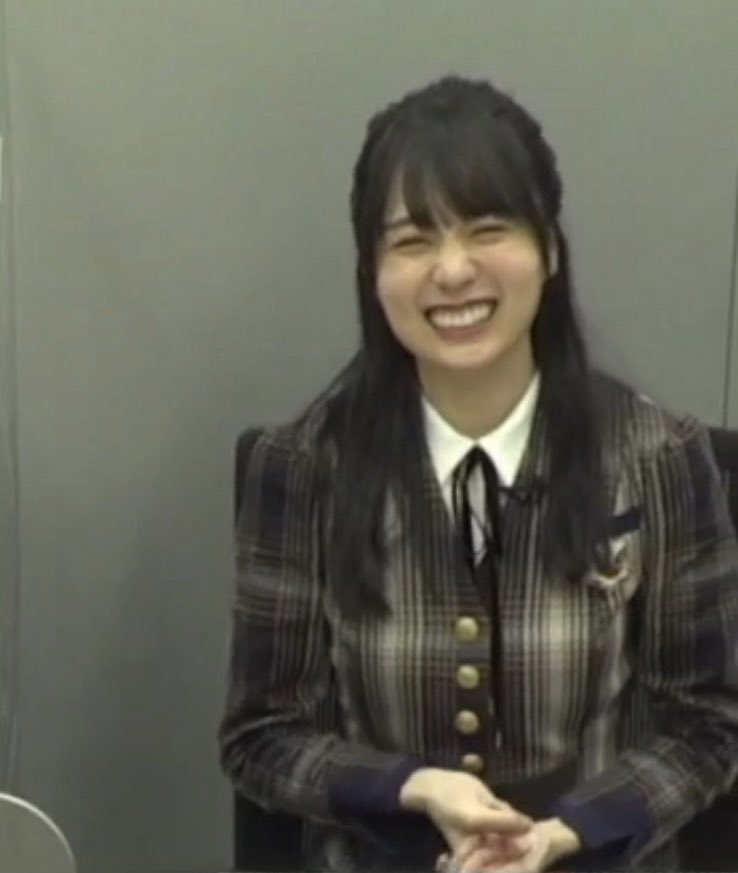




、ビキニ姿で豊満バスト大胆披露!「スタイル良すぎ」「たまりません!」-819x1024.jpg)









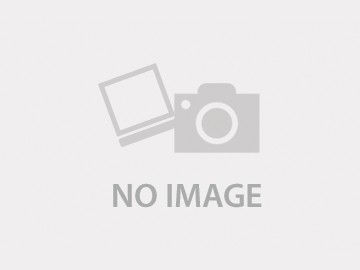

















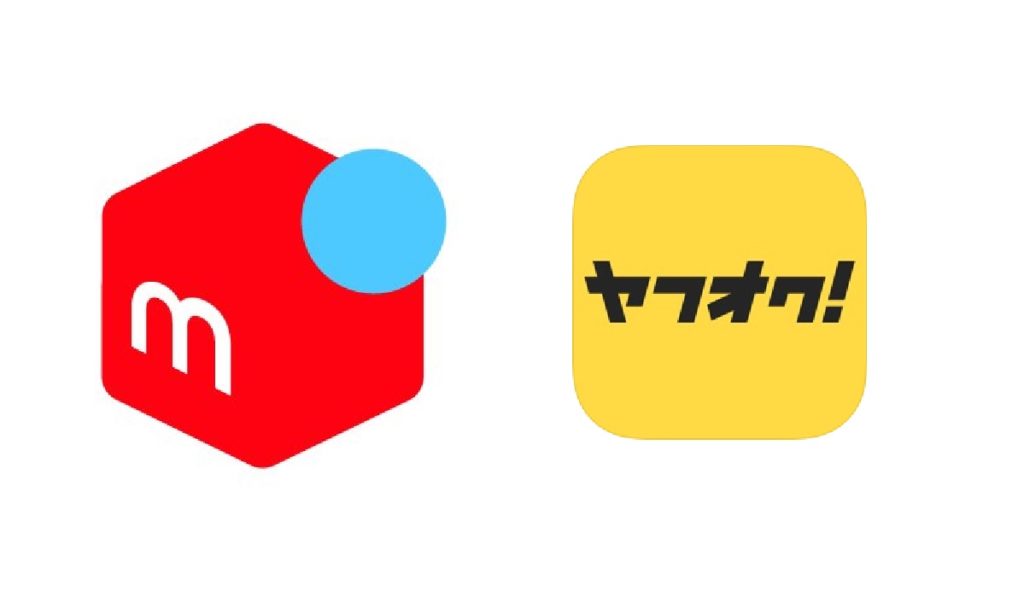





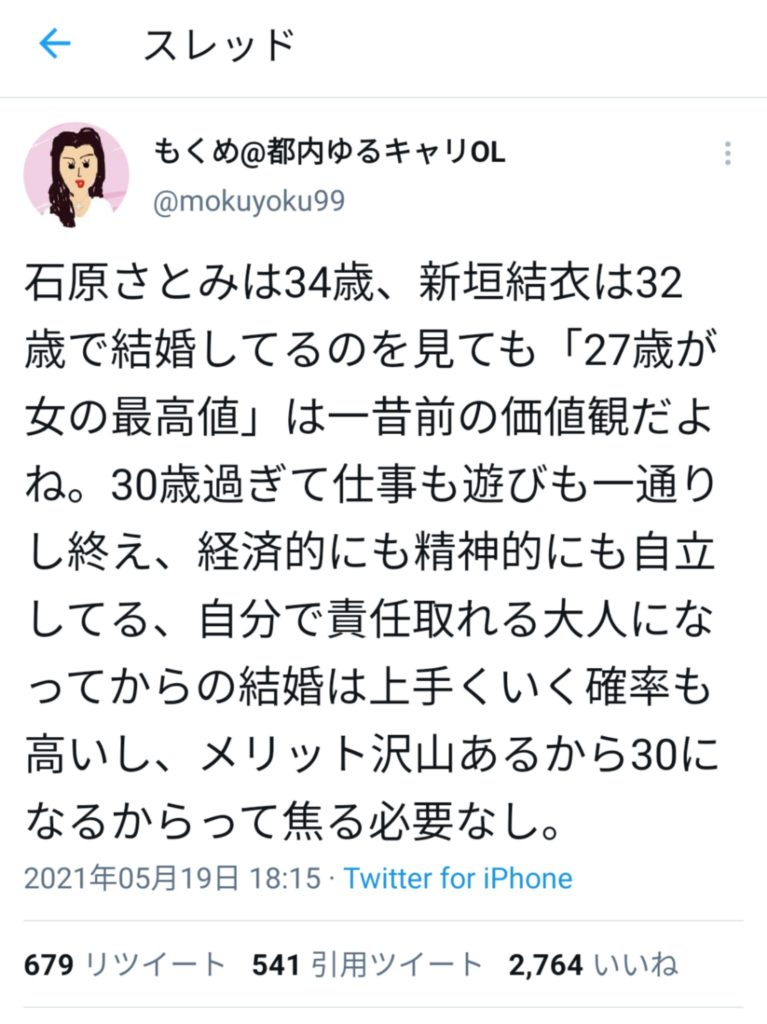




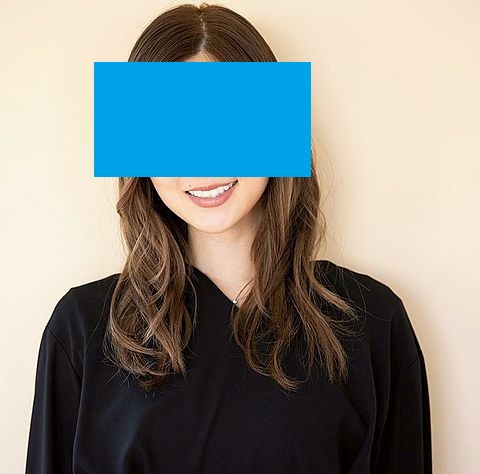




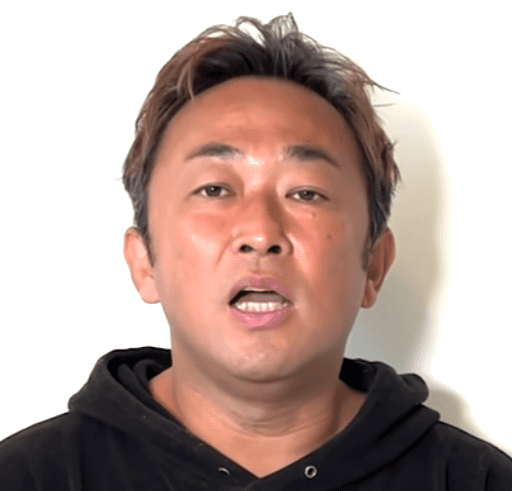



















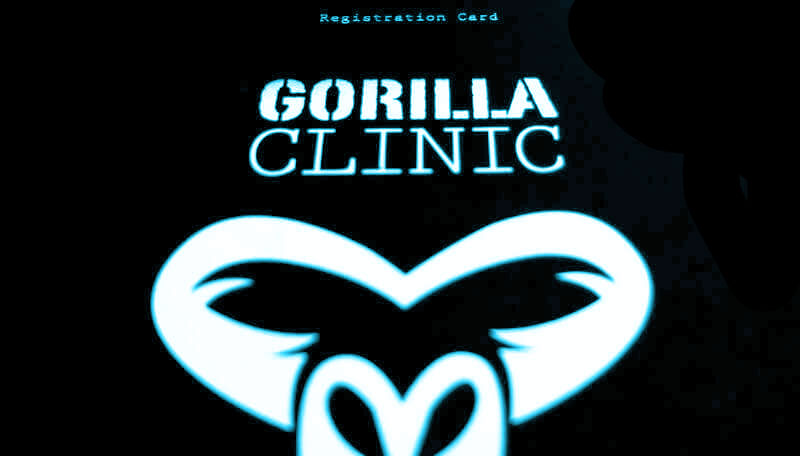
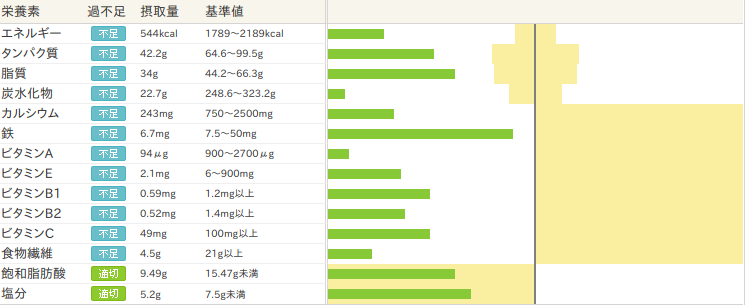


































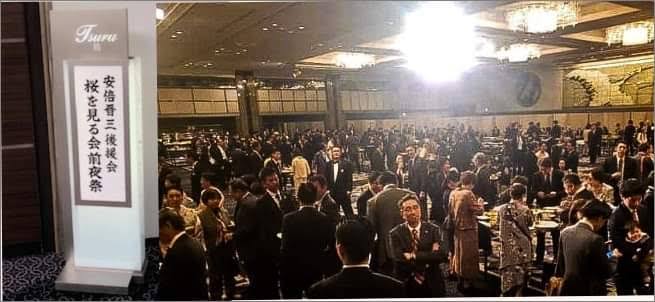







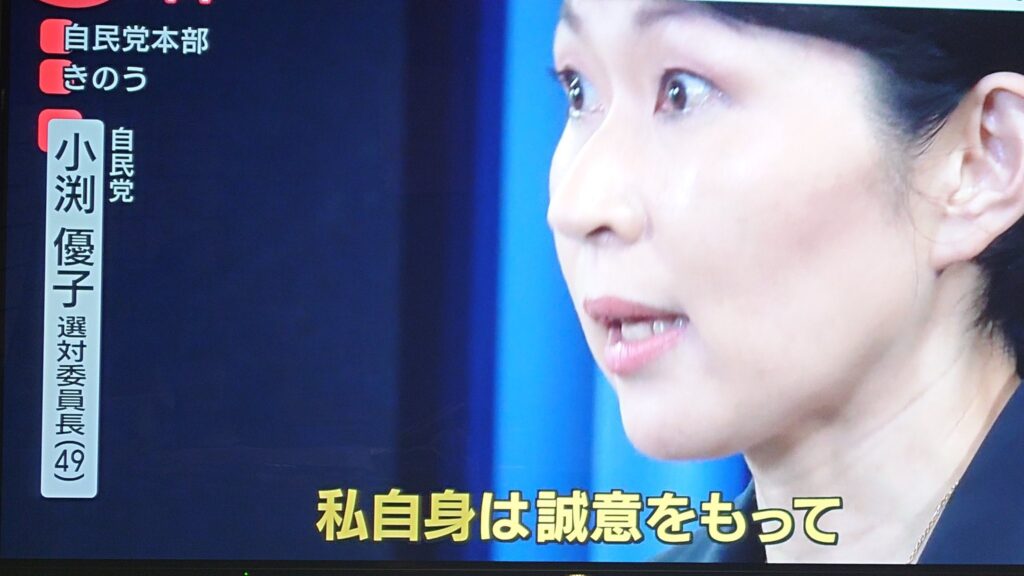
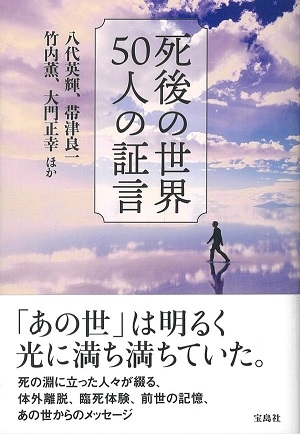








とみられる男.jpg)





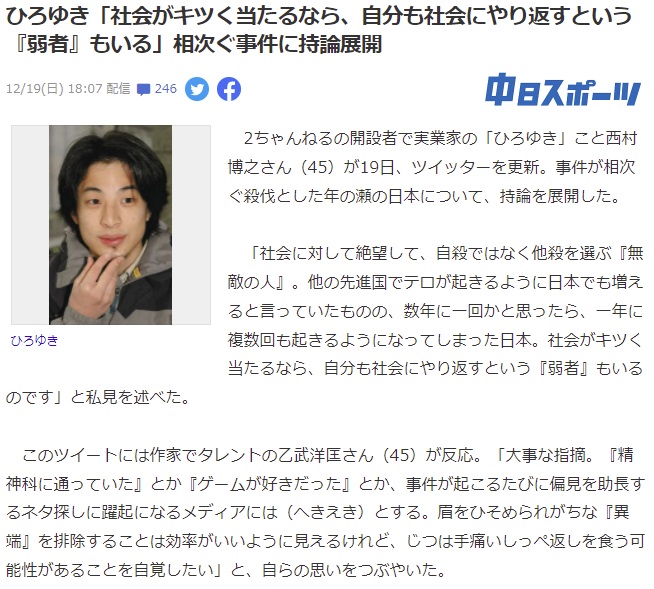










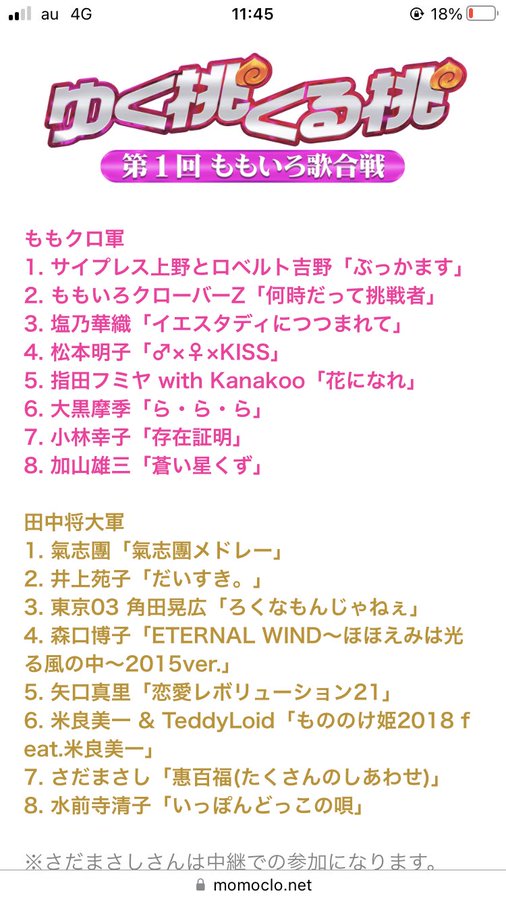

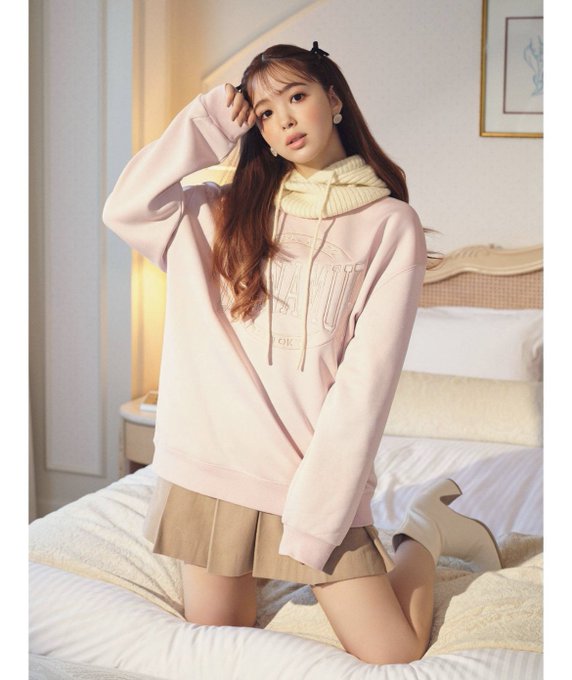












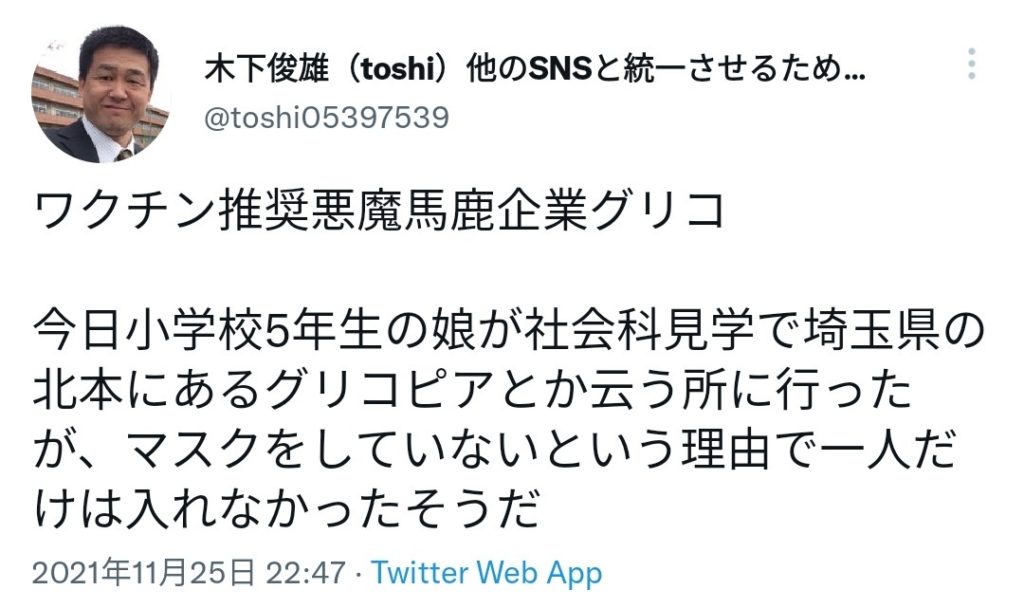






















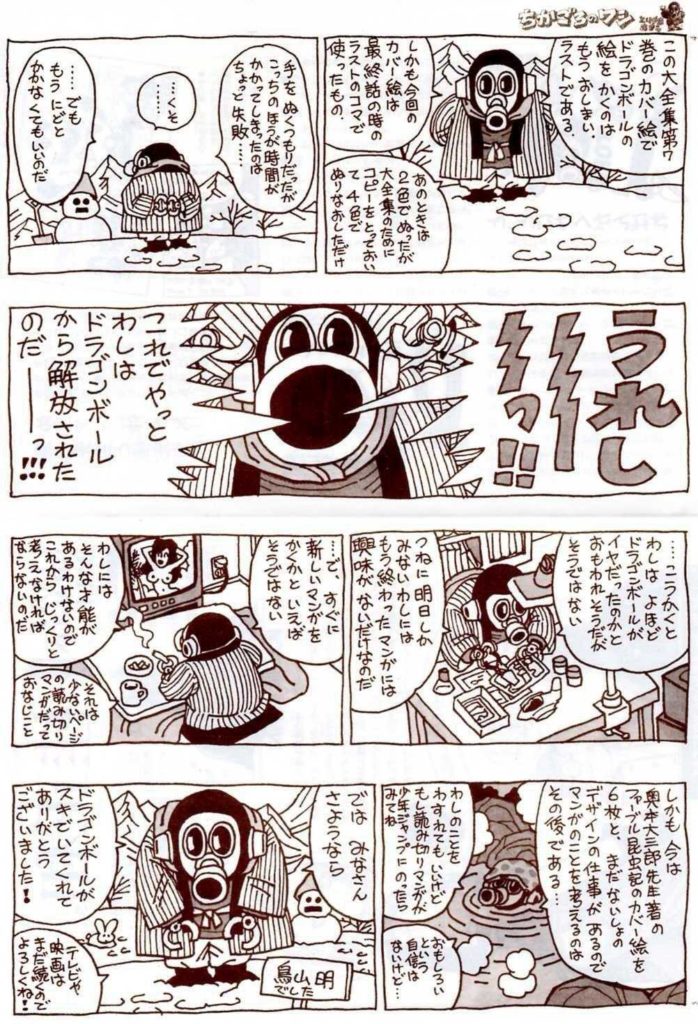





















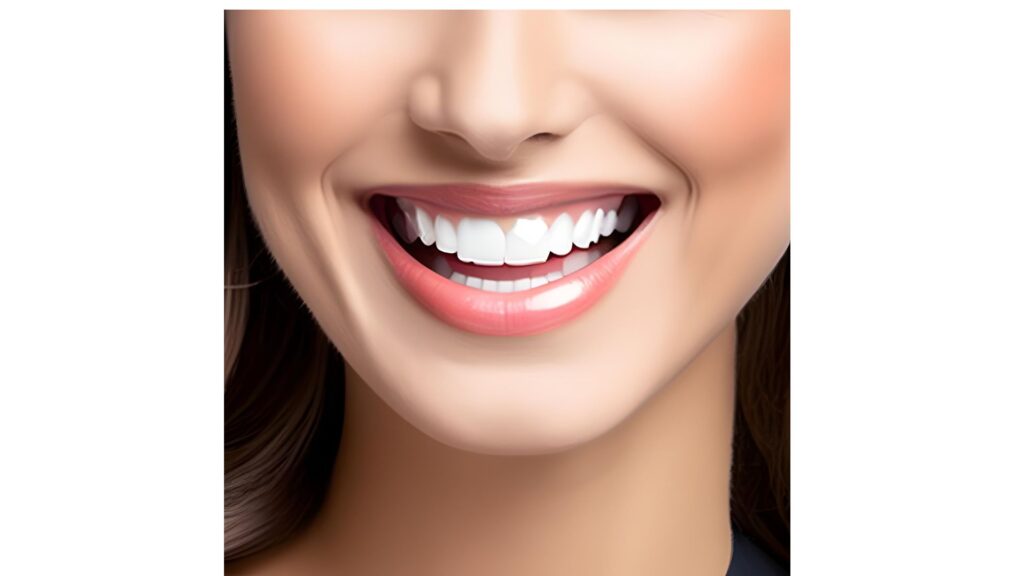





本当は無職 婚活アプリで知り合った40代女性に詐欺容疑 女性名義でアウディをローンで購入-1024x576.jpg)























」は、両方とも姿勢に関連した問題ですが、異なる状態を指します。.jpg)