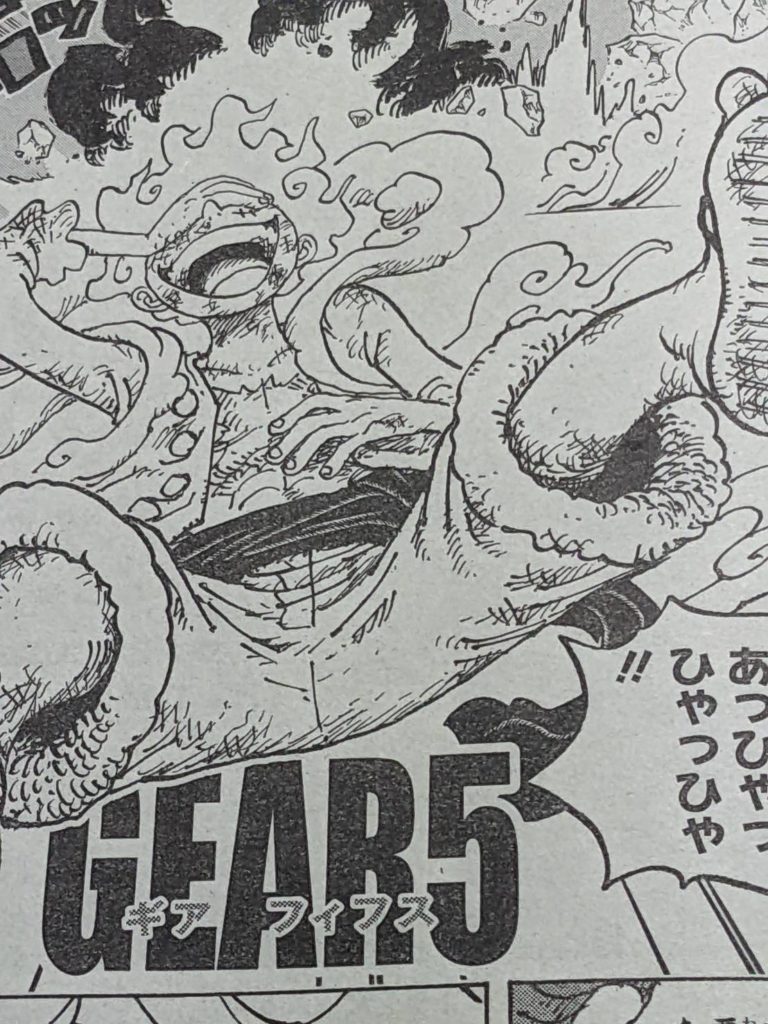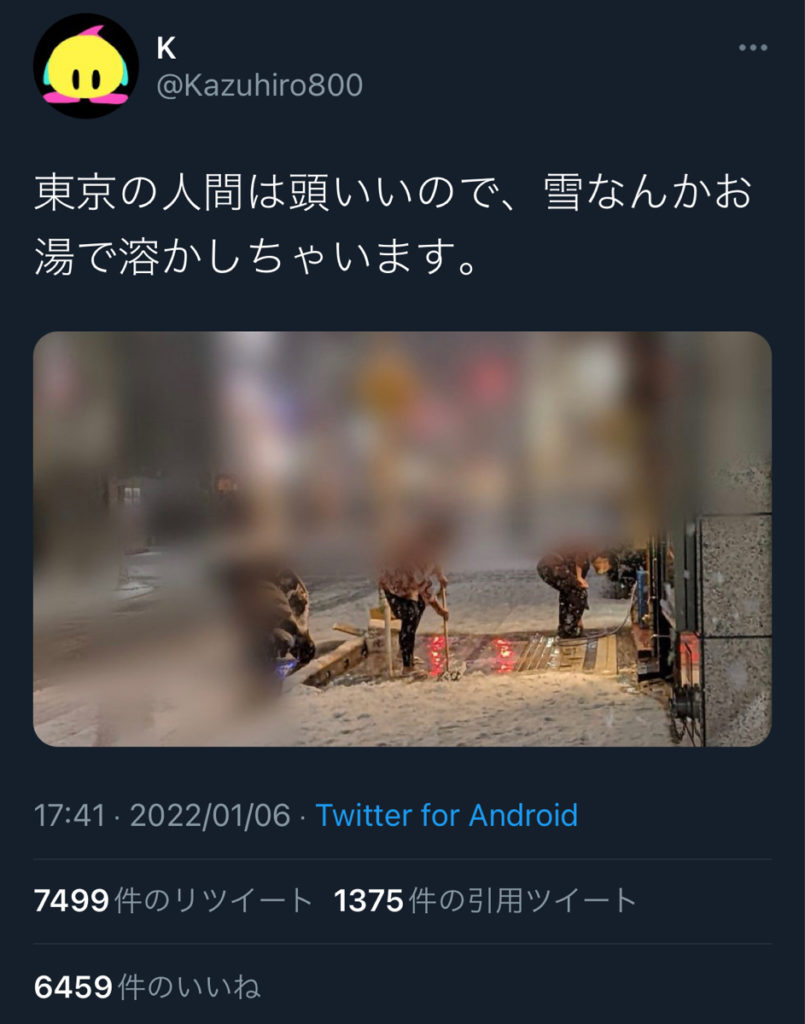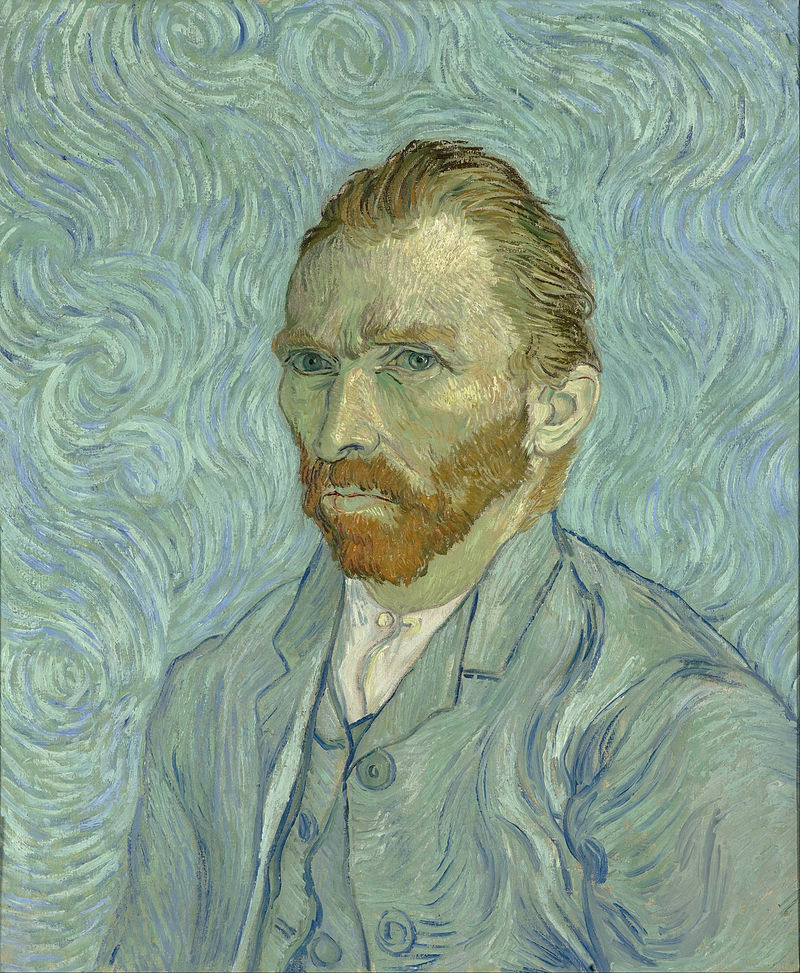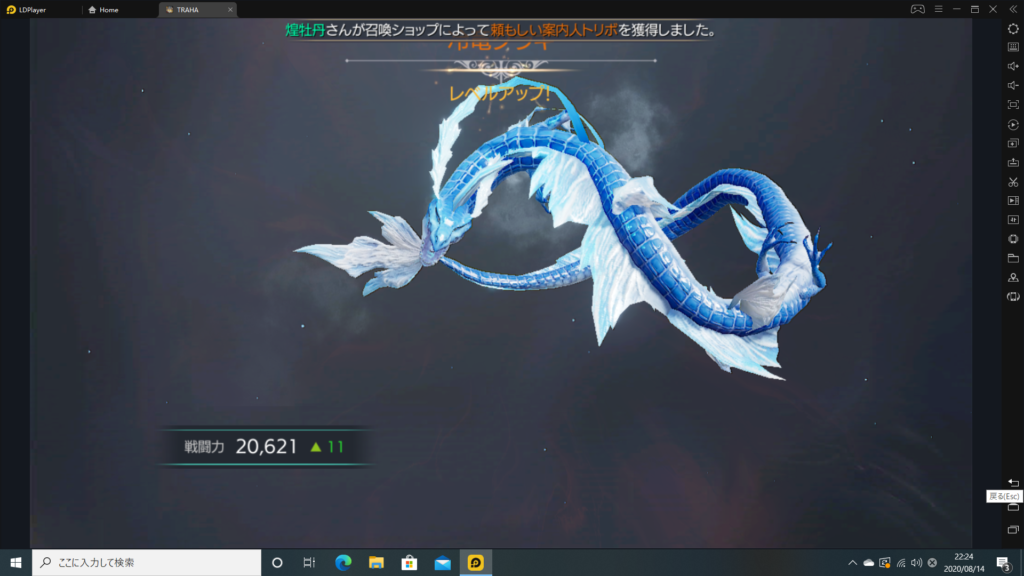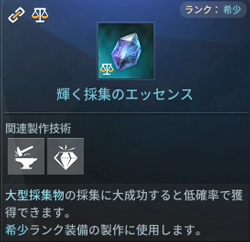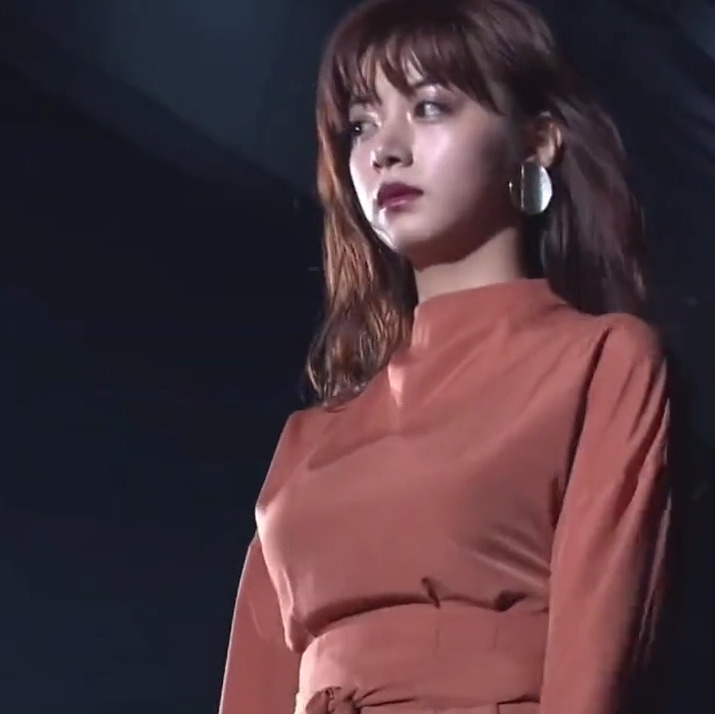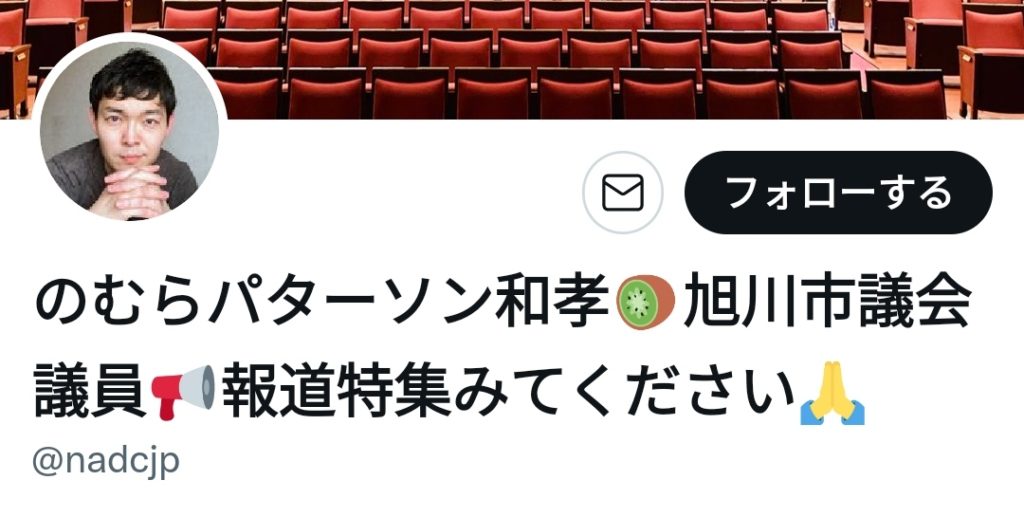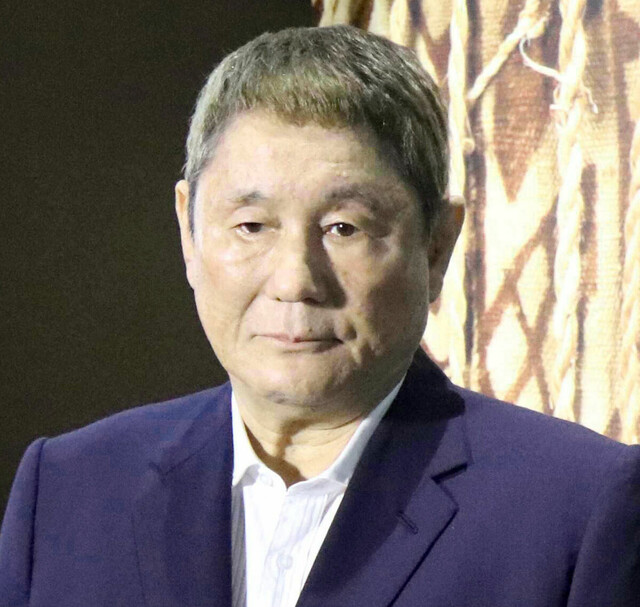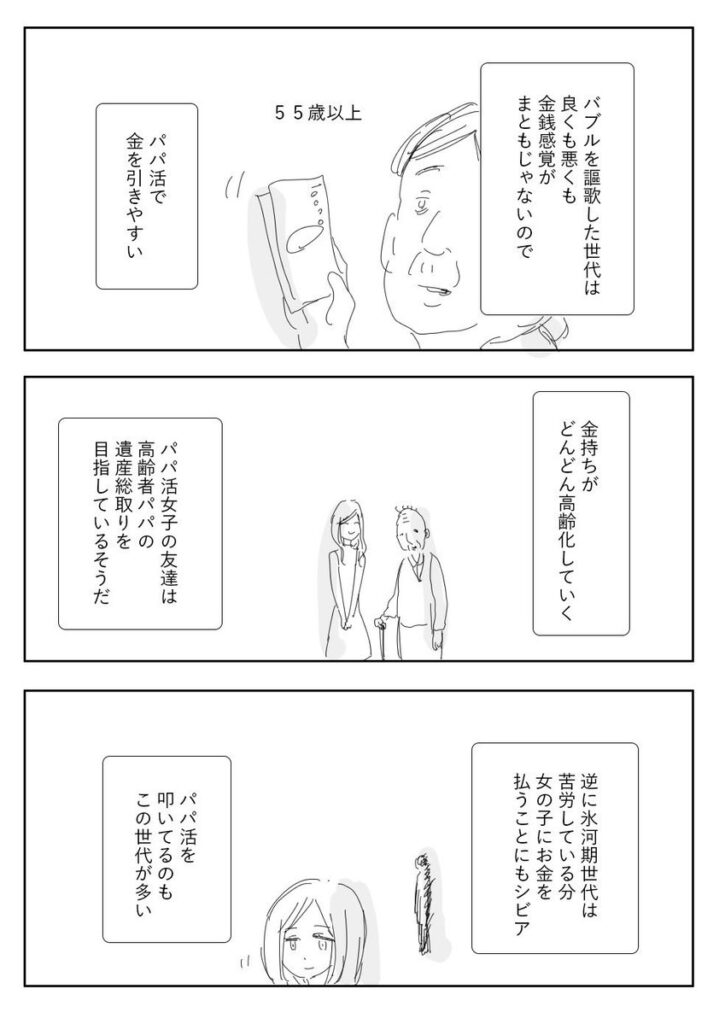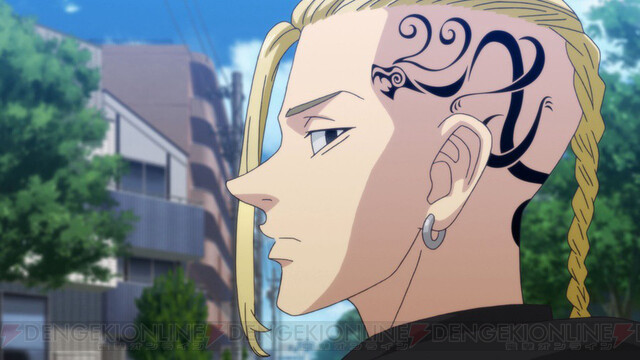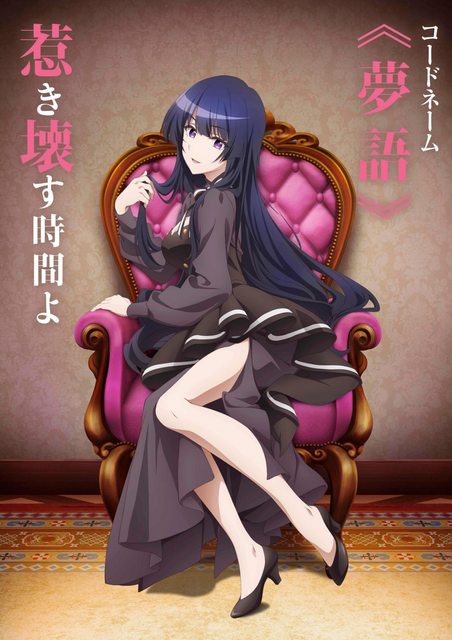石川和正がなぜ徳川家康を裏切って織田信長から豊臣秀吉についたのか、その背後にある理由は、戦国時代の複雑な政治的舞台と人間関係の絡み合いからなる興味深い一章です。石川和正は、長らく徳川家康に仕え、戦国時代の重要な出来事に深く関与してきました。彼は織田信長の死後、小牧・長久手の戦いにおいて徳川家康と豊臣秀吉との対立が激化する中、驚くべき決断を下すことになります。
家康に仕える石川和正は、家康の家老として信頼され、家康の戦略や外交交渉において重要な役割を果たしてきました。彼は家康の息子たちの人質交換や和睦交渉を担当し、その影響力は大きなものでした。しかし、小牧・長久手の戦いの後、和正は家康との対立を深め、家康の元を離れて秀吉に味方する道を選びました。この裏切りは、戦国時代最大の謎の一つとされ、多くの歴史家たちがその背後にある複雑な要因を解明しようとしてきました。
その背後には何があったのか。この謎は石川和正の個人的な動機、政治的な利害関係、そして当時の情勢の組み合わせに由来しています。石川和正は家康に忠誠を誓いながらも、秀吉との交渉において彼自身の野心や視野を広げていた可能性が考えられます。また、家康との対立や不協和音が背後にあったかもしれません。一方で、秀吉は家康の強大な力を認識しており、その力を味方に引き入れることで更なる勢力拡大を狙った可能性も指摘されています。
この裏切りは、歴史の中で大きな影響を与えました。石川和正の決断は、戦国時代の勢力争いや武将たちの信念と野心が交錯する中で生じた重要な局面であり、その影響は後の歴史にも及びました。この事件を通じて、当時の政治的状況や人間関係の複雑さが浮き彫りにされます。
要するに、石川和正の裏切りは、個人の野心や政治的な利害、時の流れと交錯した結果であり、その真相は未だに解明されぬ謎として歴史の中に刻まれています。彼の決断は、戦国時代の激動の舞台におけるひとつの鏡であり、その意味を深く追究することは、日本の歴史と人間の複雑な心の動きを理解する上で重要な一歩と言えるでしょう。





















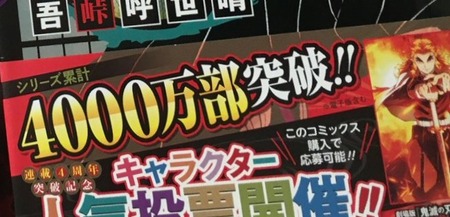








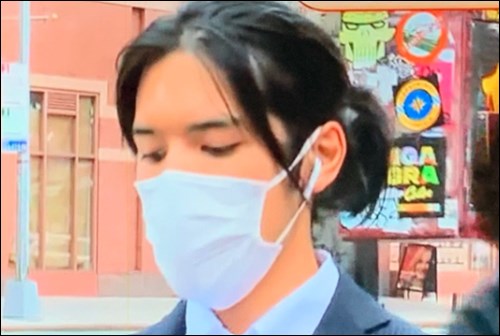



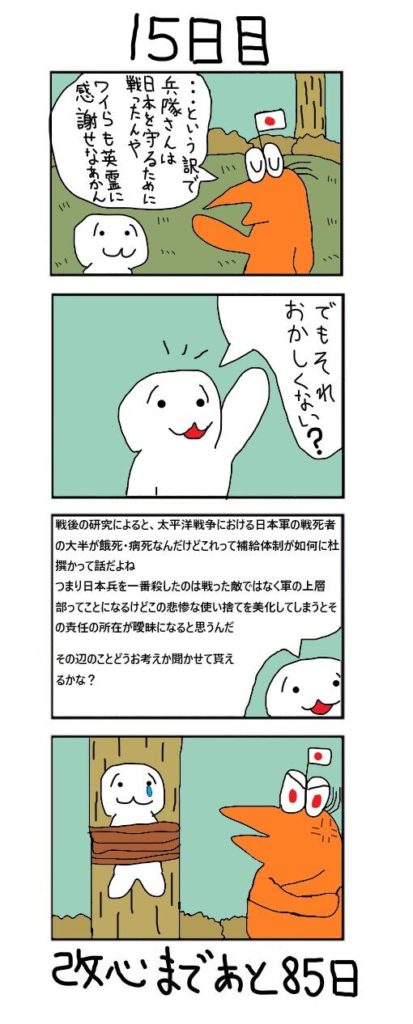








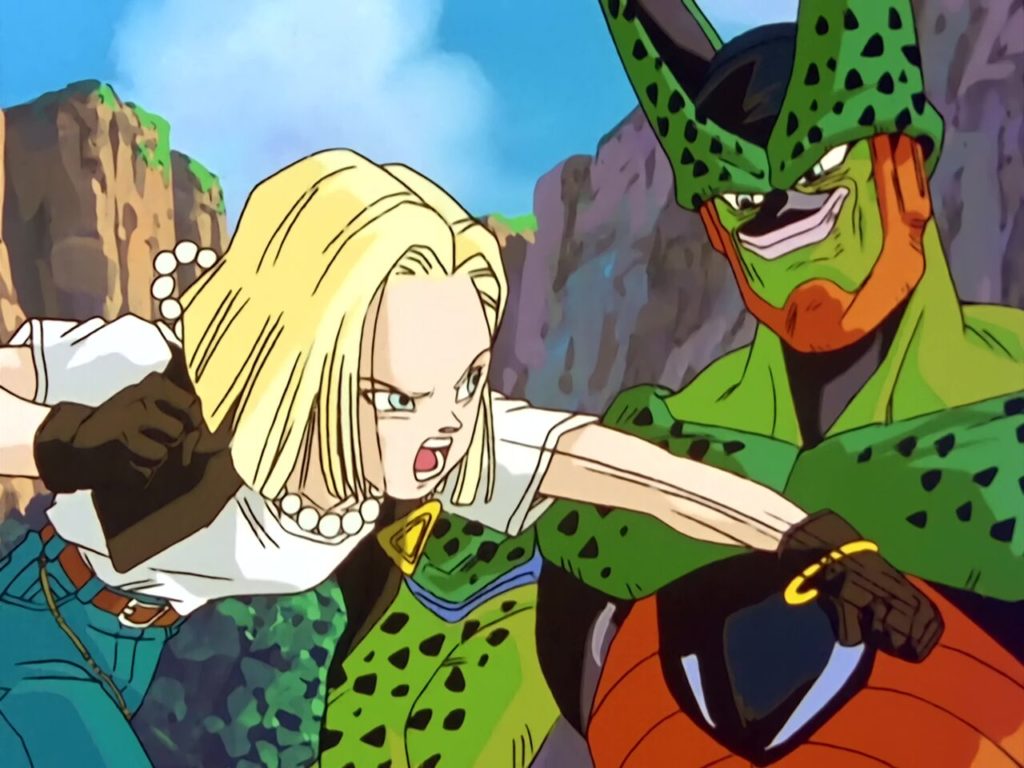





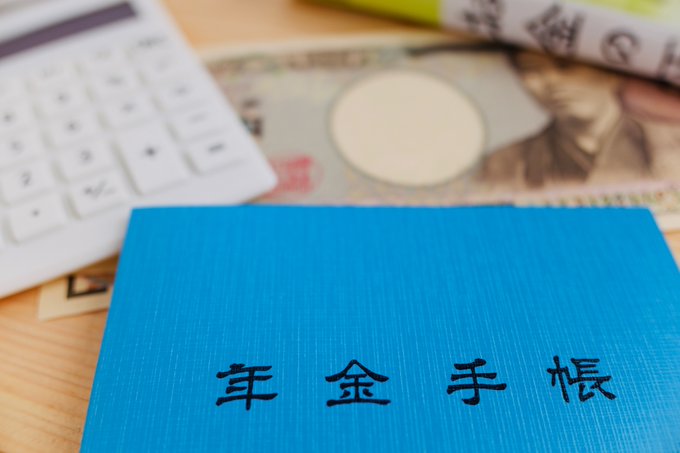
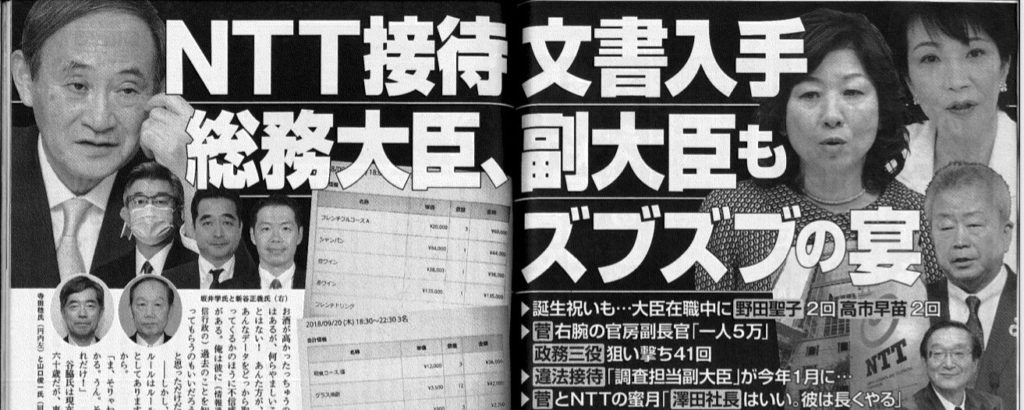
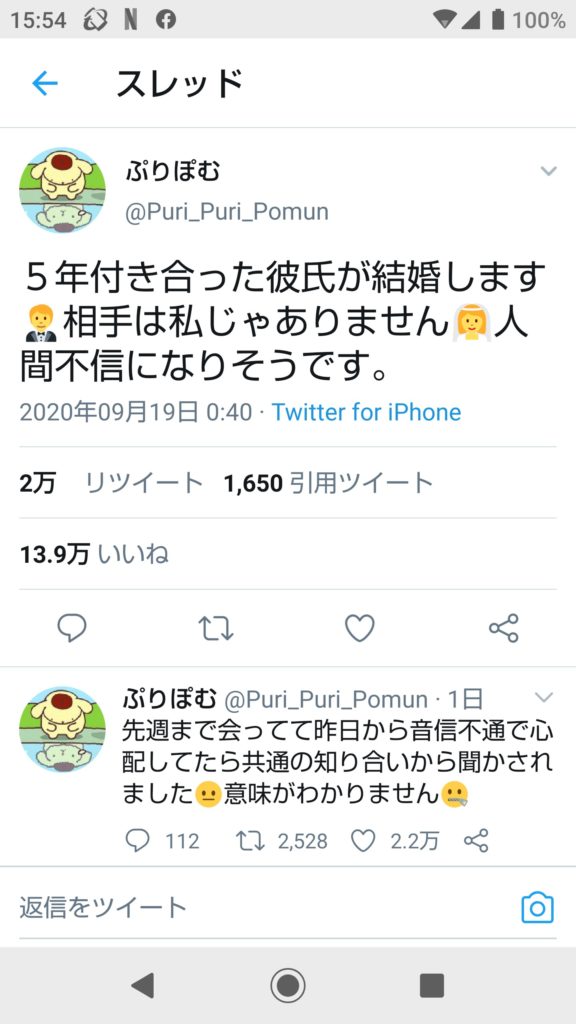

















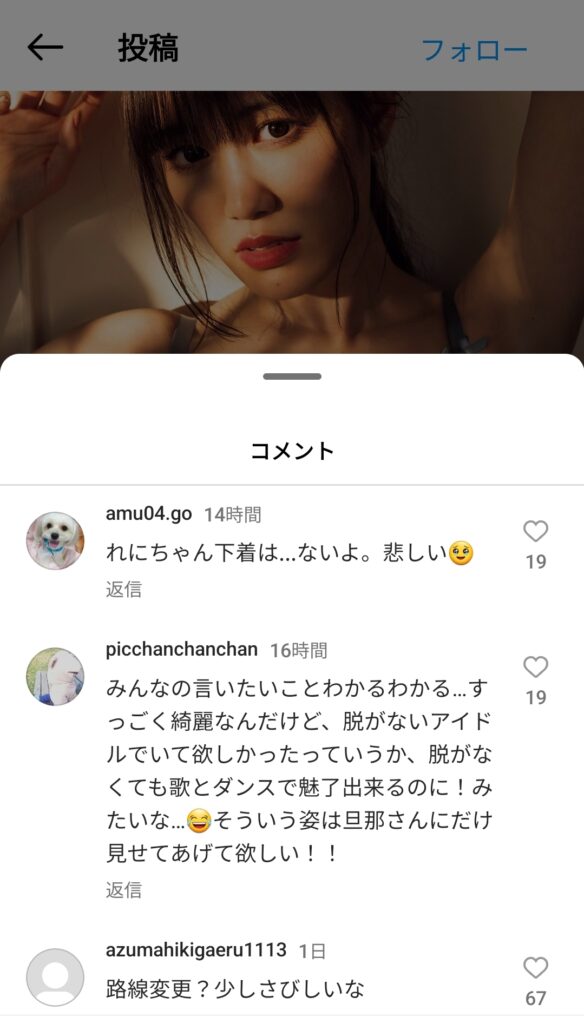



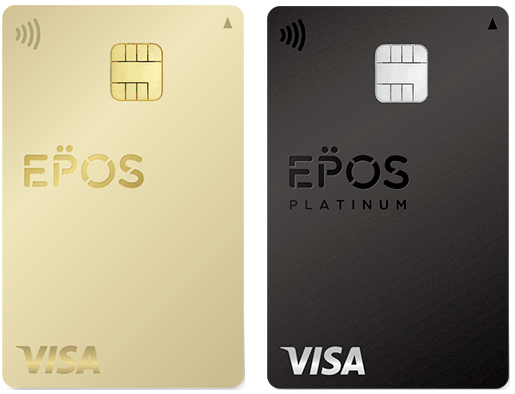











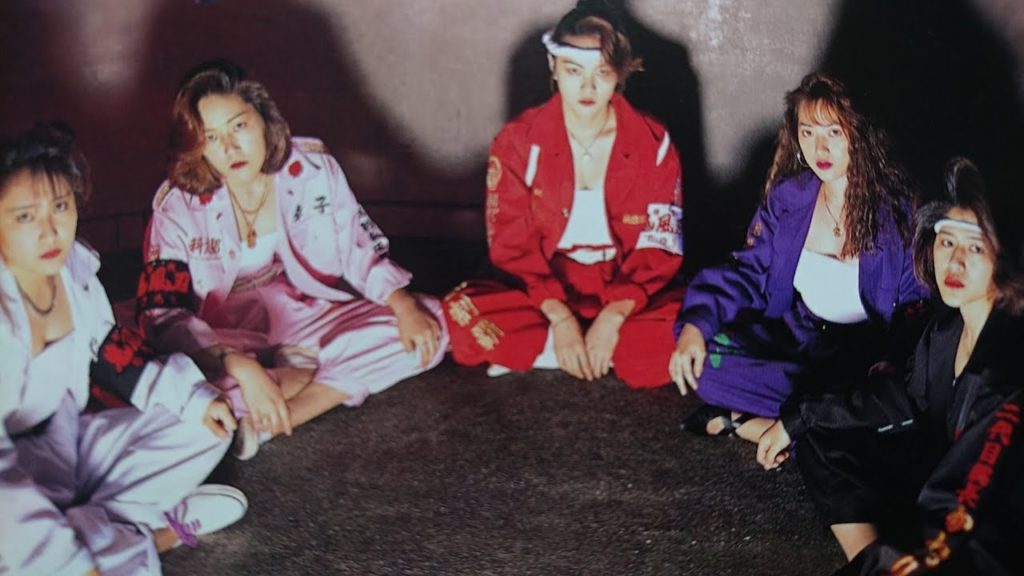

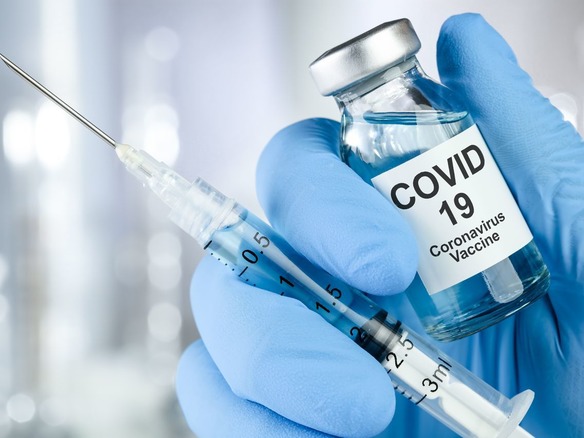







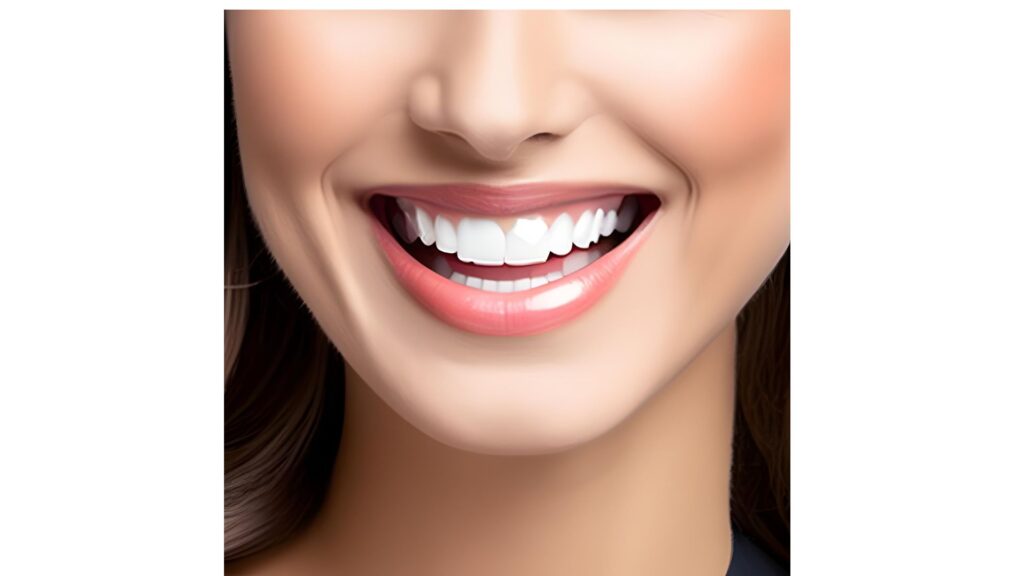



















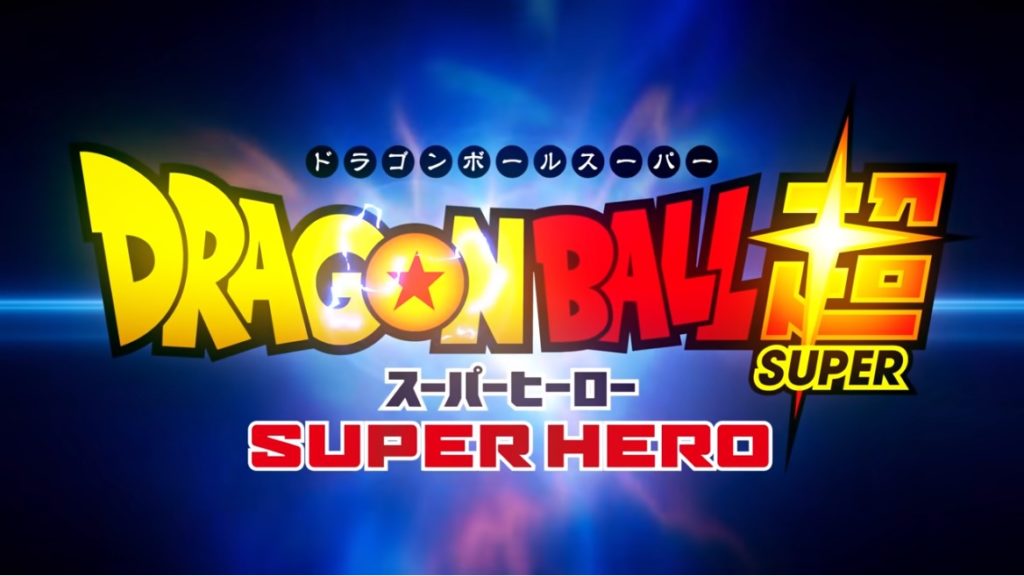











































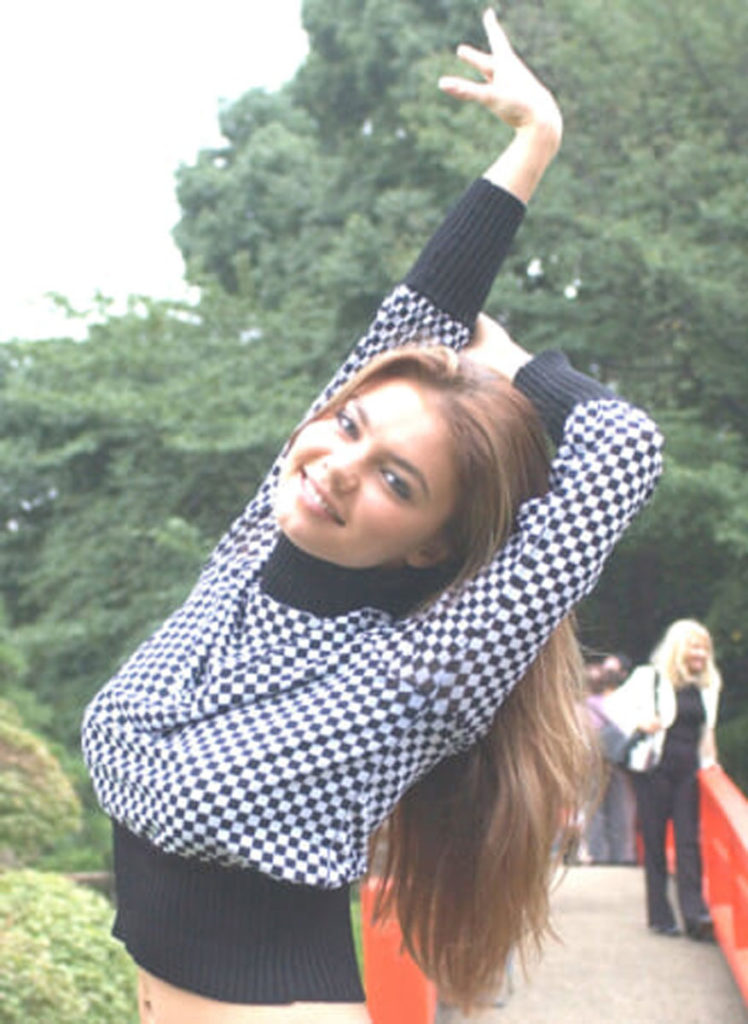





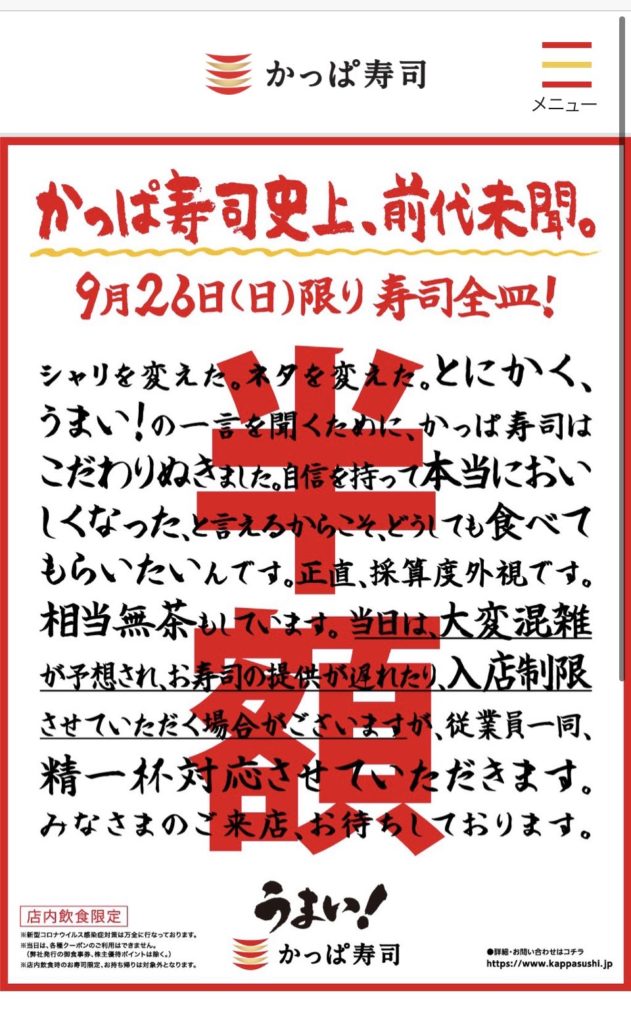

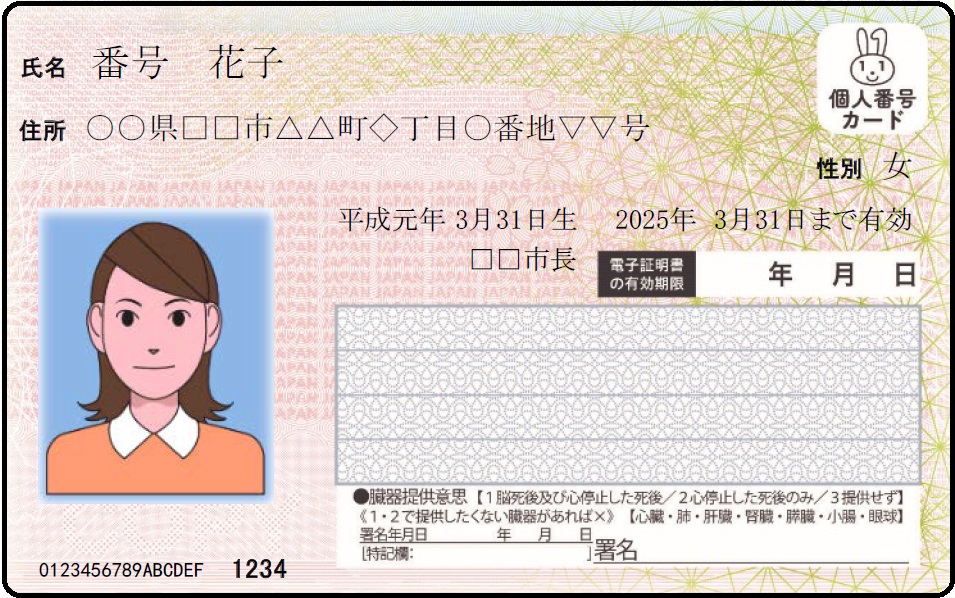









とのお別れのときが来たな.jpg)
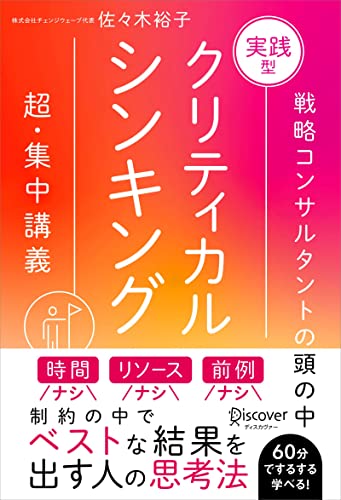



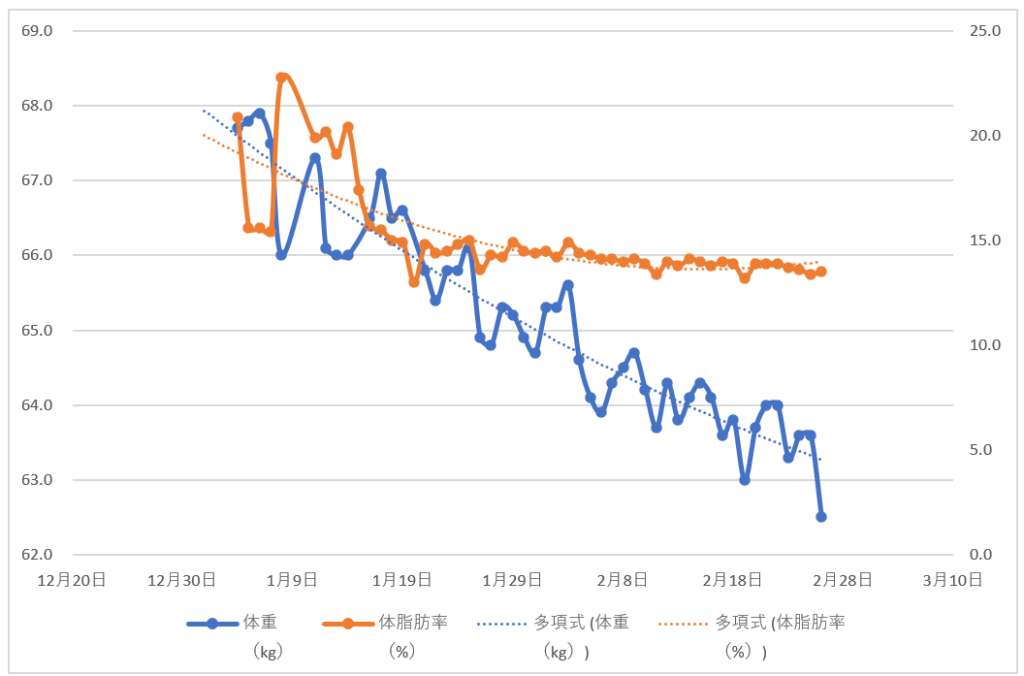

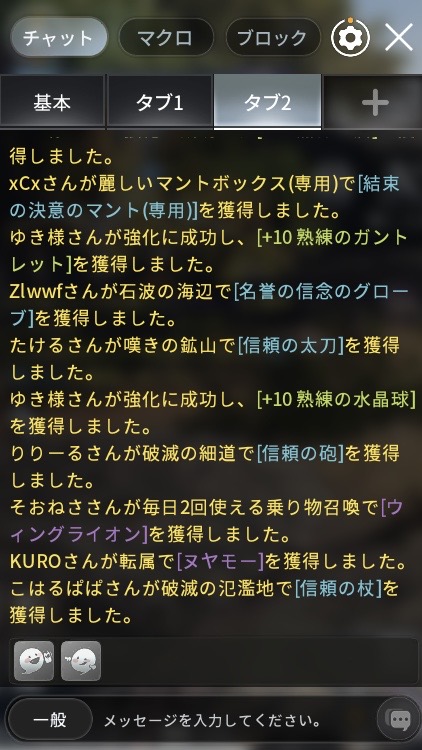
、卒業公演で号泣!「一度きりの人生。自分の好きに正直に生きてください!」--768x1024.jpg)