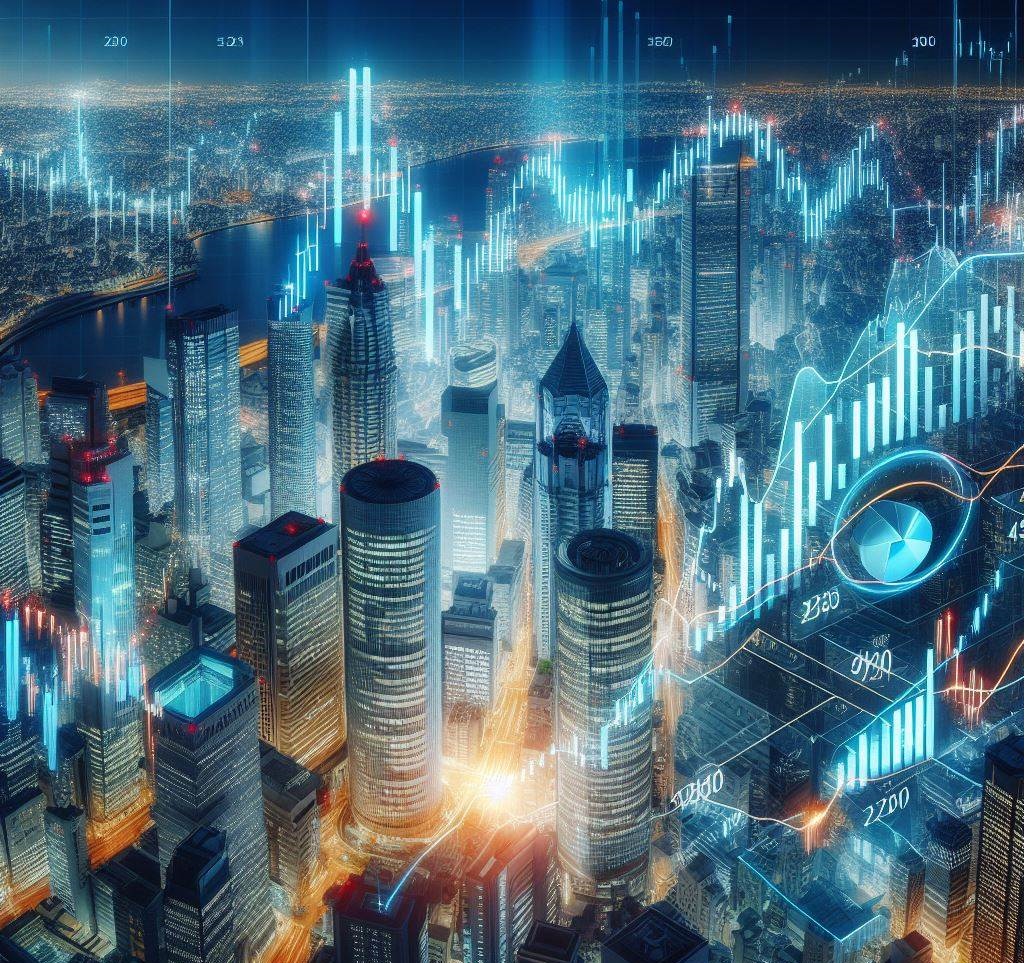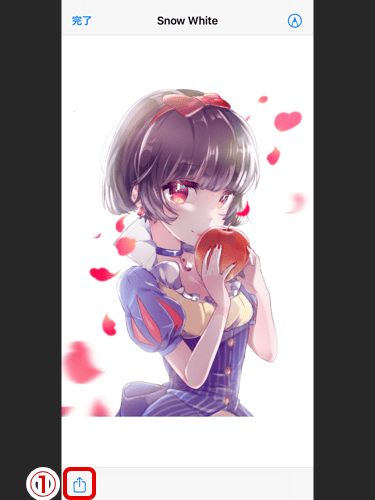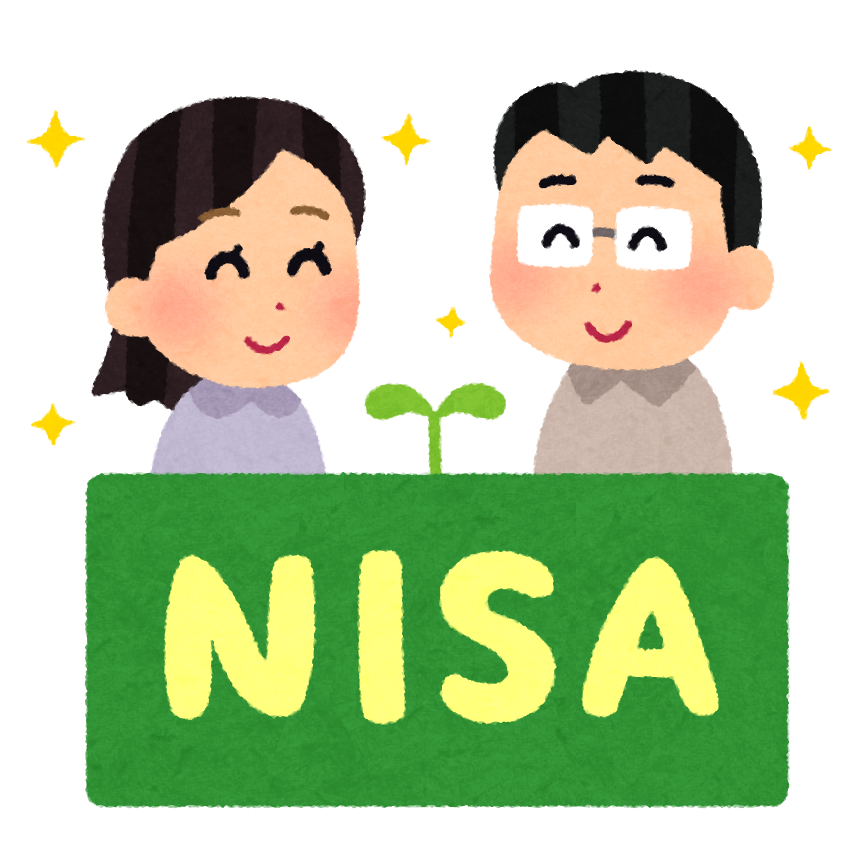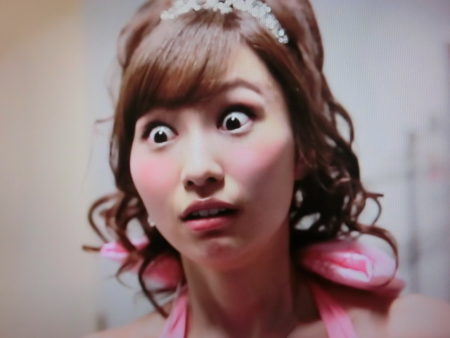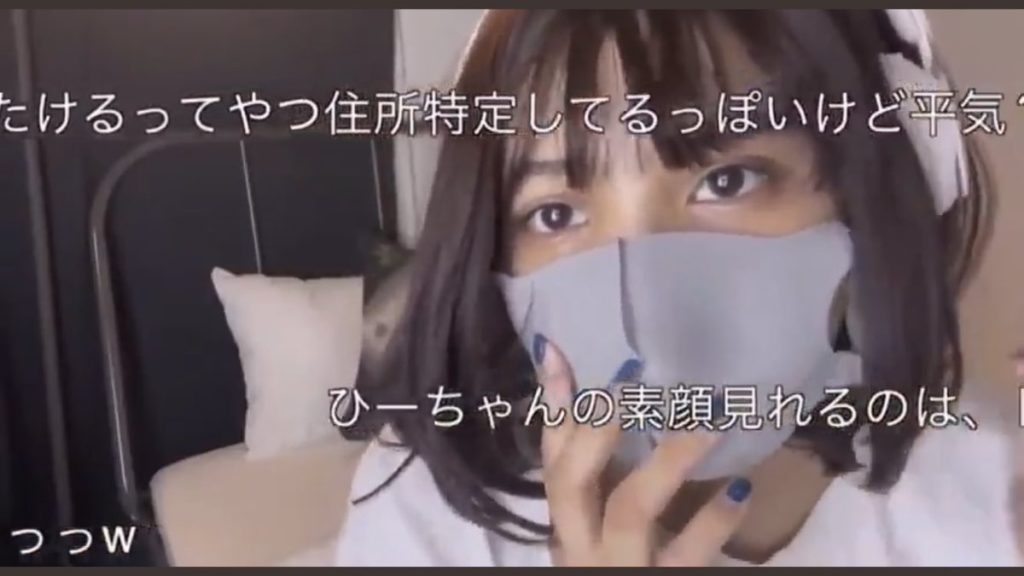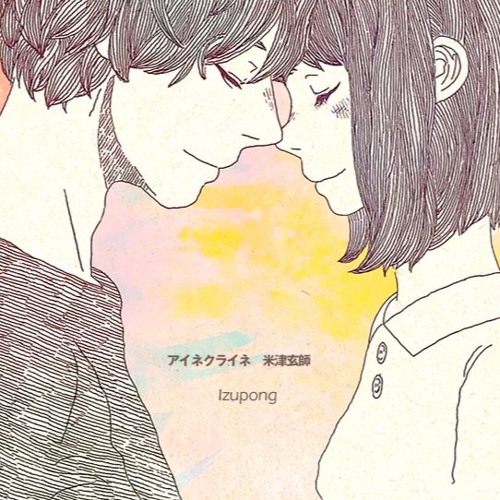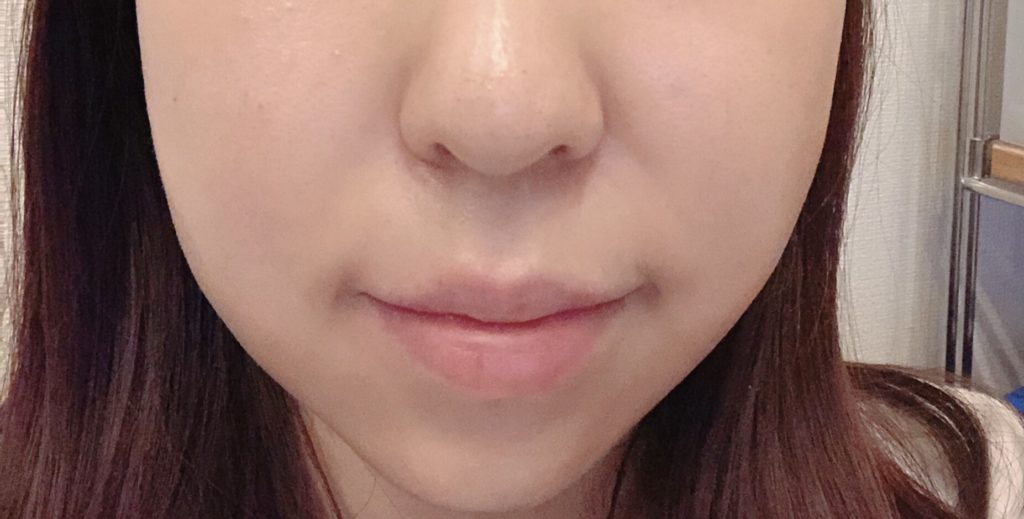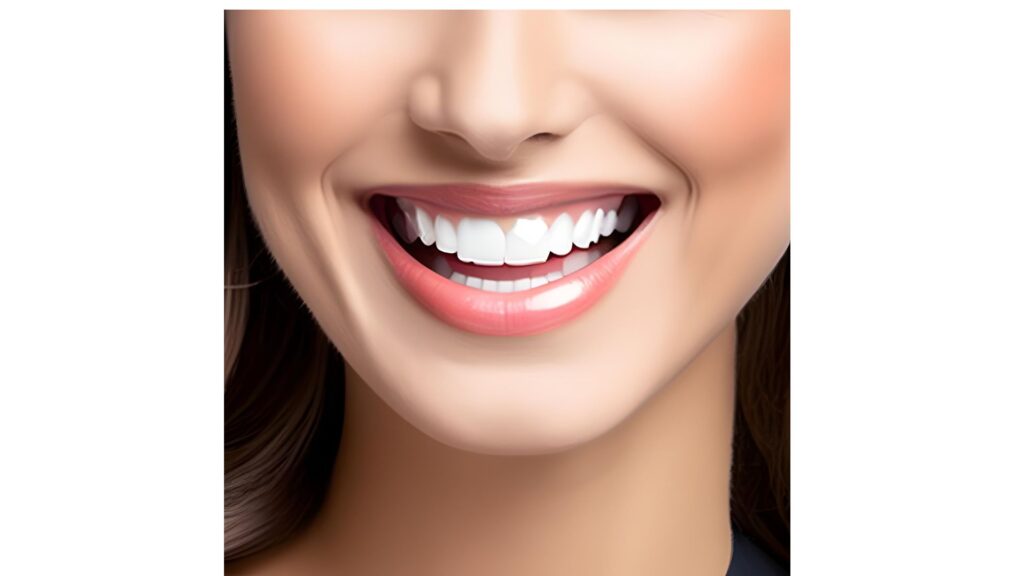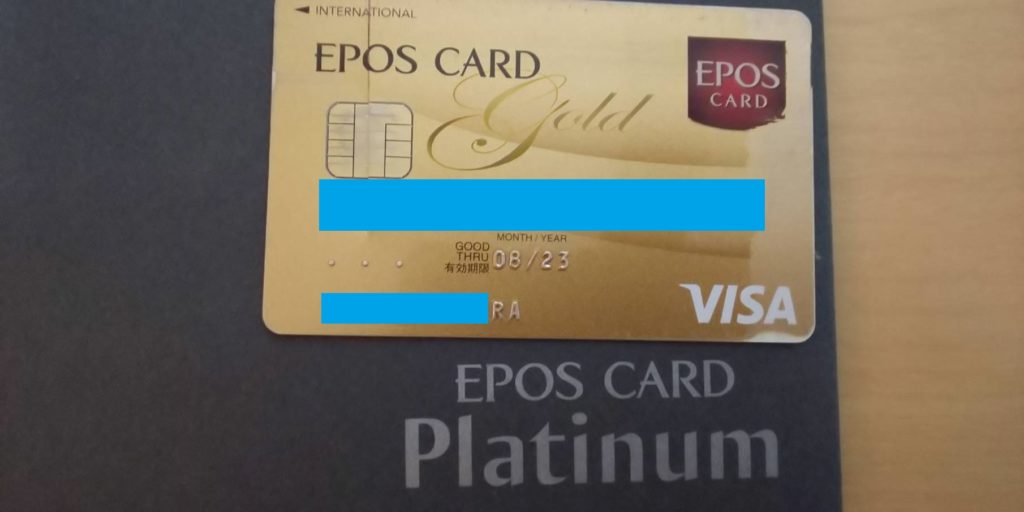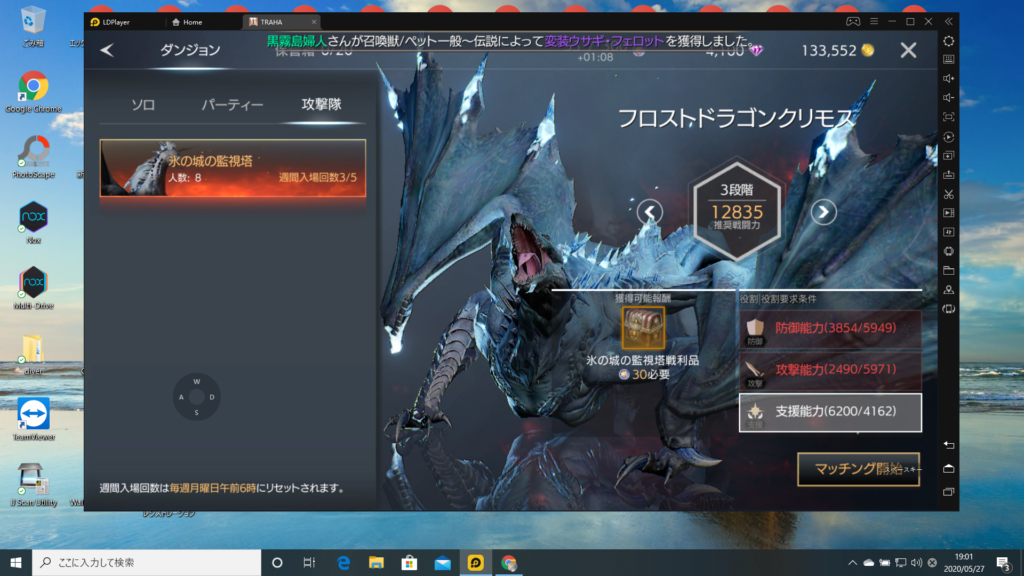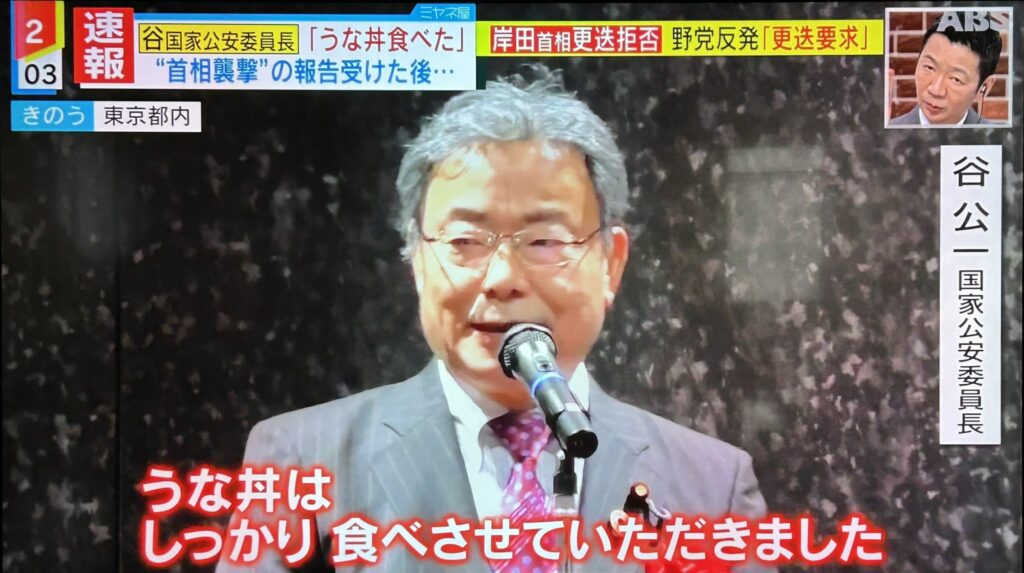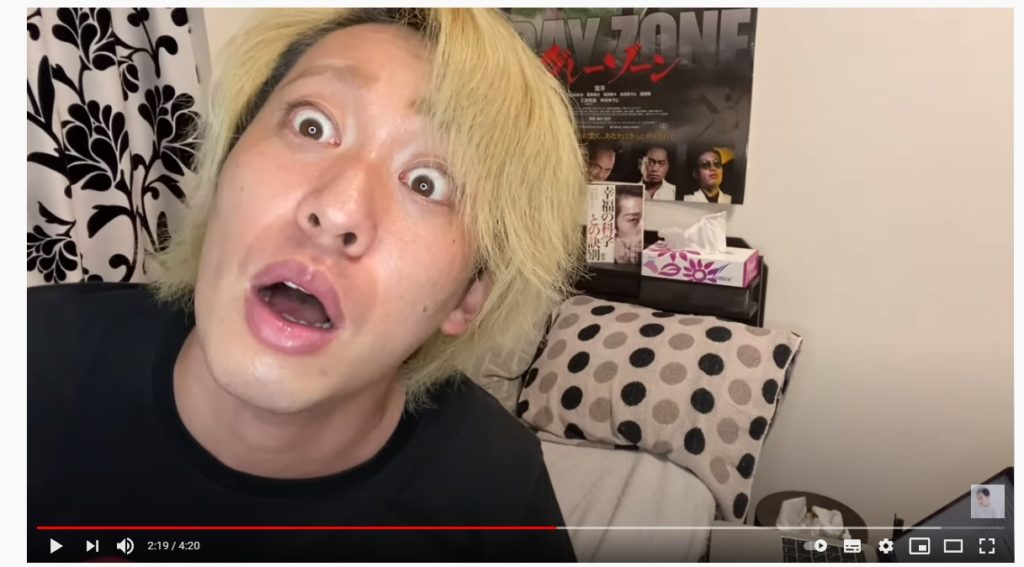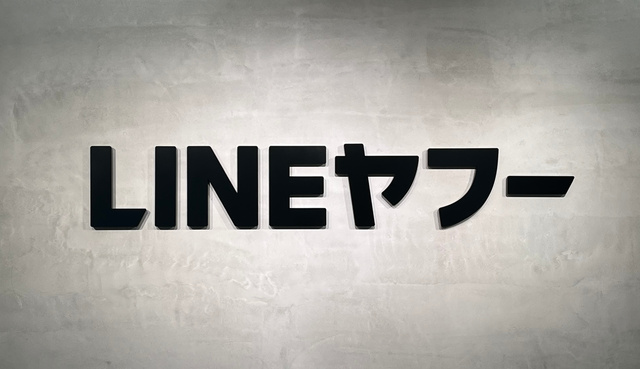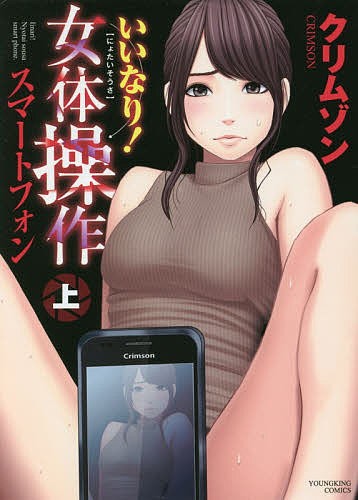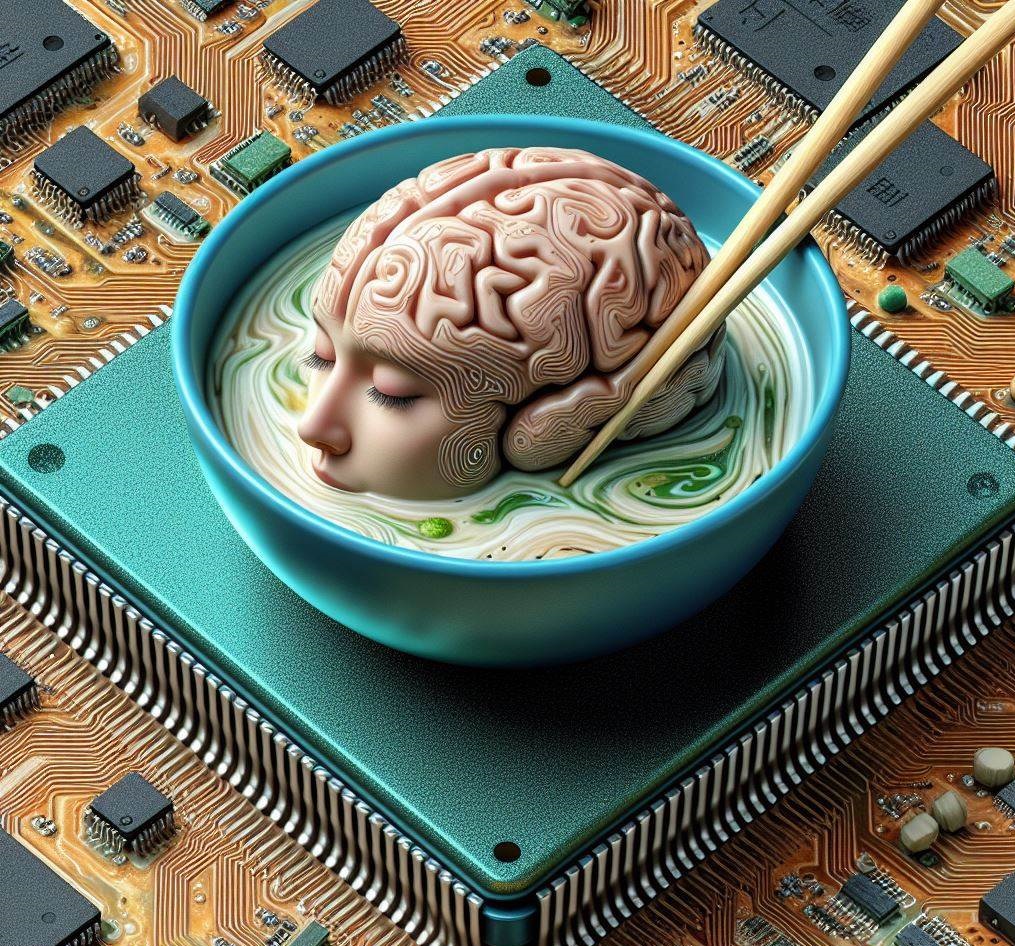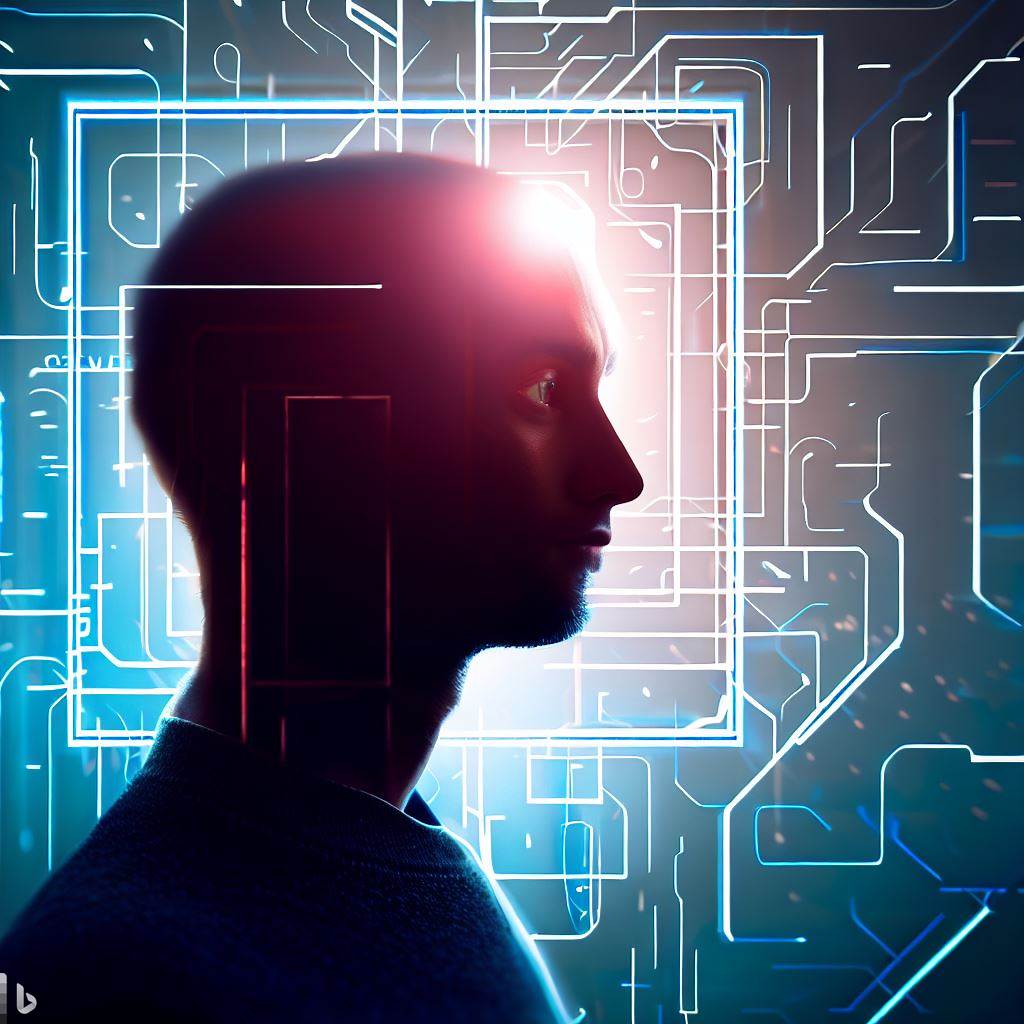近年、都合の悪い事実に対処する際、陰謀論という言葉がしばしば使われています。しかし、興味深いことに、陰謀論は都合の悪い事実を否定する際にのみ登場し、明らかな嘘に対しては使用されない傾向があります。本記事では、この現象に焦点を当て、その背後にある理由について考察します。
1. 陰謀論とは何か
陰謀論は、一般的に、秘密結社や陰謀によって操られているという信念を指します。これらの信念は、しばしば現実の出来事や事実を異なる視点から捉え、否定的な言語で表現されることがあります。
2. 都合の悪い事実と陰謀論
都合の悪い事実に対処する際、陰謀論が登場することがあります。これは、特定の出来事や情報に対して、秘密結社や陰謀が絡んでいると主張し、その事実を否定しようとするものです。しかし、この主張は根拠が薄く、科学的な裏付けがないことが多いため、信頼性に疑念を抱くことが重要です。
3. 明らかな嘘と陰謀論
一方で、明らかな嘘や虚偽の情報に対しては、陰謀論が使用されない傾向があります。これは、事実とは異なる情報を広める際には、陰謀論を用いず、他の言語や手法を選ぶことが多いためです。これにより、事実を歪曲しやすく、誤解や混乱が生まれることがあります。
4. 言葉の使い方に警戒が必要
陰謀論の使用は、情報の信頼性や透明性に対する懸念を引き起こすことがあります。言葉の使い方には慎重さが求められ、都合の悪い事実に対処する際にも客観的な情報検証とクリティカル・シンキングが大切です。
5. まとめ
都合の悪い事実に対処する際、陰謀論という言葉が登場する一方で、明らかな嘘には別の言葉や手法が用いられることが多いことが指摘されます。言葉の使い方に警戒し、客観的な情報検証を行うことが、真実と誤解を見分ける上で不可欠です。情報を正しく評価し、クリティカル・シンキングを備えることで、健全な社会づくりに寄与することができます。











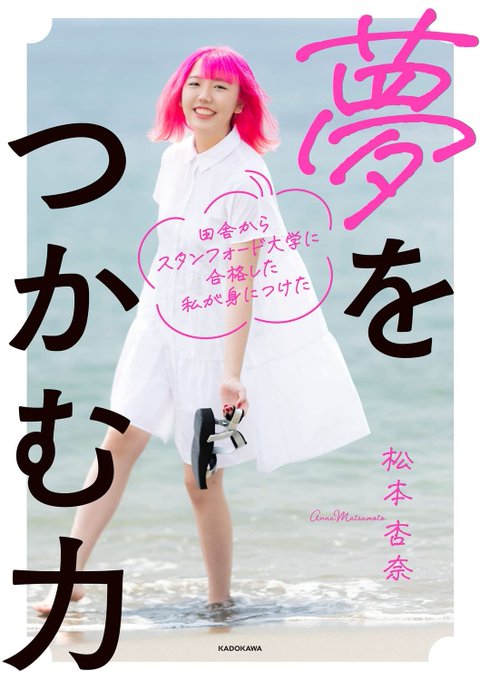


















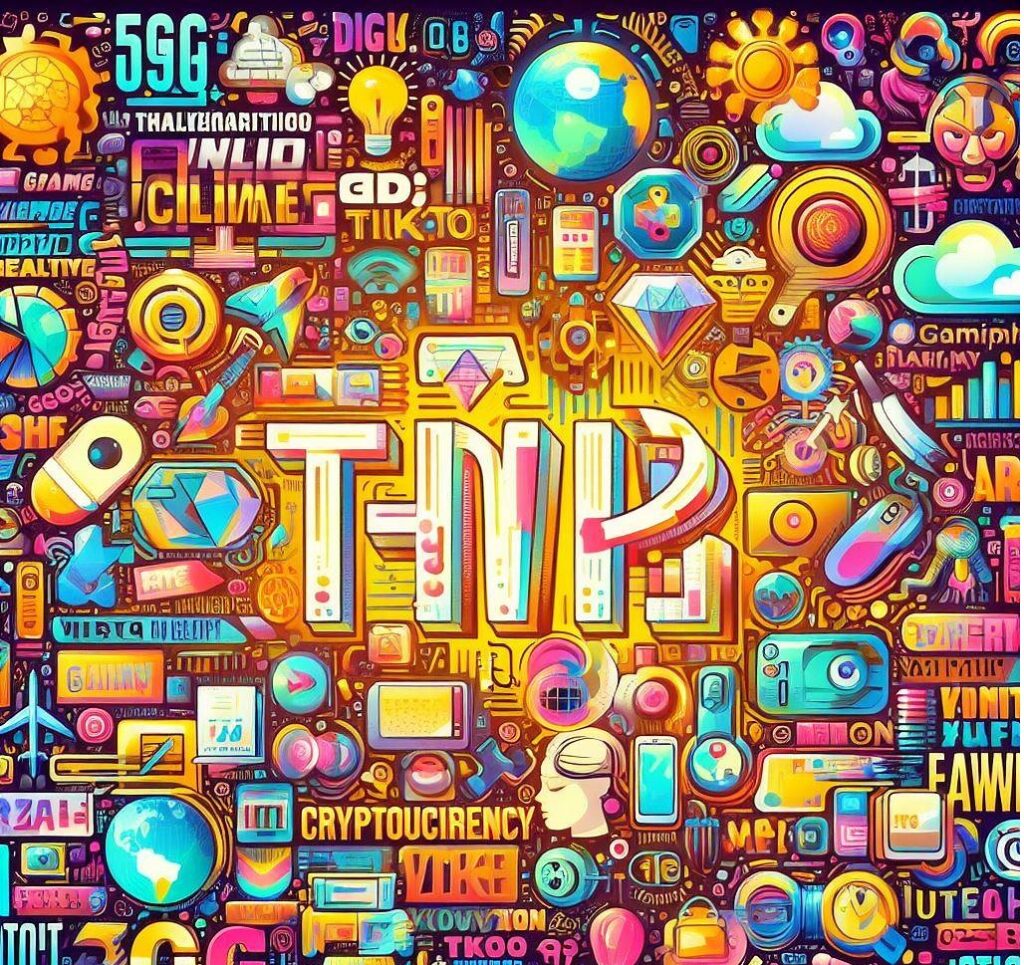



















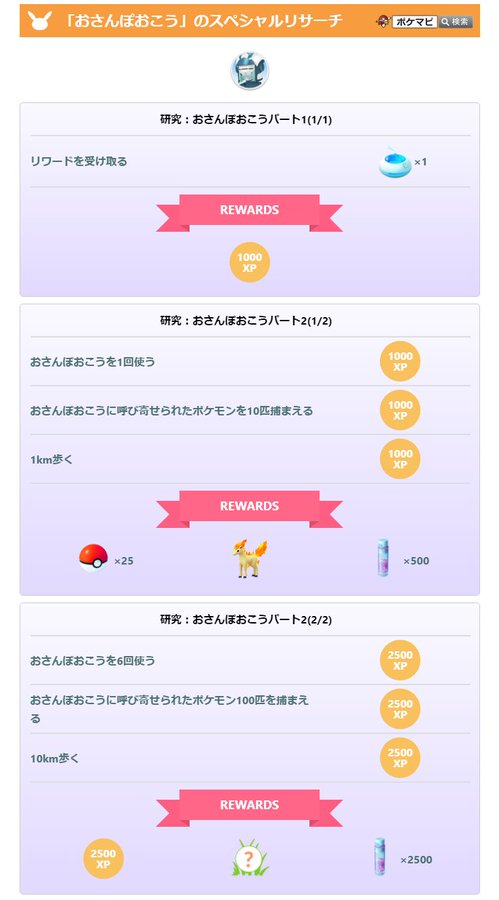



































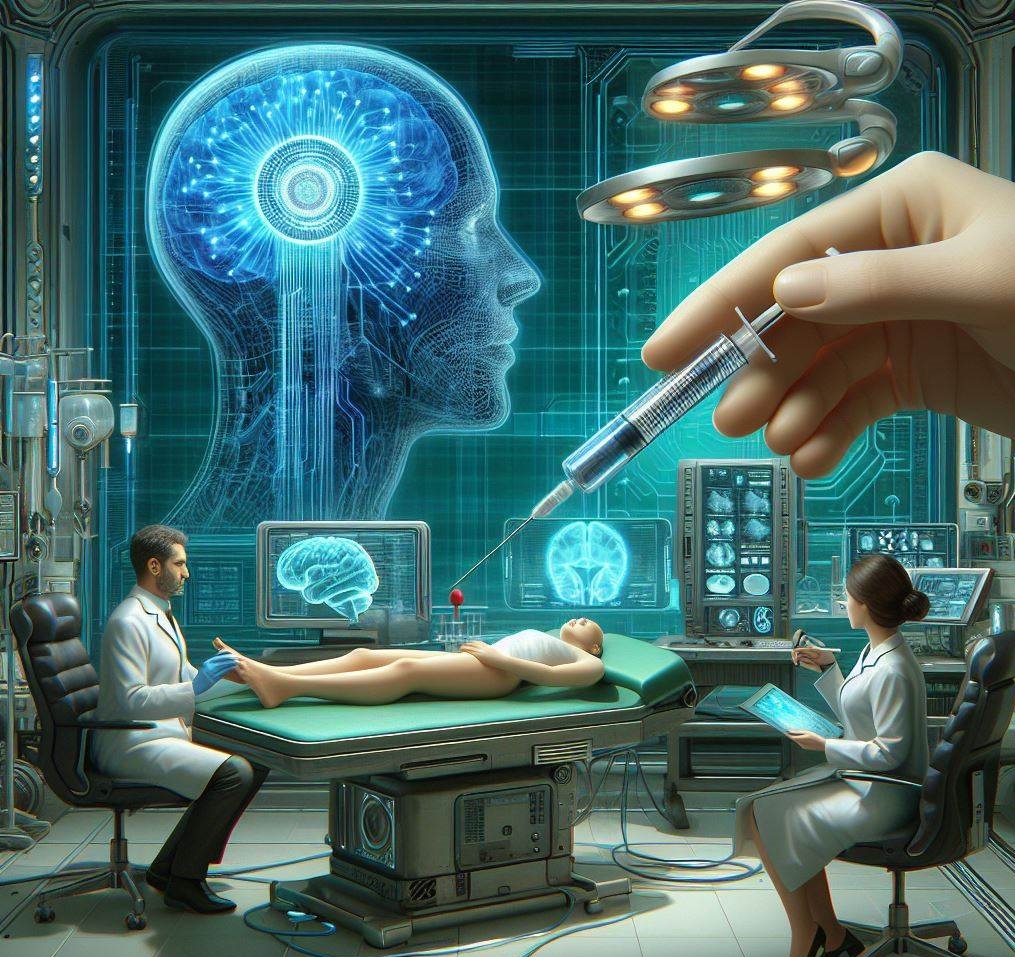

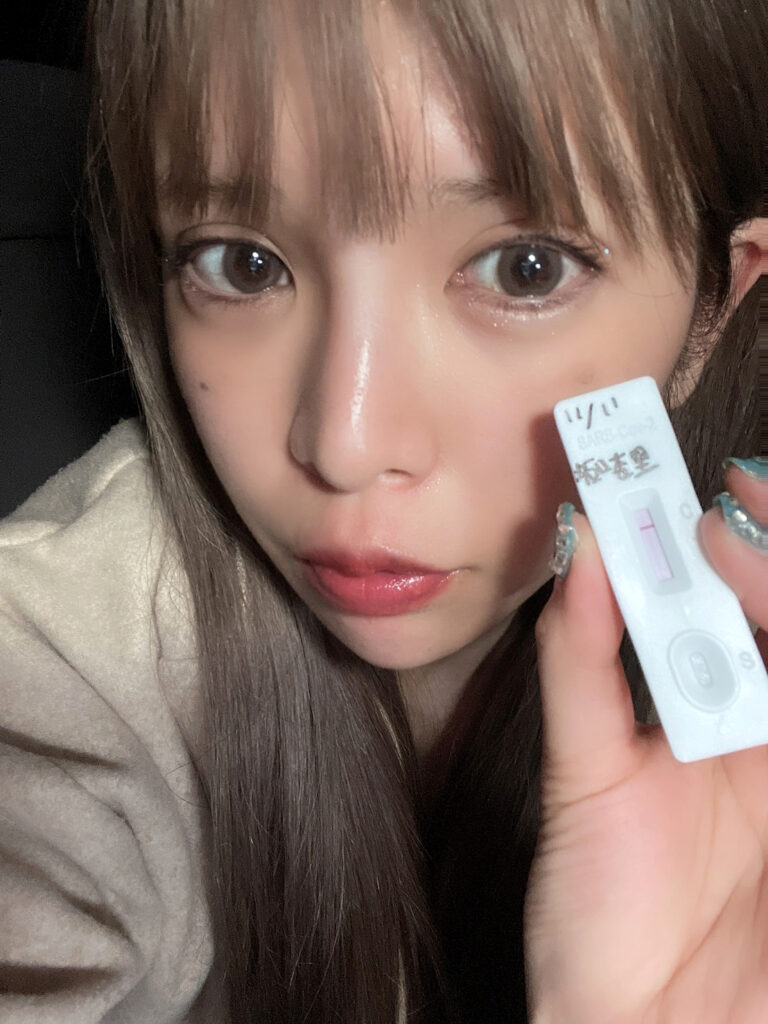








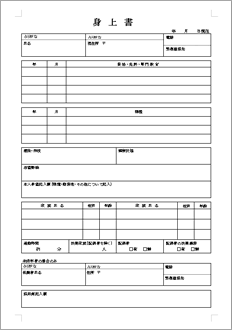




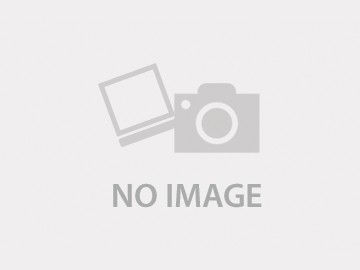
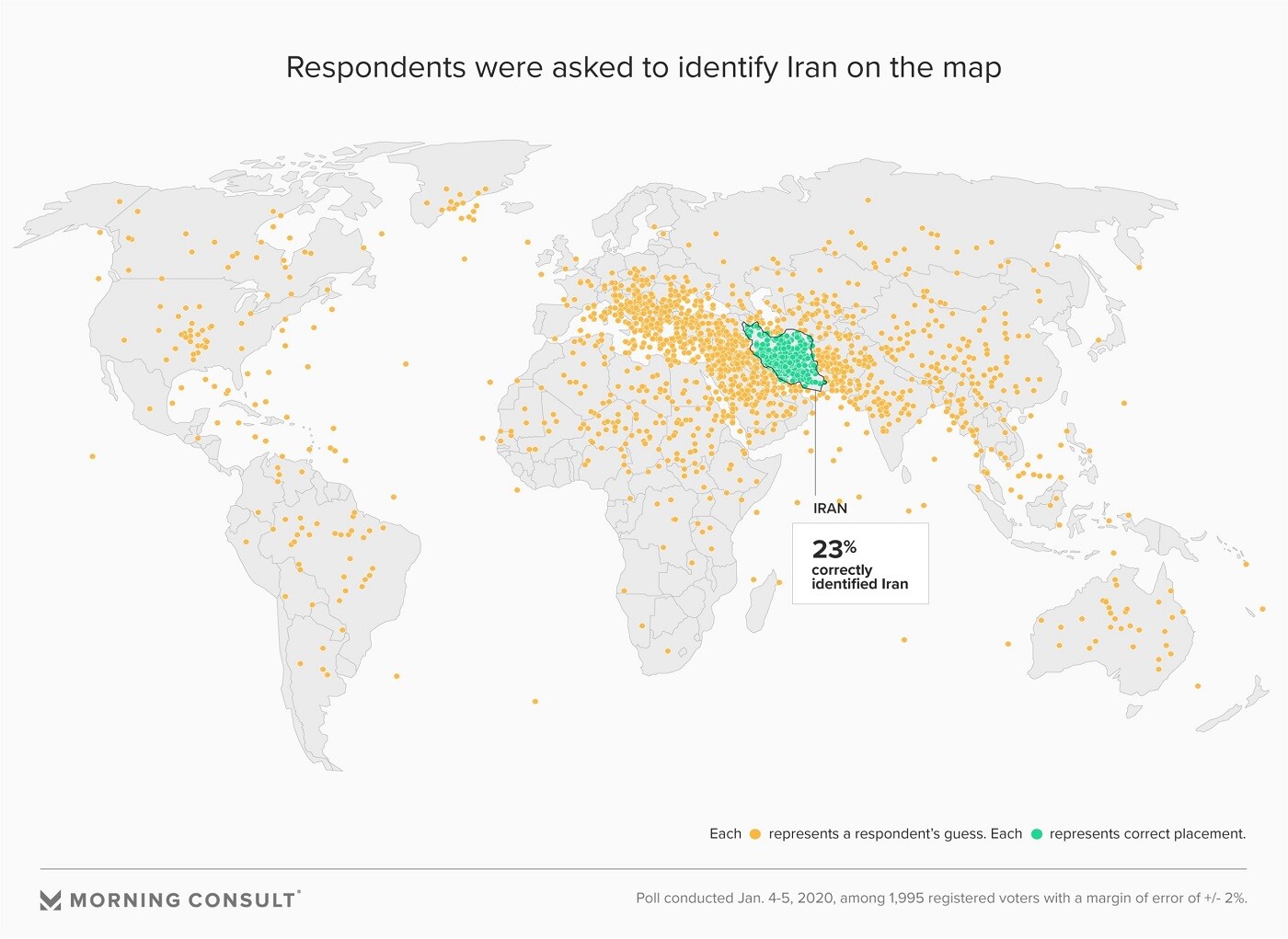








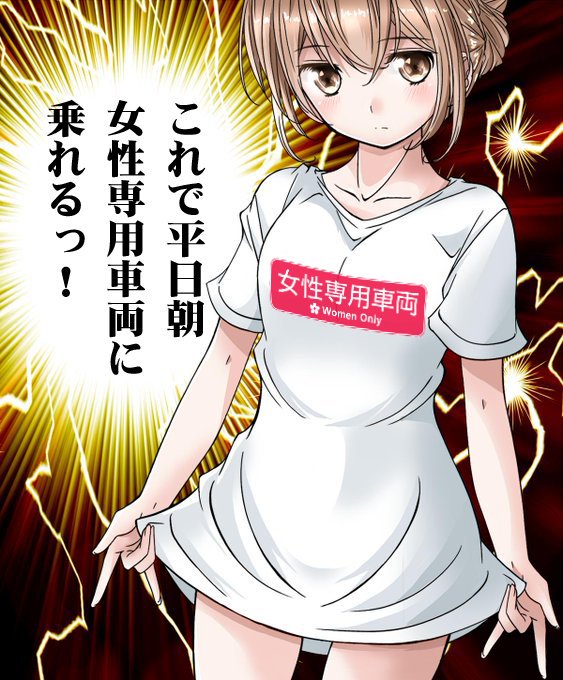





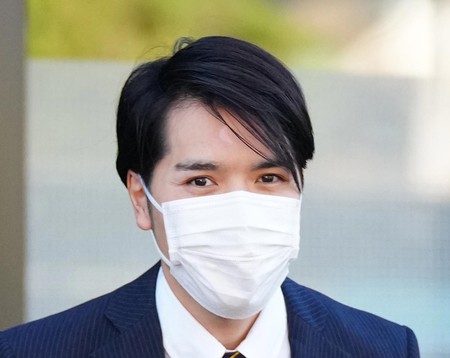

















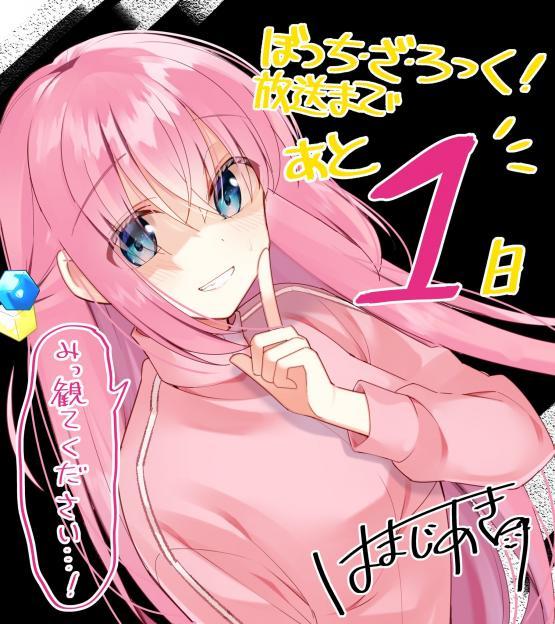
、えちえちなキャミソール姿を公開!「胸元がセクシーすぎる!」ファン悶絶-1024x769.jpg)