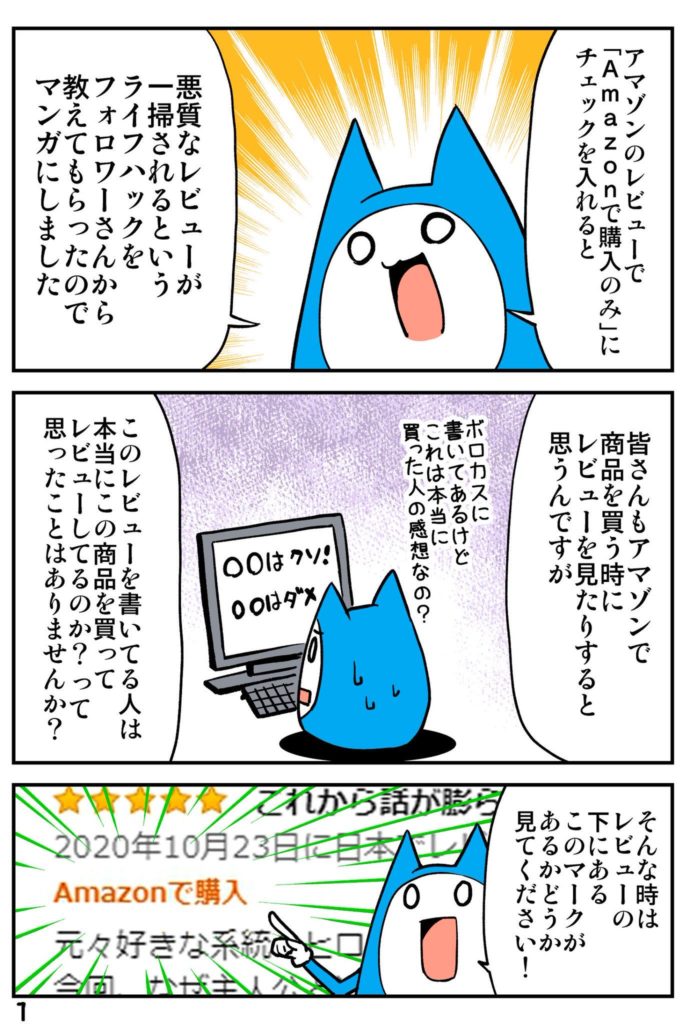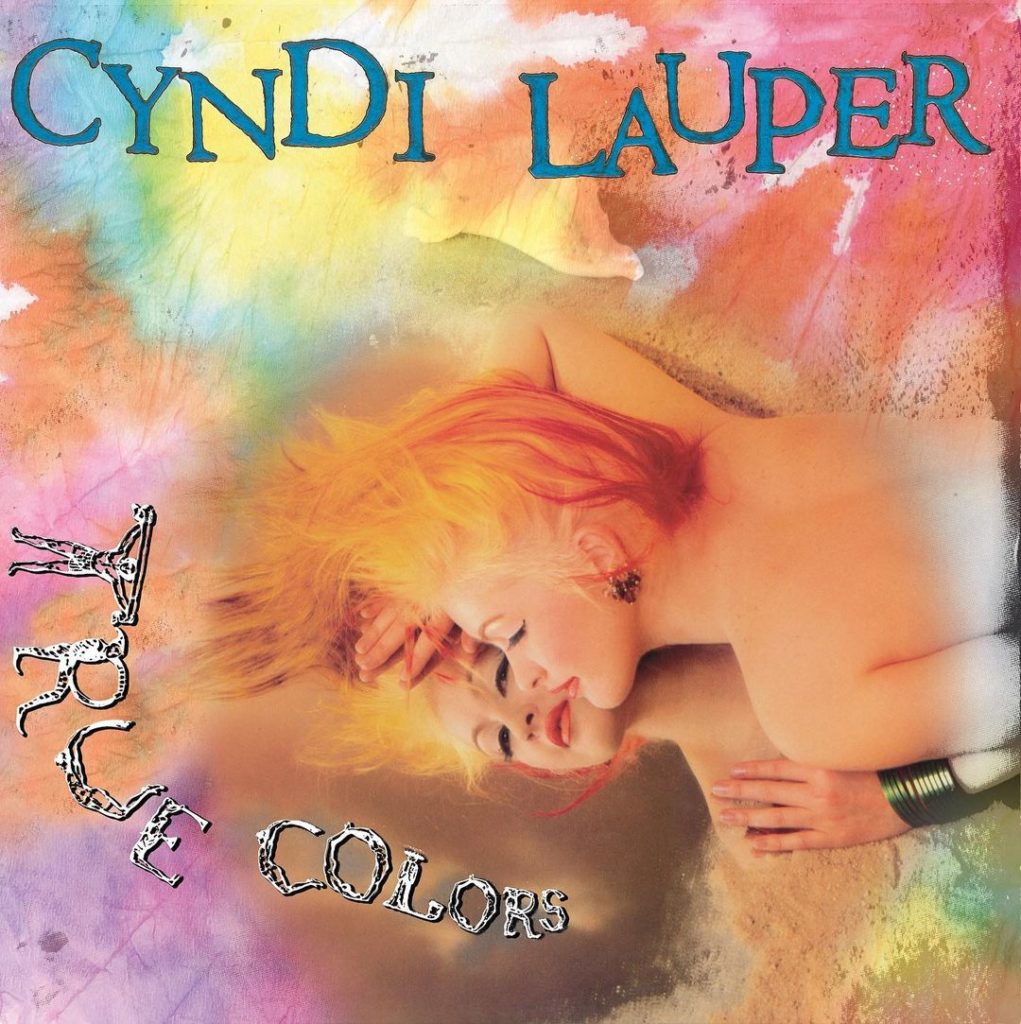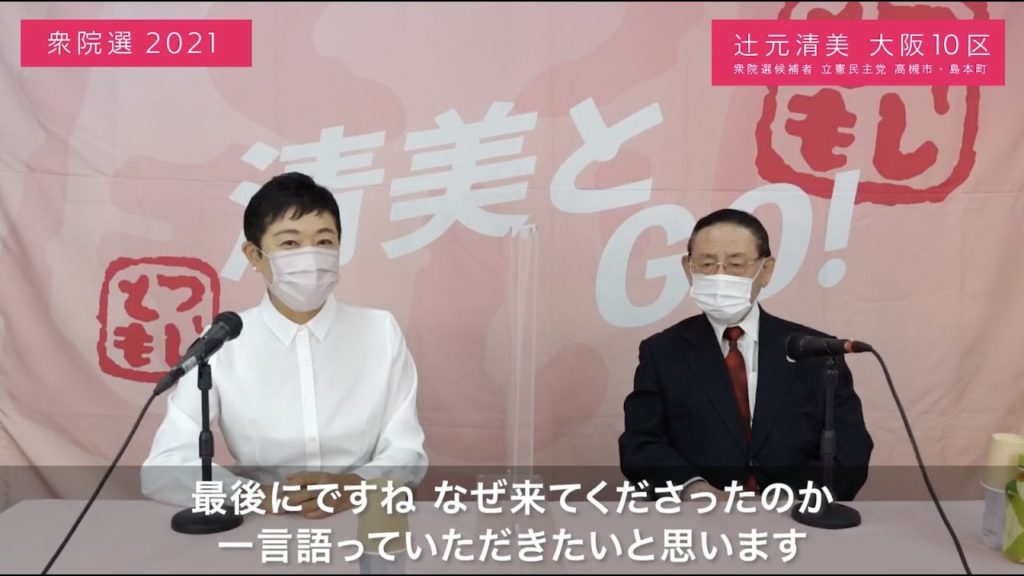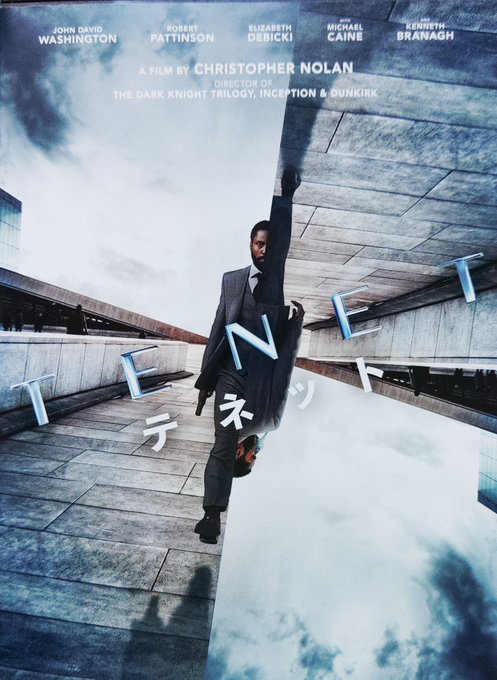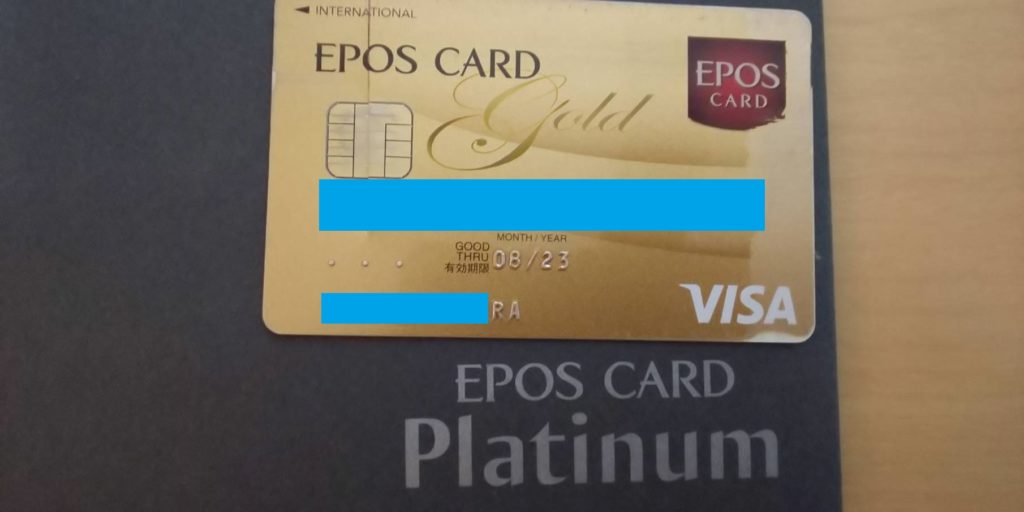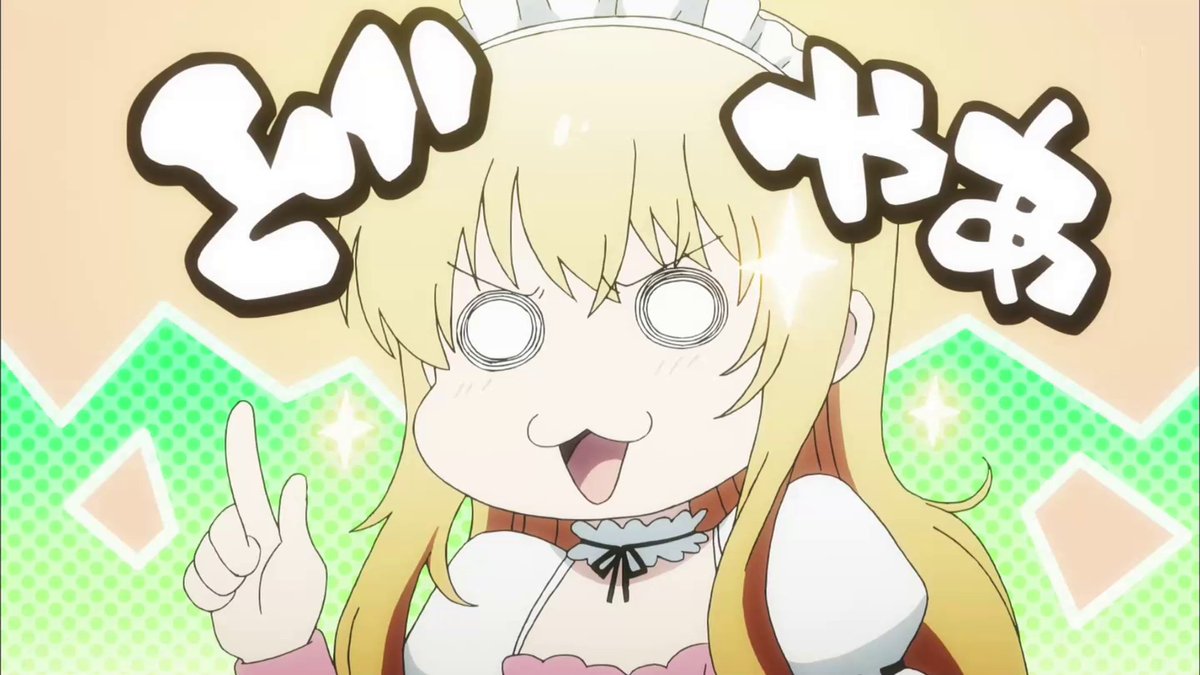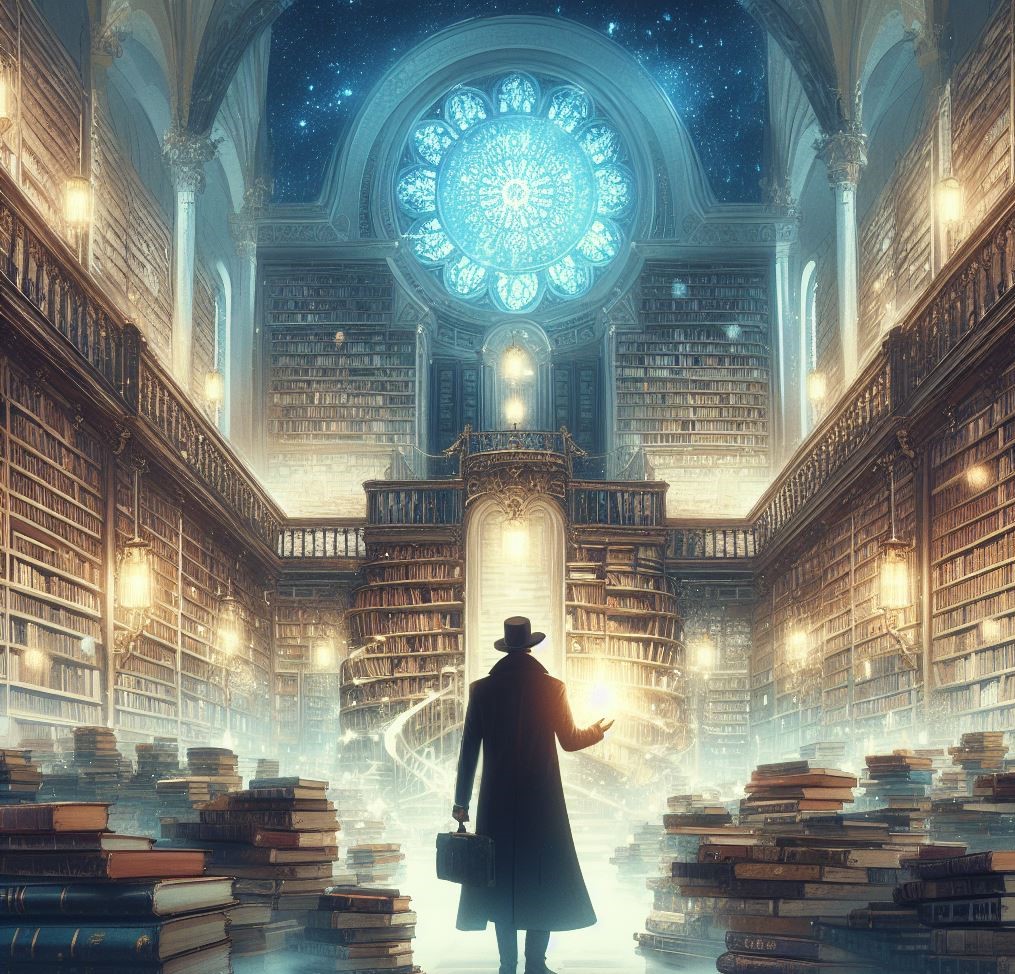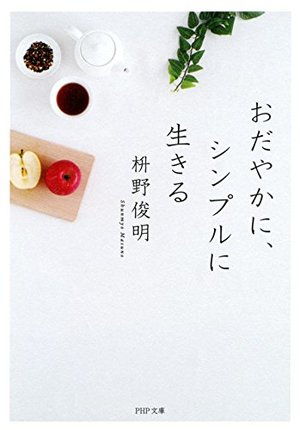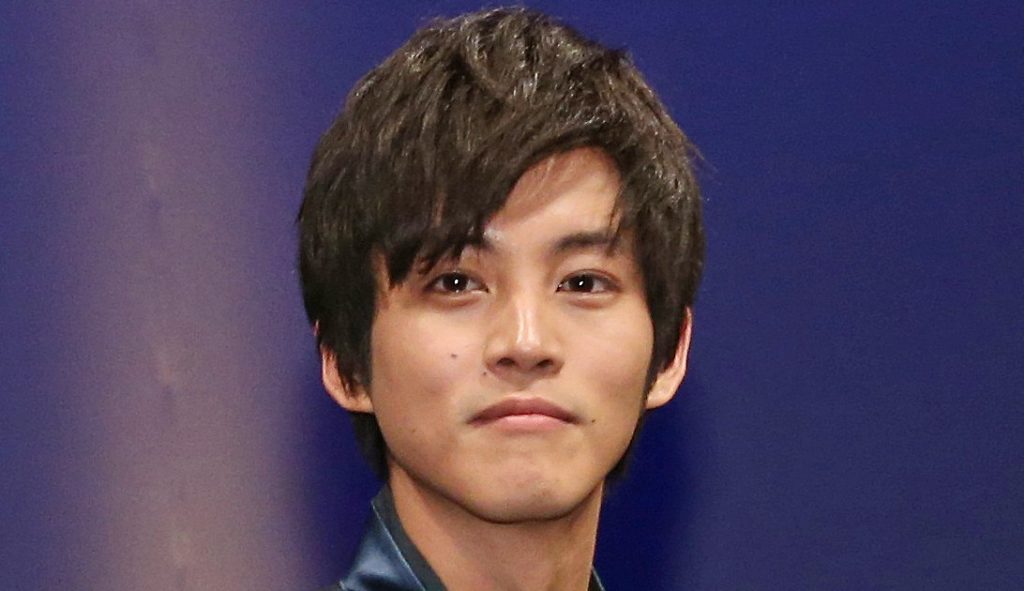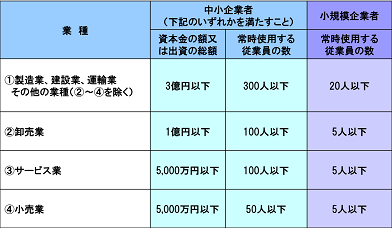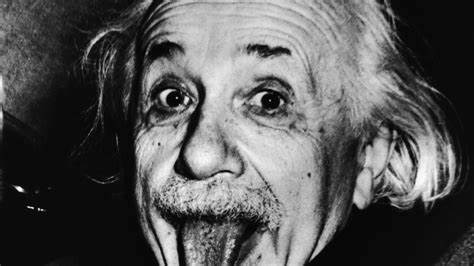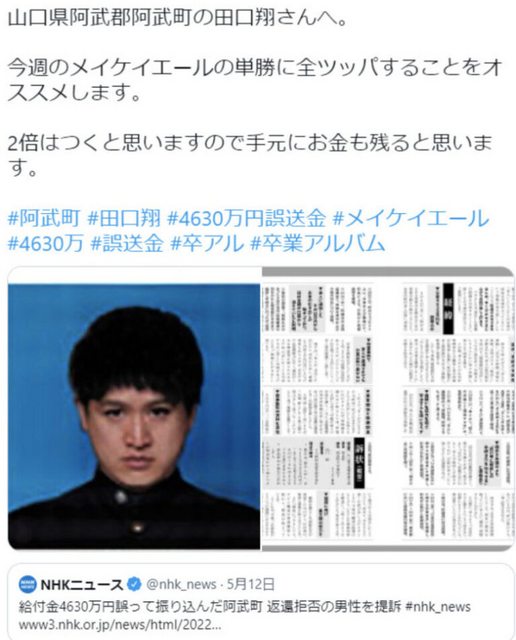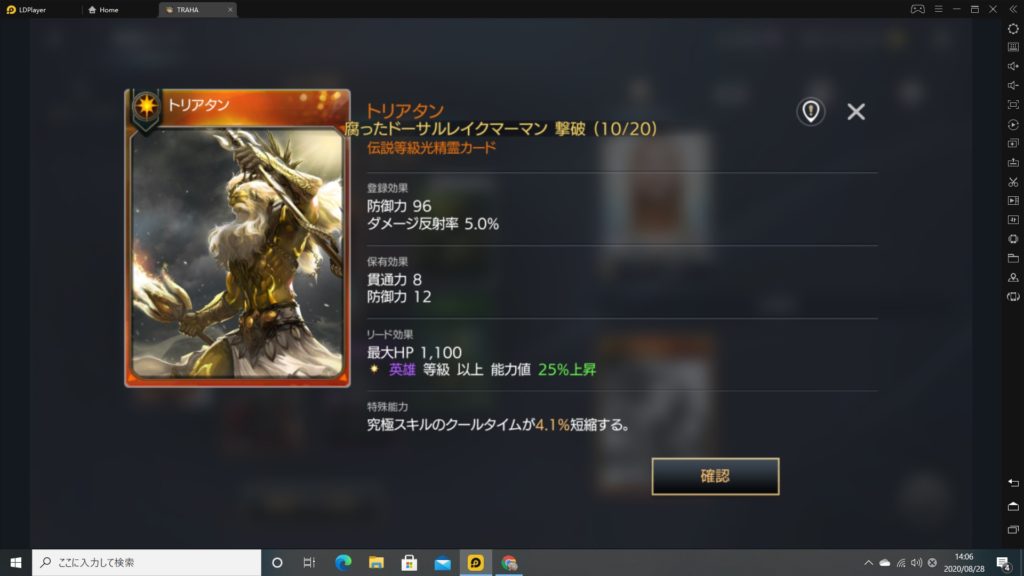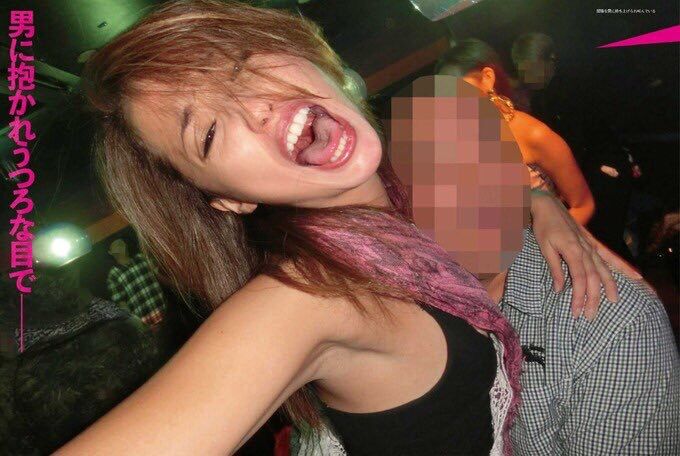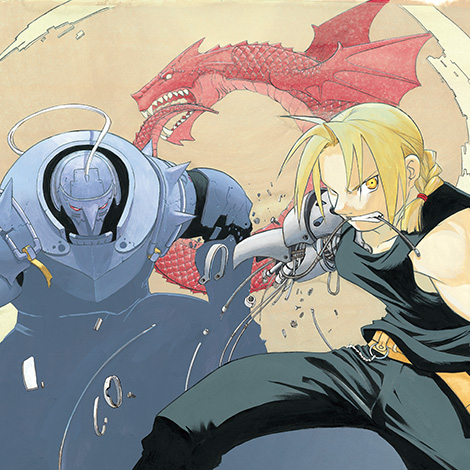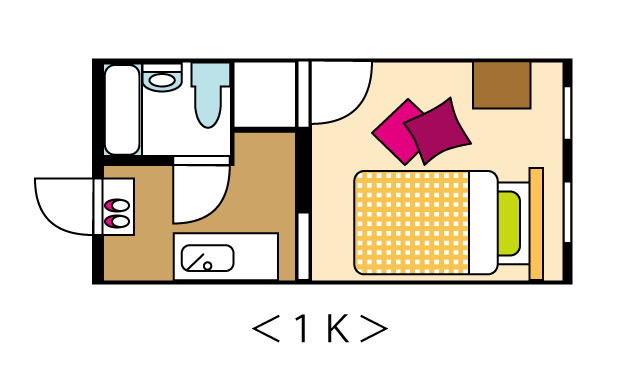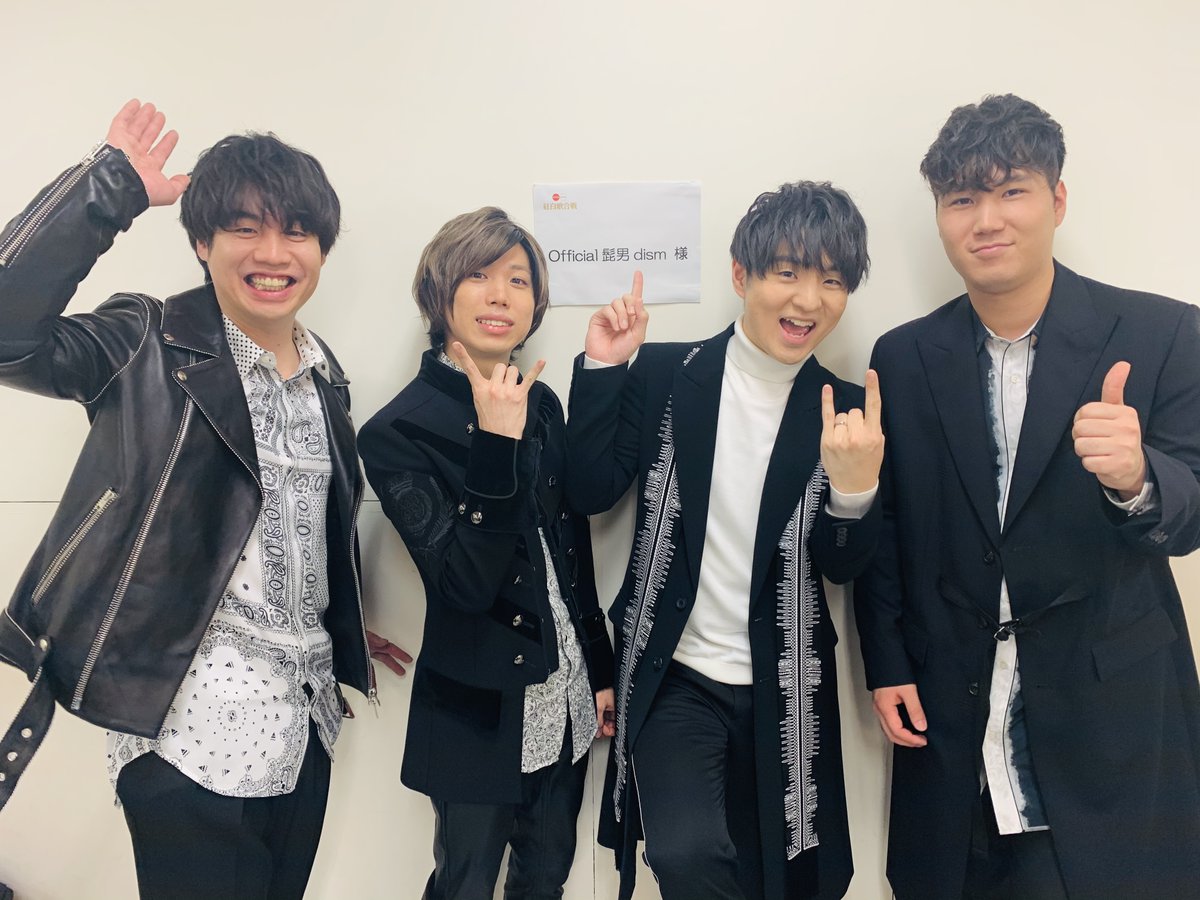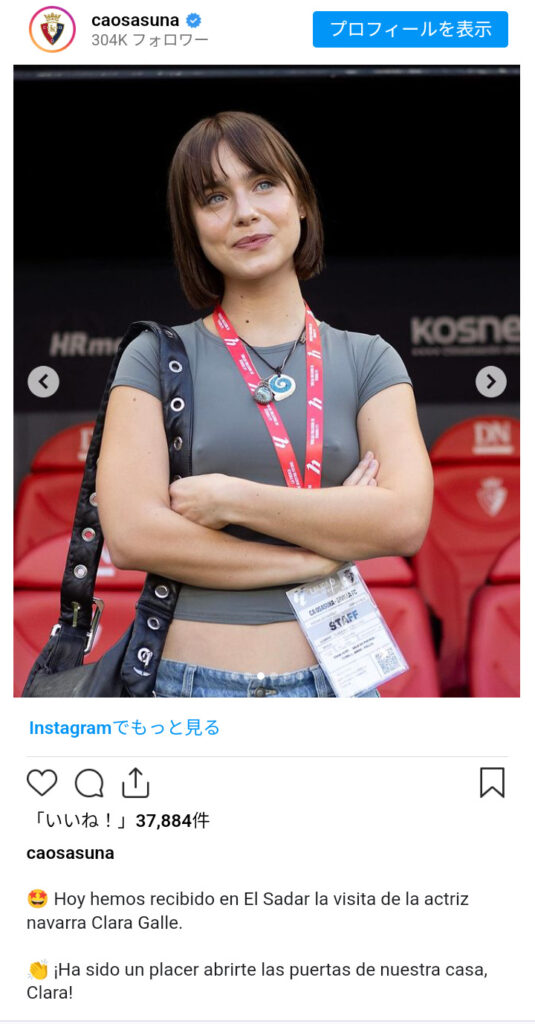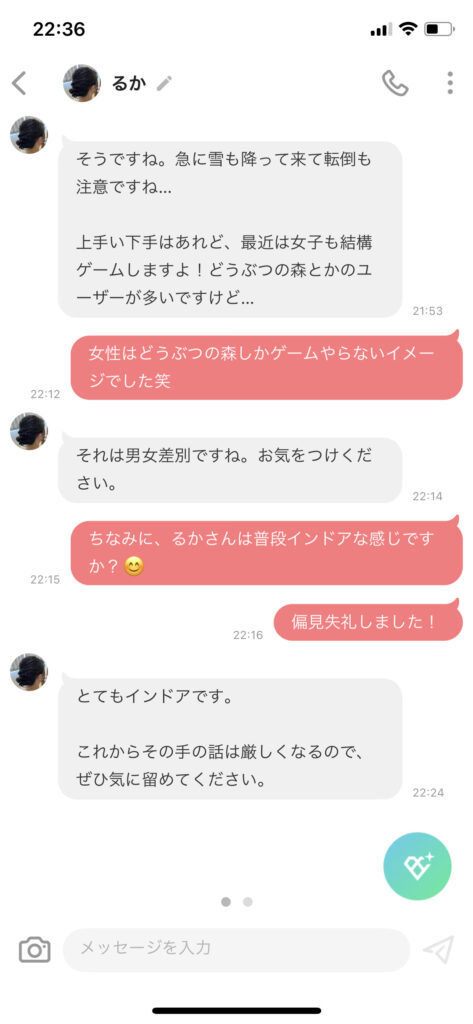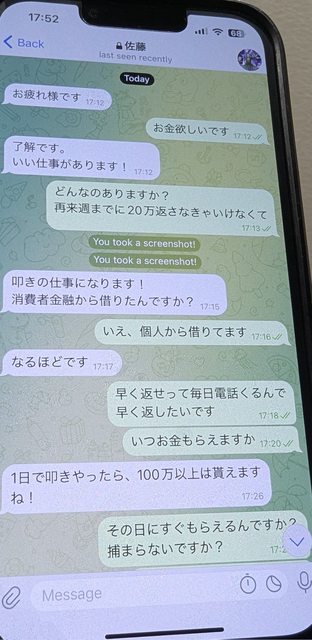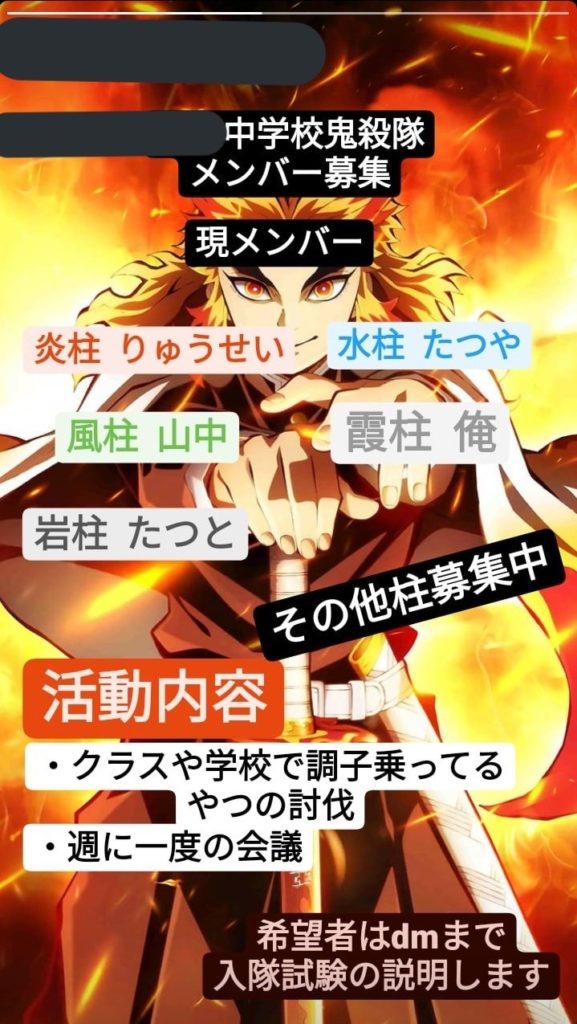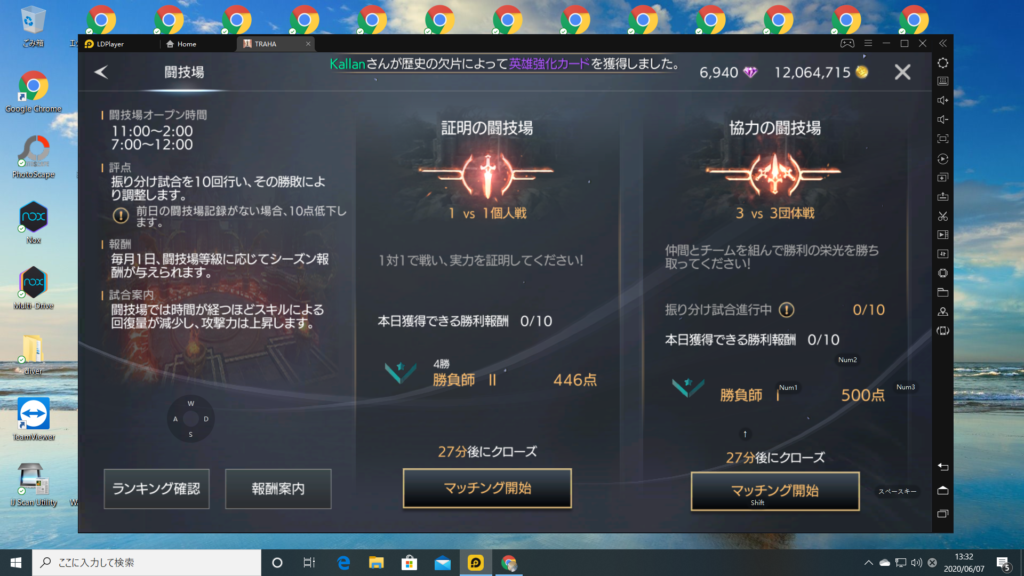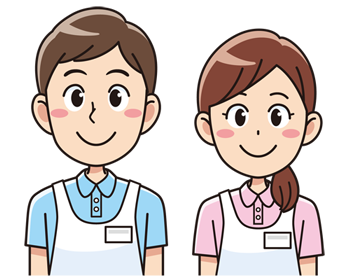1990年代半ば、日本の経済政策は大きな変革を経験し、「規制緩和」、「税制のフラット化」、「資本行動の自由化」などが導入されました。これらの政策は経済に大きな影響を及ぼし、経済格差の拡大に寄与しました。しかし、なぜ多くの日本人が自らにとって不利な政策を受け入れたのでしょうか。その主な要因を探ります。
1. 「規制緩和」への期待と官僚支配の錯覚
一つ目の要因は、「規制緩和」が官僚支配を打破し、市場の活性化をもたらす特効薬であるとの錯覚でした。多くの人々は、過剰な規制が経済の発展を阻害していると信じ、規制緩和が新たな機会を生み出すと期待しました。
2. 政策のキャッチフレーズとマスメディアの役割
二つ目の要因は、首相の私的諮問委員会における学者たちのキャッチフレーズと、それを大々的に報じたマスコミの存在でした。政策変更は簡潔で魅力的な言葉で表現され、一般市民に対して説明されました。これにより、政策が一般の人々に受け入れやすくなりました。
3. マスメディアの情報発信力
三つ目の要因は、マスメディアの情報発信力です。政策変更に関する情報は広く伝えられ、政策提言者や支持者の意見が広く知れ渡りました。マスコミの役割は政策を広く浸透させるのに貢献しました。
4. 小選挙区制度の導入
四つ目の要因は、小選挙区制度の導入でした。この制度は選挙戦を激化させ、個々の議員が選挙区の選民との強い結びつきを求めるようになりました。その結果、個別の政策提案やキャッチフレーズが有権者に訴える重要性が増し、政策の受け入れが促進されました。
これらの要因が組み合わさり、多くの日本人が政策変更を受け入れる一因となりました。しかし、一方で、その後の経済格差拡大や課題の浮上も見逃せません。政策変更の結果として生じた格差問題に対処するためには、新たな政策と社会的な協力が必要です。

















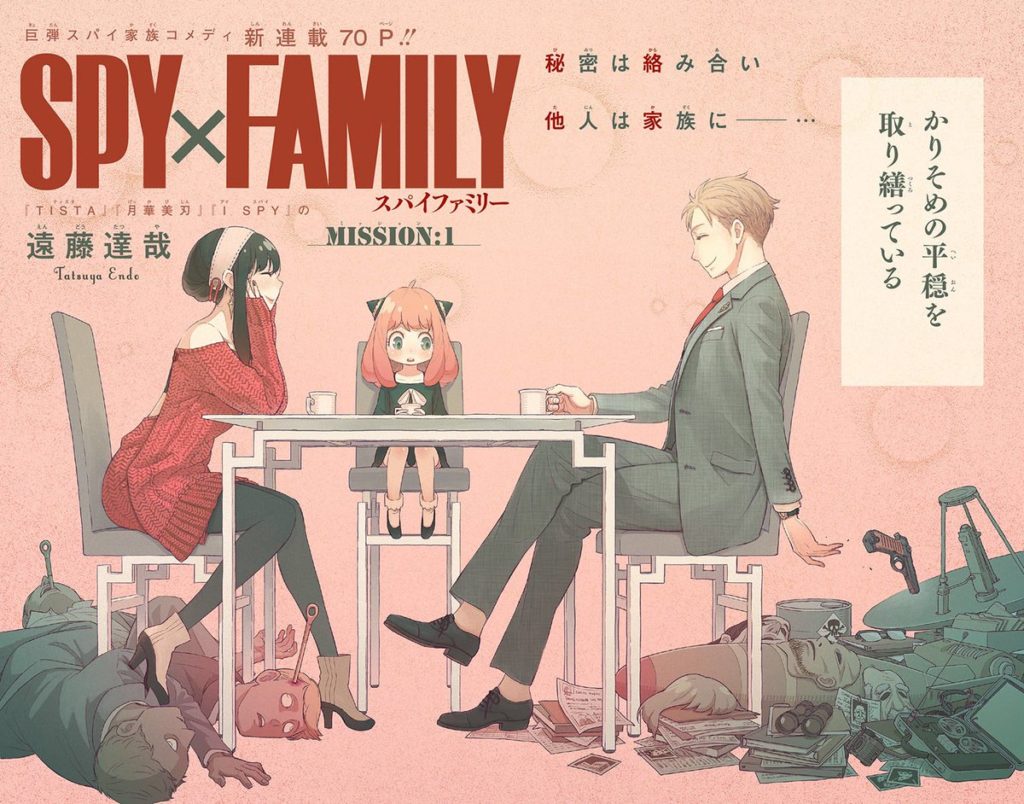








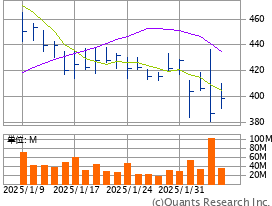











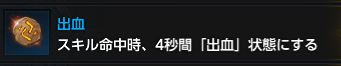

(わが国で未承認の難治性ニキビ治療薬).jpg)





















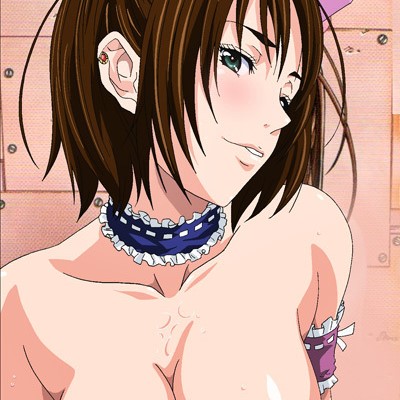

























.jpeg)